図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2025年版
小林 満男
『世界を変えるSHIEN学 : 力を引き出し合う働きかた』
- 舘岡康雄 フィルムアート社 2012年
今年(2025)の正月、久しぶりに著者の舘岡さんとお会いしました。数年に一度、お会いする程度のおつきあいですが、社会人大学院(産能大学大学院修士課程)の同級生であった頃(今から約30年前)から舘岡さんが温めておられた”SHIEN”の考えが、お会いするたびにひろがり、発展をみせているところに魅力を感じていました。著者は産能大学大学院修士課程修了後、東京工業大学大学院博士課程に進まれ、“SHIEN学”で博士号を取得され、その後は、静岡大学大学院の教授に就任されています。彼の活躍模様は、著書の著者プロフィールに紹介されているので省略しますが、大学内にとどまらず“SHIEN”に関するワークショップや講演活動等、積極的に展開されておられます。お会いした後で、あらためて彼の博士論文をベースにした著書である『利他性の経済学』を読んでみました。その時の感動を学生の皆さんに紹介したく、推薦文を書かせて頂くことにしました。
皆さんにご紹介したい本は、『世界を変えるSHIEN学 力を引き出し合う働きかた』です。この本は、『利他性の経済学』をもっと分かりやすく、SHIEN学の入門書の位置づけでまとめられているので、まずは気楽に手に取ってこの本を一気に読んでみることをおすすめします。
第1章は、SHIEN学入門として、なぜ(支援ではなくて)SHIENなのか等、時代の大きなうねりをパラダイムとしてとらえ、その変化と対応させながら丁寧に説明されています。第2章は、SHIEN学に触れたフォトグラファー、文筆家や病院の院長他が登場します。実務経験がないと実感が湧きにくいかもしれませんが、ここのところは一気に読むことをおすすめします。そして応用編の第3章は、SHIEN学の未来を考えると題して、今後の世界や社会を一緒に考える内容となっています。ここはじっくりと時間をかけて、自分の考えや思いをぶつけながら(著者と対話しながら)、読み進めるといいでしょう。どうしても時間がない人は、「目次」と「はじめに」だけでもいいでしょう。わずか15ページに目を通すだけでもご利益はあるはずです。何かを感ずるものがあったら、ぜひその先「序章 支援とSHIENの違いとは(基本ワード解説-SHIEN学がよくわかる4つの言葉)」も読んでみてください。
本書を読み、更に理解を深めたい方には、引き続き『利他性の経済学:支援が必要となる時代へ』(新曜社)を読むことをお薦めします。あるいは、Webで“舘岡康雄”と検索してみるといいでしょう。多彩な活動模様や紹介記事等に接することで、SHIEN学の面白さ、奥深さを感じて頂けるのではないでしょうか。
皆さんにご紹介したい本は、『世界を変えるSHIEN学 力を引き出し合う働きかた』です。この本は、『利他性の経済学』をもっと分かりやすく、SHIEN学の入門書の位置づけでまとめられているので、まずは気楽に手に取ってこの本を一気に読んでみることをおすすめします。
第1章は、SHIEN学入門として、なぜ(支援ではなくて)SHIENなのか等、時代の大きなうねりをパラダイムとしてとらえ、その変化と対応させながら丁寧に説明されています。第2章は、SHIEN学に触れたフォトグラファー、文筆家や病院の院長他が登場します。実務経験がないと実感が湧きにくいかもしれませんが、ここのところは一気に読むことをおすすめします。そして応用編の第3章は、SHIEN学の未来を考えると題して、今後の世界や社会を一緒に考える内容となっています。ここはじっくりと時間をかけて、自分の考えや思いをぶつけながら(著者と対話しながら)、読み進めるといいでしょう。どうしても時間がない人は、「目次」と「はじめに」だけでもいいでしょう。わずか15ページに目を通すだけでもご利益はあるはずです。何かを感ずるものがあったら、ぜひその先「序章 支援とSHIENの違いとは(基本ワード解説-SHIEN学がよくわかる4つの言葉)」も読んでみてください。
本書を読み、更に理解を深めたい方には、引き続き『利他性の経済学:支援が必要となる時代へ』(新曜社)を読むことをお薦めします。あるいは、Webで“舘岡康雄”と検索してみるといいでしょう。多彩な活動模様や紹介記事等に接することで、SHIEN学の面白さ、奥深さを感じて頂けるのではないでしょうか。
(以上)
『情報システム進化論 技術的世界観から脱却し人間を育む未来へ』
- 砂田薫 行政情報システム研究所 2025年
分かったようで、なかなか分からないものの一つとして、“情報システム”をあげる人がいる。情報システムは、私たちの身近にありながら、毎日何らかの形で利用しているにもかかわらず、情報システムに対するイメージや、そのかかわり方は人によってあまりにも多様である。そんなところがモヤモヤ感を醸し出しているのではなかろうか。そのモヤモヤ感を吹き飛ばしてくれるのが本書「情報システム進化論」である。
著者は、情報システム学会の会長(本年6月から、名誉会長)をつとめられている。情報システム学会は、人間中心の情報システムを志向し、ビジネス・研究領域の融合や情報システム人材の育成を目的とした学会である。
新潟国際情報大学の初代の情報文化学部長である(故)浦 昭二名誉教授の提唱で生まれた学会であり、現在、8名の本学教員が加入している(略)。
本書では、情報システムが人間の情報行動を支援する仕組みであり、情報を収集・処理・分析・伝達・保存したりする社会的(組織的・個人的)なシステムととらえている。そしてその情報システムを個人やその集合体である組織・社会という「人間系」とアナログ技術、デジタル技術も含む「機械系」とで構成される仕組みとしてまずはとらえ、その情報システムの進化のプロセスをみていく。そして「進化の最先端に位置付けられる情報システム」にかんしては、進化を機械系からだけでなく人間系からも考察すべきで、「人間中心の情報システム」こそ望ましい進化の方向性を示す最先端の姿であることを主張している。この「人間中心の情報システム」の概念を提案されたのが(故)浦 昭二名誉教授であり、これを軸に研究を展開している学会が情報システム学会である。本書の構成は、第1章~第2章で情報システムの進化の歴史を概観し、第3章では「人間中心の情報システム学」について考察されている。第5期科学技術基本計画で打ち出された「society5.0」は、「人間中心の社会」を志向するもので、「人間中心の情報システム」とまさに軌を一にしている。第4章では、著者の研究フィールドである北欧とエストニアのデジタル進化について紹介している。第5,6,7章は、著者のこれまでの研究成果、実践活動から生まれた社会や情報システムの見方であり、提案が盛り込まれている。
本書を読もうか、それとも読むのをやめようかと迷っていたら、とりあえずp230の「おわりに」を読んで頂きたい。この5ページに本書の勘所が要約されていると言っても過言ではなかろう。本書を徹底的に読もうという読者は、p236からはじまる「注」(参考文献)に目を通してほしい。この本がどういうバックグランドのもとで生まれたのか、先人たちの著作とのすり合わせ、格闘の中から生まれたことに少しでも思いを馳せることができたら、著者におおいに喜んで頂けるのではなかろうか。
経営情報学部共通科目(情報システム学科必修科目)である「情報システム」を担当する教員として、本書を推薦いたします。
著者は、情報システム学会の会長(本年6月から、名誉会長)をつとめられている。情報システム学会は、人間中心の情報システムを志向し、ビジネス・研究領域の融合や情報システム人材の育成を目的とした学会である。
新潟国際情報大学の初代の情報文化学部長である(故)浦 昭二名誉教授の提唱で生まれた学会であり、現在、8名の本学教員が加入している(略)。
本書では、情報システムが人間の情報行動を支援する仕組みであり、情報を収集・処理・分析・伝達・保存したりする社会的(組織的・個人的)なシステムととらえている。そしてその情報システムを個人やその集合体である組織・社会という「人間系」とアナログ技術、デジタル技術も含む「機械系」とで構成される仕組みとしてまずはとらえ、その情報システムの進化のプロセスをみていく。そして「進化の最先端に位置付けられる情報システム」にかんしては、進化を機械系からだけでなく人間系からも考察すべきで、「人間中心の情報システム」こそ望ましい進化の方向性を示す最先端の姿であることを主張している。この「人間中心の情報システム」の概念を提案されたのが(故)浦 昭二名誉教授であり、これを軸に研究を展開している学会が情報システム学会である。本書の構成は、第1章~第2章で情報システムの進化の歴史を概観し、第3章では「人間中心の情報システム学」について考察されている。第5期科学技術基本計画で打ち出された「society5.0」は、「人間中心の社会」を志向するもので、「人間中心の情報システム」とまさに軌を一にしている。第4章では、著者の研究フィールドである北欧とエストニアのデジタル進化について紹介している。第5,6,7章は、著者のこれまでの研究成果、実践活動から生まれた社会や情報システムの見方であり、提案が盛り込まれている。
本書を読もうか、それとも読むのをやめようかと迷っていたら、とりあえずp230の「おわりに」を読んで頂きたい。この5ページに本書の勘所が要約されていると言っても過言ではなかろう。本書を徹底的に読もうという読者は、p236からはじまる「注」(参考文献)に目を通してほしい。この本がどういうバックグランドのもとで生まれたのか、先人たちの著作とのすり合わせ、格闘の中から生まれたことに少しでも思いを馳せることができたら、著者におおいに喜んで頂けるのではなかろうか。
経営情報学部共通科目(情報システム学科必修科目)である「情報システム」を担当する教員として、本書を推薦いたします。
※2025年度の推薦本は図書館内のトピックコーナーに配架されています。(一部購入できないものを除く)
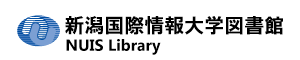


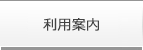
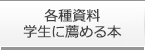
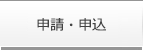
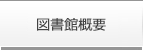

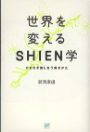

講演の内容は、通信、AI、エネルギー、宇宙とった技術の最新動向の紹介から始まり、今日の社会課題の解決に向けて新たな哲学とか日本ブランドの再構築等についての提案だった。その中で、とりわけ「IOWN(アイオン)」について熱く語られていた。IOWNという言葉は、技術雑誌等では何度も目にしていたが、きちんと理解したいと思い、早速本書を読んでみた次第である。学生の皆さんには、今後の情報通信ネットワーク等の核にあたる技術&サービスとなるであろうIOWNについて、積極的に関心を持って頂きたい。ちなみに本書の二人の著者は、NTT社長の島田明様とNTT副社長の川添雄彦様である。
「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)は、光ファイバーを使った大容量通信を実現するために、NTTが世界に先駆けて長年研究を続けてきた、「光」をベースとした技術基盤である。ネットワークからコンピュータ内部まで、従来は「電気」を用いていた信号のやり取りを「光に」置き換えることで、高速大容量かつ低遅延による安定したデータ伝送を実現しながら、電力消費も劇的に削減できるのです。」(本書p3-p4より)
本書の中で、「圧倒的な低消費電力でサステナブルな社会の実現に貢献」すると題して、この「光」の技術を基盤とした新しいネットワーク&コンピューティングの技術基盤を紹介している。データドリブン(データありき、データに基づいた)業務を推進するにあたり、生成AI・ビッグデータ等を積極的に使うことになるが、そうすると従来に比べて格段と大きな電力消費を伴うことになるので、IOWNの“圧倒的な低消費電力”はキー・テクノロジーとなると述べている。
IOWNは、将来はこのように展開していくといった“国際規格(デジュールスタンダート)”ようなものではない。現段階では“IOWN構想”であり、将来はこのように展開するだろうといった“展望”でもあり“願望”でもある。 IOWNが実現する未来については、本書第4章にそのイメージが掲載されてはいるが、本書をぜひ読みながら自分なりに考えてみる(将来の姿をイメージする)ことをおすすめしたい。
(以上)