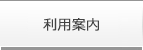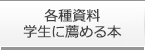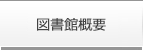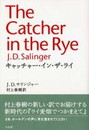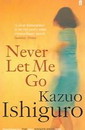図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2010年版
臼井 陽一郎
『カムイ伝』第一部・全15巻,第二部・全12巻,外伝・全11巻
- 白戸三平 小学館 2005.11-2007.4
どんな社会でも、聖なる書をもつものである。それはその社会の来し方行く末を叙事詩のように描き出すものであるとともに、その社会を越えていたるところで幾時代も貫いて普遍的に追求される、尊き価値ある人間の生き方を活写するものでもある。日本にとって、白戸三平のカムイ伝は、まさにそうした聖なる書として位置づけられるべき作品であるように思う。時は江戸、絶対的な身分制の圧倒的な暴力的抑圧に抗して生き抜こうとしていく若者たちの物語。ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟にも匹敵する広がりと深さをもって、人間存在の価値のすばらしさを読み手にうったえかけていく。第一部15巻、第二部12巻、そして外伝11巻を積み上げて、いまだ未刊の大著。生涯をかけて読み続けていくべき作品。
『百瀬、こっちを向いて。』
- 中田永一 祥伝社 2008.5
切なくも笑いのこぼれる純でポップなラブストーリー物。筆さばきが実にうまい。読後に振り返ってみれば、なるほど読ませる物語創作の術が思い浮かんでくるのだけれど、技巧に走ってる感は微塵も感じさせない。しかも、意外な展開に読者をどんどんと引き込んでいく。10代の時を愛おしく追憶する年齢になってから読むことで、感動も一塩となる良質の青春小説。
『船に乗れ』全三巻.(1)合奏と協奏
- 藤谷治 ジャイブ 2008.11-2009.11
『船に乗れ』全三巻.(2)独奏
- 藤谷治 ジャイブ 2008.11-2009.11
『船に乗れ』全三巻.(3)合奏協奏曲
- 藤谷治 ジャイブ 2008.11-2009.11
音楽高校を舞台にした青春物語。全三巻。三流音楽高校でクラシックに青春をかけるティーネイジャーたちのほろ苦く甘酸っぱい物語に、クラシック音楽の解説とニーチェなど哲学書の紹介が随所に織り込まれた知的エンターテイメントの書。友情と恋愛と裏切りと挫折と才能のきらめきと限界と崩壊する未来とその甘受があって、その中で音楽の絶対的な美しさが描かれていた。
『ヴァインランド』(池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 第2集(11))
- トマス・ピンチョン 河出書房新社 2009.12
かみさんに逃げられ、娘と二人暮らしのピッピー崩れのおやじが、合衆国政府の官憲に追われていく。逃げたかみさんには秘密の過去があった。ブロンズと青い目のくの一や死者の魂を商売のネタにするなぞの日本人、麻薬撲滅と左翼運動弾圧に権力を振るう男、闇の世界の大ボス、ベトナム帰りの死者の群れシンデルロたち、風采上がらない数学の教授であったのに気が付いたら自由を求め独立を目指すロックンロール共和国の党首に祭り上げられていた男などなど、実にいろいろなキャラが登場、カリフォルニアの雄大な自然と霊の満ちあふれる不可思議な山林や森を舞台に、雄大ではちゃめちゃでロマンチックなエンターテイメント粒子がリッチにちりばめられ、いくつもの物語が重々に交差しつつ展開していく。人間と社会と国家に対する深い洞察と重厚な抵抗の思想もまたしっかりと描き出されていて、まさにポストモダンなビート小説。時間も空間も本来はシンプルで直線的で平面的なはずであるが、本書では映写機のフィルムが同時に何本も投影されるようにめまぐるしく転回していく。現在から過去が回想され、その過去から現在への語りかけがあり、カリフォルニアの広大な土地からハワイへ行き、東京での謎の巨大生物によるものとみられる巨大な破壊があったかと思うと、場面はまたまたカリフォルニアに戻り、インディアン時代の悠久の過去にまでさかのぼり、この世とあの世とその境界にまで物語の場が拡張されていく。ピンチョン・ワールドはかくも豊かで刺激があり、怖さがありロマンスがあった。シンプルな救いや和解はどこにも見あたらない。ピンチョン・ワールドで迷子になってしまった読者は、決して少なくないと想う
『有頂天家族』
- 森見登美彦 幻冬舎 2007.9
良質な物語の好いところは、日常生活の一部になってくれるところ。本書は狸と天狗が京都を舞台に縦横無尽に走り回る物語。読後、その物語は日常生活にまさにじーんと染み渡ってきた。日々の人付き合いやらナリワイやらの荒れ地のような場をわたりあるいていくにあたって、何かコトあるごとに、人間社会の見えないところで暗躍している天狗や狸の行いを想像するようになってしまった。赤玉ポートワインを燃料に空翔る納涼船万福丸、気まぐれでこの世に荒波を引き起こす風神雷神の扇、きっと美味に違いない狸の好物・偽電気ブランの味などなど、本書を読んでアタマとココロの双方から離れなくなってしまったこと多数あり。本書は毎日の生活を狸と天狗の世界に交差させ、とても豊かなものにしてくれる。阿呆の血のしからしむるところにしたがって、面白きことこそ良きことなりとする狸哲学、これに加えて弁天様の悪魔的魅力もこころを覆ったまま。忘れがたい読書経験になるとおもう
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
- J.D.サリンジャー(村上春樹訳) 白水社 2003.4
村上訳のライ麦畑。16歳の少年のほんの2、3日の間の出来事なのだけれども、人のこころが人どうしの交錯により生み出される汚悪的なものとどういった関係を結ぶことができるのかできないのか、そんなかなり本質的なことがらについて考えさせられるストーリー展開だった。村上訳がまた好い感じを醸し出していて、主人公ホールデン・コールフィールドのキャラが日本語の世界の中で具体的に浮かび上がってくる。本書はホールデン少年を描いているようで、実は彼を鏡として映し出される世の中の有り様をつかみだそうとしたものなのかもしれない。彼の妹のフィービィに温かい気持ちにさせられた読者は、ホールデンの口癖じゃないけれど、きっと世界中に100億人くらいはいるかもしれない。
『グレート・ギャツビー』
- スコット・フィッツジェラルド(村上春樹訳) 中央公論新社 2006.11
退廃の比類なき美しき描写に、思わず息を飲んだ。登場人物たちの絡み合いは、ガラス糸細工の繊細さで、スタイリッシュにカッコよく描かれる。ため息の連続だった。ギャツビーのディジーに対する狂気の想いの切なさ、これがピンクのスーツとイエローのアメ車とニューヨークと岬のきらめきと貴族風の豪邸と豪勢なパーティそして闇のビジネスと合わさって、コントロール不能な情動が胸にこみ上げてくる。忘れられない読書経験となった。村上訳がまたすばらしく、彼の日本語の小説のようでさえあった。何度も手にとり読み返したい作品である。
『ゴールデンスランバー』
- 伊坂幸太郎 新潮社 2007.11
スリリングなエンターテイメント小説。幹となるストーリー・ラインに引き込まれていくのはもちろん、枝葉となる情景描写や脇役キャラ設定が好い感じ。暴力シーンはそれほどえぐい感覚はなかったし、無駄なセックス・シーンもない。花火や下水道や宅配といった部分の描写に惹かれる。空と地下と地上が描かれてるわけで、これに登場人物たちの大学生時代のセイシュン的場面がちりばめられる。そうした個々の場面の筆の力は、著者のエンターテイメント小説以外の分野での活躍を期待させる。学生時代の花火シーンなど、こころに焼き付くものがあった。主人公を助けていくロックンローラーの宅配人や裏家業のあやしい入院患者、そしてハードボイルドな連続刺殺事件の犯人たちが、国家の巨大で圧倒的でしかし抽象的で顔の見えない権力に反抗していく姿、これが実にワクワクものだった。
『ヘヴン』
- 川上未映子 講談社 2009.9
書き手のたましいのことばが聞こえてくる作品であった。一般にいじめと呼ばれる壮絶な暴力にたたきつけられながら、生きることの意味を求めて戦い続ける中学生男女二人のラブストーリー。暴力をふるう側である二ノ宮と百瀬の二人は、一方が主犯格、他方が暴力を正当化するスポークスマンといった役柄。ただこの二人は記号化されていて、その日常の生の具体的な状況は舞台に登場しない。主人公の僕は同じく暴力にさらされている女の子コジマとレターの交換で交信しながら、たまに逢って、やがて僕はコジマの強さ・深さ・優しさのすべてに惹かれていく。僕は斜視、コジマは汚さが、ある何ものかの徴(しるし)であると、コジマ自身が僕に語って聞かせる。くじら公園でのラスト・シーンのコジマのふるまいは、すべてを脱ぎ去った美しき天使のラスト・ダンスのように想えてならなかった。カミュが『ペスト』で主人公にこう語らせているのを想い出した。「人は神によらずして聖者になりうるか――これが、こんにち僕の知っている唯一の具体的 な問題だ」 著者・川上の描くコジマは、カミュのこの難問に対するひとつの見事な解答になっているように想えてならない。
『吉祥寺の朝日奈くん』
- 中田永一 祥伝社 2009.12
石清水のように癖のない純な文章が綴る恋物語短編集。物語の展開の意外性も読者をばっちり引き込んでいく。良質のドラマ・シナリオにもなりそう。無駄な情景描写もなく、テンポも良い。読者を飽きさせない。それどころか、必ずほろっとさせる場面が用意されている。劇場で言えば一番値段の高いS席、舞台の役者の息吹をダイレクトに感じられる。
『神様のカルテ』
- 夏川草介 小学館 2009.9
日本の医療についての地方目線の実情と終末期医療の実際が、笑いと涙のほのぼの感動ストーリーを通じてしっかりと語られていく。夏目漱石の草枕を座右の書とするためやたらとカタイ話言葉になってしまう内科医が、医局に入らず大学を離れ、地域医療の現場に飛び込み、救急医療と終末期医療の先の見えない戦いに奮闘していく物語。個性豊かな忘れがたい脇役キャラたちがまた好い味を出している。売れない貧乏画家の男爵、ニーチェ研究にいそしむ博学の学士殿、巨大な怪物外科医の友とその恋の相手のちっちゃな新人看護婦、そして主人公の細君ハルさんなどなど。200頁ほどの中編小説にして、物語はうすっぺらにならずでも密度は濃すぎず、文体は初夏の涼としたそよかぜのごとくさわやか。今年上半期のベスト本になりそうな一冊だった。
『意味がなければスイングはない』
- 村上春樹 文藝春秋 2005.11
音楽とともに音楽の中で音楽を生きる作家の珠玉の一冊。音楽家たちの生き様を描く物語でもあり、その音楽家たちの作品に入り込んでいく作家自身も一人の登場人物となって、彼自身の物語が展開される自伝的エッセイでもあった。音楽と人生をともにしていくことのすばらしさを身体全体で実感させてくれる書物。村上春樹の魅力あふれるエッセイ集であるとともに、彼の世界観がとても分かりやすく、両手にあふれんばかりの砂金のようにきらきらと重量感をもって伝わってくる作品であった。何度も読み返したい一冊になった。
『マイルスに訊け』
- 中山康樹 イースト・プレス 2007.6
マイルス・デイビスの作品に身を浸した者もそうでない者も、若者だけでなく中年のおっさんも、癒しのことば集になるし、あるいはバイブルにだってなってしまうかも。胸にグッと来ることばの集積。激しい人種差別の中で半世紀近くにわたってトップを走り続け、人類の宝物・ジャズを紡ぎ出してきた男のライブなことばの数々。多くの人に薦めたい。
『グランドマザーズ』
- ドリス・レッシング 集英社 2009.6
短編映画のような作品が4本おさめられた短編集。一つひとつの作品に登場する風景がとにかく美しい。銀幕に映し出された絵画の美しさを背景に、人間の苦しみと社会のゆがみが見事に一体化され描かれている。短編ゆえの強引な早送りは一見本書が長編作品用ノートであるかのような印象をあたえてしまいかねないが、それはまた数奇な運命の映画的な場面チェンジのようでもあって、場面によっては幻想性さえ醸し出されてくる。表題作の「グランド・マザーズ」と「愛の結晶」はいずれも年上のオンナが年下の少年のようなオトコと特別な関係に入ってしまう話。オトコとオンナの関係の偶然と必然が、一方はアメリカの、もう一方は南アフリカの、それぞれの美しい海の町を舞台に狂おしく描かれる。SF的な「最後の賢者」では、詩や歌が共同体作りの中核にあった美しき時が、やがて愚鈍と無知により暴力に覆われていく抗しがたい運命が語られる。「ヴィクトリアの運命」はイギリス社会の正確な再現ビデオであるかのように、階級格差社会の現実を映し出す。以上の4作品いずれにおいても、社会の堅く冷たい構造と暴力が実にリアルに描写され、その内部で生き抜こうとするオンナとオトコの、火災で手のつけられなくなった炎のように激しい生が描出されている。
『日記をつける』
- 荒川洋治 岩波書店 2002.2
日記の付け方でもあり、いろんな日記の紹介でもあり、日記のポテンシャルを論じる解説書でもあり、そんなこんなの日記トークがそれ自体、まるで詩であるかのように展開されていく。読んでいて楽しい。紹介される日記の解説に、目を見開かされる。日記は自分自身を語るのみならず、フツウじゃあ見えない世界を開示する試みなのかもしれない。本書を読み終えてすぐ、日記が詩や小説といった文芸作品の土台になるんだってことがすーっストンと、身体の奥底へ落ちていった。
『迷宮の将軍』
- ガルシア・マルケス 新潮社 1991.8
ラテン・アメリカをスペインの支配から解放した英雄、シモン・ボリーバルの最晩年を描いた作品。最後の旅路が、淡々と語られていく。波瀾万丈の動きは存在しない。ハンモックと船とトランプと、笑いと激高と嘆きと、それからラテン・アメリカの風景が、まるで美しいひとつの絵の中に収まったかのような作品だった。相次ぐ戦争で、体中傷だらけの将校とボリーバルが二人、船の甲板に仰向けになり、無数にきらめく星々を眺めながら、語り合うひととき。またかつての愛人が訪れ、両手を使って胸に抱えても零れるほどの想いをじっと身体の奥底にしまい込みながら、見つめ合うひととき。将校やお付きの者たちとトランプに興じ唄をうたうひととき。そしてハンモックで身体の痛みと吐き気にうめきながら悔しさと後悔と意地と未来を中空の一点に見つめるひととき。ボリーバルには生涯にわたって付き添った世話係がいて、彼の献身ぶりがページのいたるところに出てくるものの、その役柄通り、決して目立つことがない。彼の出自について、最後の最後に紹介される。本書はたくさんのドラマがボリーバルを中心に織り込まれたものでで、何人かの重要人物たちの、ボリーバル死後の行く末が、同じく最後の最後に描き出される。一つひとつが小説の作品になりそうなエピソードだった。捕鯨船に乗り込んで世界中を回り旅するオンナもいれば、とある田舎町の教会でボリーバルの弔いをつづけたオンナもいた。とにかく淡々と進む書物なので、結局、読み終えるのに2年もかかってしまった。1頁読んでから次の頁に進むのに、強靱な集中力が必要になる。でも、読み終えてしばらくして、なお、本書の雰囲気が身体を包んだままだ。雰囲気が身体に染みこむ作品。忘れられない1冊になった。
『居酒屋』
- ゾラ 新潮社 2006.1
良質の物語は、ある具体的な世界の内の身体的な経験になる。本書『居酒屋』体感の衝撃は、頭ではなく、身体で記憶していくことになるのかもしれない。貧困の底辺に張り付く労働者の街、グート・ドル街。近代都市パリのこの一角で、ヒトが人であることを自ら否定していく惨状が繰り返される。人間存在の醜さを、一切の救済の可能性を否定しつつ、克明に読み手のこころに文字通り焼き付けていく、そんな作品であった。ただ、登場人物のこころの襞の精密で刻々と変わりゆくはずの部分は、これがまったくもって単純化されていて、まるで戯画的世界のキャラ群像といった感じであった。でも、まるでロートレックの絵のような、生命の躍動が波打つシーンがちりばめられていた。洗濯場や鍜治加工場や鉄道の駅やキャバレーや貧民靴のアパルトマン、そして居酒屋、さまざまな街の空間がそれ自体生命と意志をもつ場であるかのように、描き出されていた。この街の描写も本書の魅了のひとつ。その街のどの場のどのシーンでも、奇跡は決して起きない。一切の救いの道が閉ざされる。閉鎖された死の空間、それがグート・ドル街という場であった。酒浸りになった男が精神病院でまる3日以上無様な狂気の舞踏をつづけ倒れ死したのちもやせ細った皮の中の骨の中の痙攣が終わらないというシーンがあった。この男、人の尊厳を奪う滑稽な死への舞踏のあいだ中ずっと憎しみをほとばしらせながら誰かを殴りつけようとしていた。また酔って暴力をふるう父に母を殴り蹴り殺された8歳の幼女が今度は自分が母の身代わりに暴力のはけ口を引き受けやがて打撲と飢餓で死にいたる寸前にその父にこれからの生活の細々とした注意を与え、それを終えてから安らかな笑顔で死にゆくというシーンもあった。訳がとても優しい感じの日本語で、とにかく読みやすい。世界文学モノ特有の、解読が必要な日本語訳ではなかった。でも、だからこそ、本書『居酒屋』の読書経験による衝撃の体感は、かなり和らげられることになったのだとおもう。一切の救いもファンタジーも封じ込められた物語世界。ルーゴン・マッカール叢書の他の作品もあわせて読んでみたら、もしかしたら本書『居酒屋』は何かほかのものを描き出していくための、準備的な作品になっていることがわかるかもしれない。本書に登場するナナとエチエンヌを描いた他の作品は、どうなるのだろう。ゾラの物語世界は、ドラッグのようにヒトを引きずり込んでいく。
『みどり、その日々を過ぎて』
- 岩成達也 書肆山田 2009.8
初老の男が妻へ宛てたラブレター。そんな雰囲気の感じられる詩であった。妻は向こうの世界へ旅立ったばかり。最後の日々の追憶が綴られる。光の飛沫、森の闇の奥に予感されるその光源、突然の<広がり>の現れ、二人一緒に<在るもの(あるいは遠さを克服された存在者)>を見ていることの実感。そうしたファンタジーの世界が美しく描かれていく。このファンタジーの世界を舞台に、二人の共通の経験を担ったモノや空間が在るということの意味や、最後の最後に二人で受けた洗礼の意義について、問われていく。ファンタジーの美しさを描きながら、此岸に残されたことのつらさの煩悶を存在論と神義論の問いかけに昇華していく。こうした詩作のあり方には、憧れさえ感じてしまう。
『事件』
- 大岡昇平 新潮社 2003.5
刑事裁判の現実を描き出した作品。小説が社会的現実のまさにリアルな構成にとって重要な媒体であることを、あらためて納得させてくれる。事件は裁判によってはじめて事件として成立する。そこでは三つの物語が展開される。検察による論告が構成する現実。弁護人による弁論が構成する現実。そして裁判官による判決文が構成する現実。このうち、最後の裁判的現実が真にリアルであるものとして刑罰という国家的行為が敢行される、それが文明国家である。いうまでもなく、絶対の現実ではなく、よりたしからしい現実を選び取る仕組みが、社会進化の中で模索され続けているのであり、刑事裁判という制度の今後の進化方向について(退化方向についても)、いろいろと考えてみたいと実感させられる作品であった。そしてまた、社会的現実の物語分析という視角の重要性についても、あらめて気づかされた作品になった。ちなみに昨今の裁判官制度をおもうに、いまもなお旬な作品でありそうだ。
『治療塔』
- 大江健三郎 岩波書店 1990.5
『治療塔惑星』
- 大江健三郎 講談社 2008.8
選ばれたものたち100万人が、地球文明を継承するため、新しい地球を求めて宇宙へ旅立つ。残された古い地球には、選ばれなかった落ちこぼれ人類と局地核戦争で汚染された大地が存在するのみ。しかし、その残された古い地球では、生き残りをかけて、とある社会運動が展開する。複雑なものは単純なものへ、これが合い言葉となって、効率性・生産性よりもゆっくりとした確実な、はんだごて的手仕事を優先する産業体制へと、そしてそれを中心とした社会体制へと、退化的変化が試みられる。他方、選ばれたものたちは新しい地球に到達、そこに治療塔と呼ばれるようになった人間再生装置を発見する。人類の英知の及ばない未知の知性体が人類に与えたものと推測される。選ばれたものたちは、その治療塔で身体を強化して、汚染された地球に戻り、古い地球を新たに再生させようと、方針を転換する。地球に帰還したエリートは残されていた落ちこぼれとの婚姻を禁止される。しかし、選ばれ新しい地球に赴き治療塔で身体を強化した男と、十代の前半に残された地球でギャングたちに性奴隷的に虐待を受けた女が、結ばれることに。二人の静かなでもしっかりとした絆が、イェーツの詩を通じて、とてもきれいに描き出されていく。続編の治療塔惑星とあわせて単行本600頁を越える長編。本当の治療塔は、しかしじつはすでに、古い地球に存在していた。それは、前世紀の破壊された大きなドームであって、その中に入り黙祷することで、人間の再生が可能になるような、たしかな治療塔であった。そんなメッセージが、途中ほのめかされ、最後の最後に明確に提示される。広島にある、あのドームである。
『個人的な体験』
- 大江健三郎 新潮社 1964.8
とある男の再生の物語。かつてあった自分を取り戻すの意味ではなく、つまりリセットではなく、新しき人となって再び人間の生を生き抜こうと決心する、そういう意味での再生。頭蓋に奇形のある赤子を巧妙に死へと捨て去り、その赤子の母とは異なる女性とアフリカへ旅立とうとする男の、数日間の物語。その女性、夫に先立たれている。自殺だった。男の再生の時にいたるまでのわずかな日々の描写に、文学の尊さと限りない可能性を実感させてくれる作品
『宴のあと』
- 三島由紀夫 新潮社 1989.12
高級料亭の女主人、齢50を超えながらも、そのうつくしさに衰えはない。極貧の生活から現在の地位をつかみとった情念情愛迸る無限の生命の力を内に湛える。やがて元大臣の初老の男を愛するようになり、東京都知事選に立候補した彼のために戦うことに。保守を相手に革新側に立って選挙戦を戦う彼女の、天性の才能の開花は、体制側の巨大な勢力をどんどん追いつめていく。この選挙戦、本書の醍醐味である。政治のなんたるかをきわめてリアルに描き出しながら、政治の本質もかいま見せてくれる。著者三島の筆の力は、あらためていうまでもない。しかし本書のすばらしさは、その彼女の人間像の彫拓にもある。料亭を舞台とした虚栄・虚飾溢れんばかりの人間たちの闘いの場の活力を糧に、静を恐怖する彼女の動へ向けた生命の力は、読み手のこころにも激しく揺さぶりをかけてくる。宴のあと、絶えず休むことなく次の宴を企図していくその生き方には、生ということばの本来意味するところが体現されているようでもあった。
『半島』
- 松浦寿輝 文藝春秋 2004.7
40を過ぎた男が、自らの来し方行く末に戸惑い佇み、懊悩にも苦しむ様子を、神秘的で幻想的で暴力的で官能的で、それゆえに魅惑的な世界に投影して描き出した作品。色使いも鮮やかで、半島という空間の、彼岸と此岸のあいまいな地帯に存在しているかのような雰囲気が、闇夜に漂う月光や鉱山の地下坑道で揺れる灯の波紋に表現されていて、それがまた40を過ぎた男の酔いにまかせた時間意識の攪拌とピッタリ合ってきて、読み手は物語の世界に引きずり込まれていく。遠近感を物理的にも意識的にも幻惑させるだまし絵のような空間配置は、謎の老人や美しい女性たちの謎めいた動きと相まって、読者を主人公と一体化するよう誘惑する。闇の向こうの暴力と官能の二つの雰囲気に引き込まれ、良心の呵責を起こしつつも、その部分に惹かれ楽しんでしまうという、不可思議な読書体験だった。
『1Q84』
- 村上春樹 新潮社 2009.5-2010.4
良質の物語に出会うと、読んでいる間も読み終えた後も、意識はその物語の中に入り込み、まるでその物語とともに生活しているような感覚を覚えるようになる。本書もそんな物語だった。エンターテイメントな小説であるのに、一つひとつのメタファーと物語の重層性はとても精緻に複雑に組み立てられている。そんな印象をもった。続編が出てもおかしくはないエンディングだった。100万部を超えているという。いったい、どれくらいたくさんの読者が、夜空を見上げて月が二つ浮かんでいないか、確かめたことだろう。深夜、暗闇の中、天井をボンヤリ見つめながら、思わず両手を中空のどこかに伸ばして、空気さなぎを紡いでいるような錯覚にハマってしまった読者も、たくさんいるにちがいない。ある物語を生きる。人間の人生のあり方だと想う。問題は、ある物語から他の物語に移動してしまって、もとの物語の世界に戻れなくなってしまうこと。ただ、いまいる物語の世界が大切な人によって創り上げられた物語であるのなら、その物語の中で与えられた運命を生き抜こうとすることは、とてもうつくしいことであるように想えてくる。ふかえりが提供して天吾が紡いだ物語の世界を退路断って生き抜こうとする青豆のハードボイルドな生き方は、自由なる生の絶対的な確保であったのかもしれない。それから、リトル・ピープルの存在。ひたひたと暗闇の中をどこからかやってくる怖さがあった。この作品のすぐれた部分のひとつだと想う。リトル・ピープルはどの物語にも共通に現れる暗黒の暴力。自由を求める生と必然の到来たる死。両者のせめぎ合いが、娯楽性豊かなメタファーによって描き出されていた。この筆の力量は、今回もまた凄いものがあった。
『トロムソ・コラージュ』
- 谷川俊太郎 新潮社 2009.5
いまや国民的売れっ子詩人の最新の詩集。秀逸なのは、臨死船と詩人の墓。いつまでもこころに存在していてくれるような作品になった。詩の物語性と劇場性そして思想性のすべてが、シンプルにうつくしく配合されている。
『Norwegian Wood』
- Haruki Murakami Vintage 2003,c2000
20年以上前、2度ほど読んだ本を、20年後、英語で読み返してみた。あらたな発見があった。この物語は、40を目前にした女性の、再生の物語でもあった。生と死の境界で自分という存在の存在すべき場を探し求めている若者のかたわらでやさしく強く見守りながら、その女性はようやく、生と死の境界での長い長い滞在からはなれ、生の世界に立ち戻っていくことを決心する。この物語にはところどころメタファーがあって、たとえばセックス。これはまるで、死の世界から生の世界に通じるトンネルを歩いていくような(たまにスキップしながら)、そんな行為だった。この行為によって、死の世界に行こうとする者が生の世界に少しだけやってくるときもあれば、生の世界に生きる者が死の世界に行こうとしてしまう者を生の世界に連れてこようとすることもあった。草原の井戸、夜は下ろされる日の丸国旗、ジョン・コルトレーンの死、商店街の小さな本屋のシャッター、完璧に優秀なエリートが飲み込むなめくじ、大量の使用済み生理用品を燃やす焼却炉から立ち上る煙、などなど。村上のフツウの作品とはひと味違う実話型のように見えて、実はそうではなく、彼のいつも通りの、生と死の二つの世界を行ったり来たりするための、たくさんのメタファーがちりばめられていた。それでいて、過剰な印象はもたせない。ところで、20年後の英語による再読で気がついた、この物語のもう一つの特徴。40代以上の人間が、若者に影響を与えられるほどの存在感をもって、登場してこない。小さな本屋を立ち上げた緑の父の死ぬ間際のシーンだけが例外。これもメタファーだろうか。おっさん・おばはんは、消されている小説。。。それからあとひとつ、手紙。主人公の彼は、たくさんの手紙を書いていた。手紙のことばは、とても素直でしかもうつくしいものだった。
『Never Let Me Go』
- Kazuo Ishiguro Faber and Faber 2006.3
現代文学の最高峰にランクされるべき作品。もしかしたら、21世紀の古典として、その地位を確立していくかもしれない。遺伝子技術を題材としたSFで、クローン人間を使った移植技術が、舞台設定に使用されている。ドリス・レッシングが、SFこそ文学の可能性を極限に高めるすばらしい分野だと書いていたのを読んだことがあったが、まさにそれを実証するような作品であった。
限界づけられた世界、すでに完全に決定されている将来。それを静かに受け入れながらも、しかし、他の何ものにも奪われまいと決意した追憶の世界を、大切に維持していく静かな生き方。普通の人間達の、普通の英雄的な生き方だと想う。読後、静謐の潮が心の奥底からゆっくりと押し寄せてくる作品だった。
雑誌『文学界』に掲載されていたインタビューでは、一切触れられていなかったけれども、たとえばポスト・コロニアリズムの系にある作品にもなりうると、理解できないだろうか。人間性を否定する社会構造に闘いを挑む人道主義が、中途半端なまま、圧倒的な力を持つ構造側に押しつぶされ、当初の人道主義的闘いを貫徹させるという責任は、宙に浮いたままになる。主人公達の、他の何ものにも奪われまいと決意する大切な追憶の子供時代・思春期時代の世界は、じつはそうした中途半端な人道主義と圧倒的な構造の、最初から勝敗の決まった闘いの中で、奇跡的に可能となっていた暫定的な世界に過ぎないのであり、やがては物理的に消滅してしまうよう運命づけられている世界だった。主人公達の追憶の世界は、圧倒的な中心周辺構造の中で、中途半端な人道主義により、特権的に作られた、特別な世界である。前作のWhen We were Orphanと、まさに類似の構図が描かれていた。
自らの来し方の社会的土台の、醜く歪んだ姿が徐々に明らかにされていく物語の展開の中で、主人公たちを解放するファンタジーは、しかしいっさい用意されていない。にもかかわらず、そのこころをゆったりと癒していく追憶のうつくしさが、随所にちりばめられている。人間をこの世界の抑圧から解放するものが何であるのかを考えることは、人間は何を生きるために生まれてきたのかを考えることに帰結する、そんなメッセージを本書から受け取ったような気がする。
限界づけられた世界、すでに完全に決定されている将来。それを静かに受け入れながらも、しかし、他の何ものにも奪われまいと決意した追憶の世界を、大切に維持していく静かな生き方。普通の人間達の、普通の英雄的な生き方だと想う。読後、静謐の潮が心の奥底からゆっくりと押し寄せてくる作品だった。
雑誌『文学界』に掲載されていたインタビューでは、一切触れられていなかったけれども、たとえばポスト・コロニアリズムの系にある作品にもなりうると、理解できないだろうか。人間性を否定する社会構造に闘いを挑む人道主義が、中途半端なまま、圧倒的な力を持つ構造側に押しつぶされ、当初の人道主義的闘いを貫徹させるという責任は、宙に浮いたままになる。主人公達の、他の何ものにも奪われまいと決意する大切な追憶の子供時代・思春期時代の世界は、じつはそうした中途半端な人道主義と圧倒的な構造の、最初から勝敗の決まった闘いの中で、奇跡的に可能となっていた暫定的な世界に過ぎないのであり、やがては物理的に消滅してしまうよう運命づけられている世界だった。主人公達の追憶の世界は、圧倒的な中心周辺構造の中で、中途半端な人道主義により、特権的に作られた、特別な世界である。前作のWhen We were Orphanと、まさに類似の構図が描かれていた。
自らの来し方の社会的土台の、醜く歪んだ姿が徐々に明らかにされていく物語の展開の中で、主人公たちを解放するファンタジーは、しかしいっさい用意されていない。にもかかわらず、そのこころをゆったりと癒していく追憶のうつくしさが、随所にちりばめられている。人間をこの世界の抑圧から解放するものが何であるのかを考えることは、人間は何を生きるために生まれてきたのかを考えることに帰結する、そんなメッセージを本書から受け取ったような気がする。