図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2009年版
臼井 陽一郎
- <走る人生について考えるための本>
『長距離走者の孤独』
- アラン・シリトー 新潮社 1973.8
『ラン』
- 森絵都 理論社 2008.6
『ランナー』
- あさのあつこ 幻冬舎 2007.6
『走ることについて語るときに僕の語ること』
- 村上春樹 文藝春秋 2007.10
- <ニホンの来し方のリアルな姿について考えてみるための本>
『邪宗門』
- 高橋和己 河出書房新社 1970.1
<ニホンの来し方のリアルな姿について考えてみるための本>
世の中にはビジネスや政治の世界のコンサバおやじたちに買わせるための、"現在はちょっと下り気味だけど本来はすばらしい日本人"といった論旨の本がとてもよく出回っている(ような気がする)。今年の秋には、司馬遼太郎の坂の上の雲がいよいよドラマ化される。ビジネスや政治の世界のコンサバおやじたちの日本人観・日本社会観の多くが、司馬の明治史観に影響されている(ような気もする)。実は、中学生の時にこれを読んだ。二回目は高校生の時。そして三回目が大学生の時。どうやら、コンサバおやじたちの仲間入りをしてもおかしくない読書経験をしていたらしい。ニホンはかつてすごかった。明治の男たちはすごかった。でも、やがて坂を登り切ってしまって、その後、昭和という下り坂を転げ落ちてしまった。こんなストーリー・ラインだ。周辺に向けられた日本的協働性の本来的全面的破壊性など、まったくもって見向きもされない。ここに真剣に意識を集中させないかぎり、たとえば少子化を女のわがままのせいにして自ら責を負うべき社会の抑圧性閉塞感を省みようとしないコンサバおやじたちの天下が続きそうだ。というわけで、その天下を覆す準備としてとりあえず椅子に座って机の上で平和に内省してみるための本を選んでみた。ニホンの来し方のリアルな姿について考えるための二冊を推薦したい。
※ コンサバおやじ: 世の中を見つめながらぼくが決してそうなりたくはないとこころに固く誓うにいたった人物像。自己賞賛ばかりして、これまで何の問題もなかったのだから何かを変える必要など何にもなく、お上のいうことにはとっても弱い、そんな人物像である。ただし特定の人物を指しているわけではない。あくまで想像上の人物像である。
全宗徒100万を超える巨大な教団に発展したひのもと救霊会なる架空の宗教団体を創作、その来し方行く末を通じて、戦前ファシズム期と戦後占領下の日本社会の、叫喚・嗚咽絶えることなき蠢きを描き出そうとした作品。宗教団体がその規模を巨大化してその活動を全面化するとき、社会のすべての場を、また人々のすべての層を、その活動のうちに包摂することができる。宗教団体の神の国実現へ向けた世直しの活動は、したがってそれが真摯かつ純粋なものであればあるほど、時の国家権力との衝突の避けられなくなる場合がある。理想の社会づくりを、神の使徒ではなくどこまでも生身の人間が作り上げた宗教団体によって進めようとした場合の悲劇、これが本書によって見事に描き出されていた。著者の文学の書き手としての人生のランドマークとなる作品であろうし、日本の文学史にとっても、なくてはならないかけがえのない作品である。日本語文学作品の伝統の、その質の分厚さに大きく貢献しているといえるように思う。
ひのもと救霊会の信者たちが闘ったそれぞれの場面での一切の救いなき悲劇、そこに著者の卓抜した筆の力によってリアリティが注入されている。満州開拓団の物語があり、瀬戸内の癩病患者の収容所の物語があり、九州の炭坑に徴用された朝鮮人たちの物語があり、人里離れた被差別部落の物語があり、工場労働者の物語があり、地主の奴隷たる小作人たちの物語があり、製紙工場の若き女性たちの物語があり、都市の貧民街の娼婦の物語があり、農村の男の奴隷たる農婦たちの物語があった。高橋和己の描き出す、一切の甘い夢への陶酔を微塵も許さない暗黒の世界、そこから見えてくるさまざまな日本の姿、そこでこそいまもさまざまに形を変え各所に潜んでいるあるきわめて日本的なるものの実体を探ることが出来る。そこに迫っていく認識の営みは、歴史のいつの段階でも必ずや必要な知的営為になってくるのではないだろうか。そんな思いに駆られる素晴らしい作品であった。
世の中にはビジネスや政治の世界のコンサバおやじたちに買わせるための、"現在はちょっと下り気味だけど本来はすばらしい日本人"といった論旨の本がとてもよく出回っている(ような気がする)。今年の秋には、司馬遼太郎の坂の上の雲がいよいよドラマ化される。ビジネスや政治の世界のコンサバおやじたちの日本人観・日本社会観の多くが、司馬の明治史観に影響されている(ような気もする)。実は、中学生の時にこれを読んだ。二回目は高校生の時。そして三回目が大学生の時。どうやら、コンサバおやじたちの仲間入りをしてもおかしくない読書経験をしていたらしい。ニホンはかつてすごかった。明治の男たちはすごかった。でも、やがて坂を登り切ってしまって、その後、昭和という下り坂を転げ落ちてしまった。こんなストーリー・ラインだ。周辺に向けられた日本的協働性の本来的全面的破壊性など、まったくもって見向きもされない。ここに真剣に意識を集中させないかぎり、たとえば少子化を女のわがままのせいにして自ら責を負うべき社会の抑圧性閉塞感を省みようとしないコンサバおやじたちの天下が続きそうだ。というわけで、その天下を覆す準備としてとりあえず椅子に座って机の上で平和に内省してみるための本を選んでみた。ニホンの来し方のリアルな姿について考えるための二冊を推薦したい。
※ コンサバおやじ: 世の中を見つめながらぼくが決してそうなりたくはないとこころに固く誓うにいたった人物像。自己賞賛ばかりして、これまで何の問題もなかったのだから何かを変える必要など何にもなく、お上のいうことにはとっても弱い、そんな人物像である。ただし特定の人物を指しているわけではない。あくまで想像上の人物像である。
全宗徒100万を超える巨大な教団に発展したひのもと救霊会なる架空の宗教団体を創作、その来し方行く末を通じて、戦前ファシズム期と戦後占領下の日本社会の、叫喚・嗚咽絶えることなき蠢きを描き出そうとした作品。宗教団体がその規模を巨大化してその活動を全面化するとき、社会のすべての場を、また人々のすべての層を、その活動のうちに包摂することができる。宗教団体の神の国実現へ向けた世直しの活動は、したがってそれが真摯かつ純粋なものであればあるほど、時の国家権力との衝突の避けられなくなる場合がある。理想の社会づくりを、神の使徒ではなくどこまでも生身の人間が作り上げた宗教団体によって進めようとした場合の悲劇、これが本書によって見事に描き出されていた。著者の文学の書き手としての人生のランドマークとなる作品であろうし、日本の文学史にとっても、なくてはならないかけがえのない作品である。日本語文学作品の伝統の、その質の分厚さに大きく貢献しているといえるように思う。
ひのもと救霊会の信者たちが闘ったそれぞれの場面での一切の救いなき悲劇、そこに著者の卓抜した筆の力によってリアリティが注入されている。満州開拓団の物語があり、瀬戸内の癩病患者の収容所の物語があり、九州の炭坑に徴用された朝鮮人たちの物語があり、人里離れた被差別部落の物語があり、工場労働者の物語があり、地主の奴隷たる小作人たちの物語があり、製紙工場の若き女性たちの物語があり、都市の貧民街の娼婦の物語があり、農村の男の奴隷たる農婦たちの物語があった。高橋和己の描き出す、一切の甘い夢への陶酔を微塵も許さない暗黒の世界、そこから見えてくるさまざまな日本の姿、そこでこそいまもさまざまに形を変え各所に潜んでいるあるきわめて日本的なるものの実体を探ることが出来る。そこに迫っていく認識の営みは、歴史のいつの段階でも必ずや必要な知的営為になってくるのではないだろうか。そんな思いに駆られる素晴らしい作品であった。
- <ニホンの来し方のリアルな姿について考えてみるための本>
『異族』中上健次選集
- 中上健次 小学館 1998.11
未刊の書だが、巨大なポテンシャルをもつ作品。被差別部落出身の若者、二世の在日韓国人、アイヌ民族の若者、人買いに買われていった沖縄の若者、部落出身者と黒人との混血児、日本に帰化した台湾の高砂族、右翼にあこがれる暴走族の若者、際限なく性交渉を続ける知恵遅れの女の子、政財界・やくざ社会の黒幕で右翼の大物、そしてフィリピンの日系二世の人々。こうした"異族"たちの生身の暴力の連鎖によって紡がれる日本の姿。本書の存在によって見えてくるそうした日本の姿の異様さは、しかし日本に閉じた固有の現象でなく、文明社会のどこにおいても現れる徹底的な疎外の構造であろうか。本書は特殊日本的な小説ではなく、待望久しい東アジア小説ですらない。まさに普遍的なる射程をもった作品だと思う。あらゆる価値理念を取り去ったナマの人間の姿が、たんたんと描写される。理知的で社会改革への情熱をたぎらせる人間は、一人も登場しない。人間の生の現場が活写される。本書の描き出す人間と社会をどう読み解くか。長く時間のかかる課題を突きつけて、本書未完のまま、中上はこの世を去ってしまった。彼の活写する人間の生の現場を起点に、いろいろなことを考え直さなければいけないのだと思う。
『Briefing for a Descent into Hell』
- Doris Lessing.
<人間の根源について集中して意識してみるための本>
文学とは、人間の根源について集中して意識してみるための読み物である。
小学校の低学年のとき、逆上がりができない子は存在そのものを否定されるような軽蔑の眼を注がれた。そのクラス中から受ける軽蔑のまなざしのつらさは、少年を文学の世界へ向かわせることになった。クラスの女の子からの評判は、もはや鉄の表面のさびゆく相を早送りで画面に映し出したときのように、無惨に醜いものとなっていった。自らの身体を致命的に故障させる危険をあえて冒す鉄棒の逆上がり、そんなもの出来たからといってそれで何かがあらたに生み出されるわけではない、と、そう確信した少年にとって、文学の世界は真の世界であった。
でも、やっと飛び込んで自ら入り込んだ世界の、実は灰色のニヒリズム的色調に覆われた場であったことにしばらくして気がついたとき、はじめて真に文学に目覚めはじめたのだといえるのかもしれない。それが大学生の時であった。それまでの人生は羽毛布団でぐっすり眠っていた人生に等しい。
考えてみれば、逆上がりとは痛い想いをするかもしれないのにあえて頭と足を逆さにしてみる行為であって、実は人間の根源について意識を集中させるなんて行為は、実質的にはまさにこれと等しいのかもしれない。日常的なふるまいを意識的に否定する姿体を中空に現すのである。しかも頭を下にして見せるわけだ。これこそ文学といえないだろうか。
ただ、一歩さらに文学の世界の奥に立ち入って、人間の根源にあるものを描こうとしてしまうと、いよいよ人間の他者に対する暴力性や社会に対する破壊性に正面から向かい合わなければいけなくなってしまう。倫理性の、表層にぺらぺら漂うかのようなはかなさ、知性や信頼やといったことがらのうさんくささ、そうしてそれらを扱うことの難しさ、これに挑戦しようとするところに、文学が文学として尊重されるべき筆の腕前・卓越した技術の存在意義がある。多くの場合、ただのバイオレンスアクションドラマに成り下がってしまう。そして、自らの才能の無さを思い知らされることになる。
たとえばドストエフスキーの卓越さは、暴力性や破壊性の、コンクリの固まりのごとき冷ややかな堅さの中に、知性や友情や愛情の尊さを浮かび上がらせることのできるその抜群の筆の技量に存していると想う。そうして、ドストエフスキーのような書き手は、人類の長い歴史の中でも、そうそうたびたび生まれてくるわけでもない。
実は真の文学の書き手の書いた本の冊数など、ニイガタコクサイジョウホウダイガクライブラリーの蔵書のごくごくほんの一部にしかならないのである。今回はそんな数少ない真の文学の一例として、レッシングから1作品、中上健次の主要作、そして大江健三郎から二作品を選んでみた。
ロンドンのウォーター・ルー・ブリッジ近く、エムバンクメントで、中年の男性が保護された。記憶は失われていた。発することばの表現するところは、論理的で理性の破壊されていないことを十二分に示してはいるが、一般のノーマルな人々の理解では、それは狂人の言であった。やがて身元が明らかになる。古典ギリシャの文献学を専門とする大学教授であった。この彼のインナー・ワールドの展開が主旋律となって、二人の精神科医と彼との対話や、彼を知る人々の手紙による証言が伴奏となり、本書は進んでいく。圧巻は無人島での彼の体験だ。インナー・ワールドでは船乗りであった彼は、クリスタルの空飛ぶ円盤に追われ、仲間を奪われ、無人島に漂着するのだが、そこには知性の産物としか想えない石造りの文明が存在していて、しかしまた同時に、鼠の頭をしたイヌが二足歩行をしていて、猿との間で果てしのない殺し合いを続けていた。彼は大きな鳥の背に乗り、大空を飛びながら、その惨状をつぶさに眼にする。またギリシャ神話に登場する神々たちの対話にも引き込まれる。主人公の大学教授の独自の、したがっておそらくは著者レッシングによる自由なアレンジによる神話世界の展開に、読み手は魅せられる。彼をめぐる人間関係や彼の思想をつまびらかにしていく手紙の連なりには、レッシングの卓越した小説技法を見ることが出来る。250頁ほどの中編作品で、著者の意識には実験的なねらいもあったのかもしれない。読書経験の記憶に根づいて離れないだろう、かけがえのない作品となった。
文学とは、人間の根源について集中して意識してみるための読み物である。
小学校の低学年のとき、逆上がりができない子は存在そのものを否定されるような軽蔑の眼を注がれた。そのクラス中から受ける軽蔑のまなざしのつらさは、少年を文学の世界へ向かわせることになった。クラスの女の子からの評判は、もはや鉄の表面のさびゆく相を早送りで画面に映し出したときのように、無惨に醜いものとなっていった。自らの身体を致命的に故障させる危険をあえて冒す鉄棒の逆上がり、そんなもの出来たからといってそれで何かがあらたに生み出されるわけではない、と、そう確信した少年にとって、文学の世界は真の世界であった。
でも、やっと飛び込んで自ら入り込んだ世界の、実は灰色のニヒリズム的色調に覆われた場であったことにしばらくして気がついたとき、はじめて真に文学に目覚めはじめたのだといえるのかもしれない。それが大学生の時であった。それまでの人生は羽毛布団でぐっすり眠っていた人生に等しい。
考えてみれば、逆上がりとは痛い想いをするかもしれないのにあえて頭と足を逆さにしてみる行為であって、実は人間の根源について意識を集中させるなんて行為は、実質的にはまさにこれと等しいのかもしれない。日常的なふるまいを意識的に否定する姿体を中空に現すのである。しかも頭を下にして見せるわけだ。これこそ文学といえないだろうか。
ただ、一歩さらに文学の世界の奥に立ち入って、人間の根源にあるものを描こうとしてしまうと、いよいよ人間の他者に対する暴力性や社会に対する破壊性に正面から向かい合わなければいけなくなってしまう。倫理性の、表層にぺらぺら漂うかのようなはかなさ、知性や信頼やといったことがらのうさんくささ、そうしてそれらを扱うことの難しさ、これに挑戦しようとするところに、文学が文学として尊重されるべき筆の腕前・卓越した技術の存在意義がある。多くの場合、ただのバイオレンスアクションドラマに成り下がってしまう。そして、自らの才能の無さを思い知らされることになる。
たとえばドストエフスキーの卓越さは、暴力性や破壊性の、コンクリの固まりのごとき冷ややかな堅さの中に、知性や友情や愛情の尊さを浮かび上がらせることのできるその抜群の筆の技量に存していると想う。そうして、ドストエフスキーのような書き手は、人類の長い歴史の中でも、そうそうたびたび生まれてくるわけでもない。
実は真の文学の書き手の書いた本の冊数など、ニイガタコクサイジョウホウダイガクライブラリーの蔵書のごくごくほんの一部にしかならないのである。今回はそんな数少ない真の文学の一例として、レッシングから1作品、中上健次の主要作、そして大江健三郎から二作品を選んでみた。
ロンドンのウォーター・ルー・ブリッジ近く、エムバンクメントで、中年の男性が保護された。記憶は失われていた。発することばの表現するところは、論理的で理性の破壊されていないことを十二分に示してはいるが、一般のノーマルな人々の理解では、それは狂人の言であった。やがて身元が明らかになる。古典ギリシャの文献学を専門とする大学教授であった。この彼のインナー・ワールドの展開が主旋律となって、二人の精神科医と彼との対話や、彼を知る人々の手紙による証言が伴奏となり、本書は進んでいく。圧巻は無人島での彼の体験だ。インナー・ワールドでは船乗りであった彼は、クリスタルの空飛ぶ円盤に追われ、仲間を奪われ、無人島に漂着するのだが、そこには知性の産物としか想えない石造りの文明が存在していて、しかしまた同時に、鼠の頭をしたイヌが二足歩行をしていて、猿との間で果てしのない殺し合いを続けていた。彼は大きな鳥の背に乗り、大空を飛びながら、その惨状をつぶさに眼にする。またギリシャ神話に登場する神々たちの対話にも引き込まれる。主人公の大学教授の独自の、したがっておそらくは著者レッシングによる自由なアレンジによる神話世界の展開に、読み手は魅せられる。彼をめぐる人間関係や彼の思想をつまびらかにしていく手紙の連なりには、レッシングの卓越した小説技法を見ることが出来る。250頁ほどの中編作品で、著者の意識には実験的なねらいもあったのかもしれない。読書経験の記憶に根づいて離れないだろう、かけがえのない作品となった。
『軽蔑』
- 中上健次 集英社
金持ち御曹司なのにちんぴらまがいの生き方に身を落とすオトコと、新宿のトップレス・ダンサーのオンナとの悲しい恋物語。中上作品的な空想的神秘的シーンがふんだんに織り込まれていて、うつくしい幻灯のムービーを見ているようだった。トップレス・ダンサーには羽が生えていて、彼女は中空に浮かびあがることができる。でも、それは舞台の上だけの話。オトコと所帯をもって地上に降りてしまっては、いじらしいばかりにオトコと五分と五分の間でいようとするための、ガラス細工のような意地が薄氷のごとく張られていくだけ。中上作品の、救いの一切存在しない徹底的なリアリズムには、でも実は随所に空想的神秘的なシーンが織り込まれていて、それがあるために読者は作品全体に身体を浸すことによって、どこか救われていくような錯覚に陥っていく。とても不思議な魅力だ。
『千年の愉楽』
- 中上健次 河出書房新社 1992.10
オムニバス的にショート・ストーリーが続いていくが、すべて同時代の同じ土地での出来事。二人の夫婦の半生ほどの時の長さで(でも実はそれは千年にも続こうかとするような伸縮自在の時であり・・)、路地と呼ばれる特殊かつ根源的な場が舞台になる。ただしこの路地は、南米の鉱山町や北海道のアイヌの民の住処ともオーバーラップしてくる。本書は、路地のみに生きる二人の夫婦のしずかでしんみりしたラブ・ストーリーでもある。夫は死を祈る坊主。妻は命を取り上げる産婆。ショート・ストーリーに出てくる若い衆は、すべてこの産婆が取り上げた男の子だった。彼らはすべて、中本の一統として、女を虜にする男の魅力をみなぎらせ、路地という人間の生の限界状況で神秘のもう一つの世界と接しながら、悪事を尽くすも、それぞれの生の一瞬を生き抜く。そして老婆がそのさまざまな生のありとあらゆることを肯んじる。彼女によるあらゆる生の絶対的な肯定は、解放であり癒しであり再生でもある。奇跡の名作だとおもう。この作品に出会えたことが、人生を価値あるものにしてくれる、それほどの作品である
『枯木灘』
- 中上健次 河出書房新社 1980.6
中上健次のいわゆる秋幸三部作の第二部。日本文学史上最高傑作のひとつである。映画に名シーンがあるように、小説にも忘れられない場面がある。この作品では、川に浮かぶ盆の灯籠おくりの光が、人肌にぬるま湯のようにまとわりつく闇の中にぼんやりといくつもゆれていた、あのくだりだろうか。もちろん、その他にもたくさんの名場面が作品の全編に渡ってちりばめられている。ダンプカーが暴走族のバイクを倒して踏みつぶすシーンもあれば、肌に汗の光をまばゆく光らせながらつるはしで女の肌のようにやわらかく土をめくる場面もある。中上の文体は、風景描写と心理描写を渾然一体にして濃密なる今この時を表現することに成功している。彼の文体でなければどうしても描けない世界が、熊野的神話的空間だ。血と大地の肉感的な情の世界と、川や海や木々の葉に反射して撥ねる美しき光の世界が、読み手をまさに暴力的に作品の中に引きずり込み、なのに気がつけば、こころはあったかく癒されている。ただし、冒頭で触れたクライマックスで、事態は一気に動いていく。そして、秋幸三部作の第三部、地の果て至上の時につながっていく。
『奇跡』
- 中上健次 小学館 1999.9
千年の愉楽の続編的な作品。ただ枯木灘とも交差する作品であって、秋幸三部作からスピン・オフしたようなパートもある。それは秋幸の兄、イクオのパートであり、彼はギターを奏で微笑むだけで何人もの女を魅きつけ難なく腰から落とし絶えず女の取り巻きを引き連れ回る若者であった。彼の一族一統は例外なく女を魅きつけもてあそび捨てていく者たちであり、例外なく若死にしてしまう。そんな彼のシャブ中毒で自死するまでの物語が、本書のサイド・ストーリーとして織り込まれている。
近代的理知的なるものの境界の外に除外され、その啓蒙的明るさ・経済的豊かさからシャットアウトされ、そのようなものの完全に及びえない空間たる路地が醸し出す、神話的なる甘露の魅力。中上作品の魅力の一つだと想う。元は土地の荒くれ者で主人公タイチの後見人だったトモノオジが、アル中になって精神に異常を来してしまい、精神病院で妄想に引き込まれ、ヌエになりイルカになり湾の海底深く潜りながら、路地の唯一の産婆オリュウノオバと過去未来を縦横に経巡りながら会話を交わす。その会話ので、タイチやイクオの物語が進行していく。暴力と非倫理的性の渦巻く路地の神話的神秘的な甘露が艶美に映写され、人間社会の底に生きる者たちが暖かく描出され、でも周辺が周辺のまま近代的理知的世界の境界の外に追いやられたままの、冷たい現実も記録されている。
近代的理知的なるものの境界の外に除外され、その啓蒙的明るさ・経済的豊かさからシャットアウトされ、そのようなものの完全に及びえない空間たる路地が醸し出す、神話的なる甘露の魅力。中上作品の魅力の一つだと想う。元は土地の荒くれ者で主人公タイチの後見人だったトモノオジが、アル中になって精神に異常を来してしまい、精神病院で妄想に引き込まれ、ヌエになりイルカになり湾の海底深く潜りながら、路地の唯一の産婆オリュウノオバと過去未来を縦横に経巡りながら会話を交わす。その会話ので、タイチやイクオの物語が進行していく。暴力と非倫理的性の渦巻く路地の神話的神秘的な甘露が艶美に映写され、人間社会の底に生きる者たちが暖かく描出され、でも周辺が周辺のまま近代的理知的世界の境界の外に追いやられたままの、冷たい現実も記録されている。
『鳳仙花』
- 中上健次 小学館 1999.3
母の不倫の子として生まれたフサの、悲しい恋物語。風景描写がとても美しい。川や井戸の水が光に撥ねるきらめき、風が山の雑木を揺らす音。紀州和歌山の風土が印象派の絵画の世界に入り込み、フサと勝一郎の恋物語がそこで映える。普通の夫婦の普通の生活なのに、その美しさを描く中上の筆の技は、もう奇跡に近い。本書は秋幸三部作の番外版的な位置にあるが、これ自体独立の作品として、それ自身の生命が脈打っているのを感じることが出来る。秋幸三部作の三作目、地の果て至上の時の約20年前に当たる物語。本書を読むことによって、秋幸三部作の登場人物一人ひとりにあらたな想いを抱くことができる
『地の果て至上の時』
- 中上健次 小学館 2000.3
近代化の破壊的な波に抗しつつ、しかしやがてつぶされていく前近代的周辺の暴力性を背景に、父親殺しのテーマを突き詰めていった作品、とでもいえようか。しかし、この作品の描き出していることがらの深さ・複雑さは、並みの文学作品の水準ではない。日本文学は彼の存在によって、一段と厚みを増したといいたい。
中上のこの作品には、徹頭徹尾、暴力性と破壊性が貫き通されている。読み手のこころの救いとなるようなキャラクターは皆無である。ただし、救いとなる場、これが用意されていた。個々人の誰もがあらがいえない近代化の流れの中で、中上が本書に描き出した「路地」と「山」は、人間の奥底にある暴力性や破壊性のさらにその根本にあってしかもそれらをあたたかく抱擁してくれる最終帰着地点であるかのようだった。この「路地」と「山」が、出発点としては人間性を拒否し排除する場であると感じざるをえないにもかかわらず、人の生の最後に帰り着きたいと想う場であることが、物語の進行の中でしみじみと感じられてくる。「路地」と「山」という場こそが、人の救いとして用意されていたといえまいか。
中上のこの作品には、徹頭徹尾、暴力性と破壊性が貫き通されている。読み手のこころの救いとなるようなキャラクターは皆無である。ただし、救いとなる場、これが用意されていた。個々人の誰もがあらがいえない近代化の流れの中で、中上が本書に描き出した「路地」と「山」は、人間の奥底にある暴力性や破壊性のさらにその根本にあってしかもそれらをあたたかく抱擁してくれる最終帰着地点であるかのようだった。この「路地」と「山」が、出発点としては人間性を拒否し排除する場であると感じざるをえないにもかかわらず、人の生の最後に帰り着きたいと想う場であることが、物語の進行の中でしみじみと感じられてくる。「路地」と「山」という場こそが、人の救いとして用意されていたといえまいか。
『洪水はわが魂に及び 上』大江健三郎全作品 第2期4
- 大江健三郎 新潮社 1994.11
『洪水はわが魂に及び 下』大江健三郎全作品 第2期5
- 大江健三郎 新潮社 1994.11
核シェルターに住み着いた父子と、自由航海団の若者たちの物語。子はいまだ幼児、障害をもって生まれた。名をジンという。様々な鳥の声を正確に聞き分けられる。父は自らの名を勇魚と変え、海の鯨と陸の大樹の双方の魂と交信しながら、ジンとともに、人の世から隠れ生きていた。そこに自由航海団の若者たちが現れる。暴力の恐怖に覆われた局面は、やがて勇魚・ジンのコンビと自由航海団の結合、そして体制の檻から逃れ自由を求め大海に船出する夢を求めた共同戦線へと展開する。著者・大江が日本の文学史に残る優れた書き手でありうることを、本書はいっさいの疑念無しに証明している。すばらしい作品。シンボリックなものごと・ことがらがたくさんちりばめられているが、メタファーの過剰は一切感じさせない。物語の展開にぐいぐい引き込む。その物語の構造は、ジンの存在によって基礎づけられている。彼の存在は、登場人物もまた読み手も、双方ともに、現代社会にあって人間性を押しつぶすあらがいえない重たいものから、解放してくれる。
『燃えあがる緑の木・第一部:救い主が殴られるまで』
- 大江健三郎 新潮社 1993.11
『燃えあがる緑の木 第二部:揺れ動く<ヴァシレーション>』
- 大江健三郎 新潮社 1994.8
『燃えあがる緑の木:第三部・大いなる日に』
- 大江健三郎 新潮社 1995.3
両性具有のオトコオンナと、救い主になりたいのに情けなく弱虫なオトコの物語。全三部作の長編作品。性転換して男から女になったサッチャンがオトコオンナで、他者の命のために自らの命を捧げたいと祈り続けるのが弱虫救い主の隆くん。隆くんは、救い主を意味するギー兄さんと呼ばれるようになる。実は彼は二代目のギー兄さん。初代のギー兄さんは性的な事件を起こして殺され、テン窪の人造湖に投げ込まれていた。サッチャンとその二代目ギー兄さんの二人は、屋敷の主であった老婆のオーバーに庇護され、育てられる。そしてともに四国の山奥の森の中で、その屋敷を土台に独立した生活共同体を作ろうとする運動に入る。しかし、村の民人たちの盲信的崇拝と暴力的反抗の両方に直面する。
森、屋敷、谷、在、テン窪の人造湖など、物語の全体の意味構造を決めていくメタファーがテキストに遍在、作品の雰囲気を作り出している。中でも、イエーツの詩に出てくる燃えあがる緑の木が中心になる。本書は実験小説でもある。物語の語り手は著者自身ではなく、そもそも著者自身が物語の中に登場してくるので、ナラティブは複合的だ。そうして著者の読書経験や思索がふんだんに織り込まれていく。この箱庭的な私的心象風景の広がる世界が本書の物語の場となっている。
最後の最後、残り100頁くらいのところから一気に物語が加速しはじめる。ラストはその後を感じさせる終わり方で、うまい映画の作り方と同じ。大江のちょっとニヒリスティックな、でも社会改革へ向けた理想も原則も実はまったくあきらめていない姿勢、これはとっても好感の持てるものだった。繋ぎの思想とでも呼べるだろうか。宗教組織の官僚化や尖鋭化、そしてセクト化と分裂、これも実にリアルに描かれていた。ある普遍的な問いを具体的な時代状況の中で登場人物に即して個別的に追求しつつ、しかし時代を超えた含意をそこに見出そうとする作品作りのスタイル。すばらしいと想う。ただし著者自身が物語に登場して著者自身の作品について語るところは鼻についてしまった。そこだけが残念。
森、屋敷、谷、在、テン窪の人造湖など、物語の全体の意味構造を決めていくメタファーがテキストに遍在、作品の雰囲気を作り出している。中でも、イエーツの詩に出てくる燃えあがる緑の木が中心になる。本書は実験小説でもある。物語の語り手は著者自身ではなく、そもそも著者自身が物語の中に登場してくるので、ナラティブは複合的だ。そうして著者の読書経験や思索がふんだんに織り込まれていく。この箱庭的な私的心象風景の広がる世界が本書の物語の場となっている。
最後の最後、残り100頁くらいのところから一気に物語が加速しはじめる。ラストはその後を感じさせる終わり方で、うまい映画の作り方と同じ。大江のちょっとニヒリスティックな、でも社会改革へ向けた理想も原則も実はまったくあきらめていない姿勢、これはとっても好感の持てるものだった。繋ぎの思想とでも呼べるだろうか。宗教組織の官僚化や尖鋭化、そしてセクト化と分裂、これも実にリアルに描かれていた。ある普遍的な問いを具体的な時代状況の中で登場人物に即して個別的に追求しつつ、しかし時代を超えた含意をそこに見出そうとする作品作りのスタイル。すばらしいと想う。ただし著者自身が物語に登場して著者自身の作品について語るところは鼻についてしまった。そこだけが残念。
- <癒しのゆるさ・森絵都の世界を体験する>
『架空の球を追う』
- 森絵都 文芸春秋 2009.1
短編集。とりたてて基調となるメッセージやメタファーが提示されているわけではないが、オンナのいろいろな人生へのやさしいまなざしが起点になっていたと思う。少年野球チームの熱血コーチの指導にもかかわらずゆるく遊んでしまう野球少年達をスタンドで見つめるもっとゆるゆるのヤング・ママたちがいて、年に数度定期的に飲み会を開き飲みまくって愛や恋や家庭や不倫やさらには新宿・池袋の有利不利までなんでもかんでも議論してしまうアラフォー近づく三十路のヤング・ミセスたちがいて、ある雨の夜に乗ったタクシーがきっかけで不倫が人生の再スタートになりうることを知ったオトコに別れ話を持ち出されたオンナがいて、難民キャンプで数十年家族を守り続けながらもひっきりなしにやってくるNGOスタッフやジャーナリストの正義の味方ヅラした上から目線に抗して尊厳を守り続けようとする30代のでも老婆と呼ばれるママがいて、40代前半石油会社社長の息子というやっと掴んだ玉の輿との婚姻を守るべくかつての自分をひた隠しに婚前旅行でドバイにやってきてでもその社長の息子がカツラを取ってプールに飛び込んだことで思わずかつてのズベズベちんぴらだった頃の言葉遣いや物腰が出てしまってしかしその社長のはげ息子にやさしくやさしく抱擁されるオンナがいて、スペインの空港で店員の無責任な説明と対応のせいでせっかく買ったワインの厚紙のケースの底が抜け空港の通路に瓶の破片と赤の液体をぶちまけてしまったイギリス人老夫婦が黙々と周りのヤジや汚らしいものを見る眼を一切気にせず綺麗にすべてを片づけてその全部が終わって二人ほっとしてほのぼのと微笑んでいる姿をチョコレートショップから見つめ続けるオンナがいて、実はその彼女はイギリス人老夫婦が買った厚紙ケース入りワインを買うつもりだったのであった。この最後の小品は逸品だと思う。チョコレートショップから見つめる彼女は真のイギリス紳士を見た想いがするとこころでつぶやきそのまなざしはおそらくはようやく本物に出会った感動の表情を見せていると想うのだけれど、この彼女に何があったのか、読者はついつい自らストーリーを作って想像してしまう。この小品がさまざまなオンナの人生いろいろ小話の一番最後に配されているので、それはなおさらのことだとおもう。もちろん、チョコレート・ショップからイギリス人老夫婦を見つめていたのは、ほんとうは作者自身かもしれないけれど。
『アーモンド入りチョコレートのワルツ』
- 森絵都 講談社 1996.10
中学生が主人公の小品3つ。3つともそれぞれのピアノ曲を基調に、中学生の時期にだけ流れるキリンレモンや三ツ矢サイダーのような空気にふれられる作品だった。3つの曲は、バッハのゴルドベルグ変奏曲のアリア、シューマンの子供の情景、そしてサティ。読み終えてすぐにサティのCDを買いに行く。でも、売ってなかった。タワー・レコードにまで足を延ばしたけれども、なかった。サティを主題にした3番目の作品は、どうしてもネット通販でなくこの足で歩いて直に買いに行きたくなる、そんなエンディングだったわけだ。結局無駄足に終わってしまったけれども、そのためによけいにサティが聴きたくなってきた。それといっしょに、森絵都の作品の世界もどんどんイマジナリーに広がっていった。中学生時代の空気を描き出すのは非常に難しいと想う。この時代を甘酸っぱく懐かしく思い起こしたくなるような人生は、しあわせな人生ではないだろうか。森絵都が中学生時代を描いてくれると、想像上の追体験によって、人生の後から思い起こして大切に撮っておきたい中学生活の場面場面を楽しむことができる。しかも、ただ甘酸っぱいだけでなく、ギスギスやモンモンもありながら、ユルユルのフアフアも織り込まれてくるから、森絵都の筆のタッチは、油絵と水彩画と色鉛筆画のすべてを美しくひとつの世界にまとめていくことを可能にしているようで、ほんとうにすごい描き手だと思う。
『カラフル』
- 森絵都 文藝春秋 2007.9
ある日突然天使のプラプラが現れ、抽選にあたったからと、この世に戻るチャンスが与えられる。実はその男の子、自殺だった。中学校でいじめにあっていた彼。父も母も兄もみな味方でなく、それどころか彼は家族それぞれの人の道に外れた異常な行動に直面し苛まれ打ちのめされてしまう。と、筋だけ書けばとてもシリアスな現代的日常のよくあるドラマである。しかし、そこは森絵都、冒頭の天使のプラプラ登場からはじまり、彼女ならではのあたたかでほんわかとしたファンタジーが展開されていく。ストーリーのどんでん返しも、なんとなく予想できるのに、こころの琴線にふれてくる。主人公の男の子や天使のプラプラをはじめ、彼女の得意のどこかほのぼのぽかぽかしたキャラたちのやりとりが、読んでいてこころを和ませてくれる。大人も楽しめるヤング・アダルト作品の逸品、森絵都ファン必読の代表作。ロー・ティーンからおっさん・おばはんまで、とっても幅広い読者層を惹きつける作品である。現代にふあふあ生きる人たちのありのままの姿が、此岸と彼岸を行き交うキャラを登場させたファンタジーによって、読みやすくありありといとおしく想えるように描き出されていく。同世代の作家の中でも、非常に貴重な書き手の一人だと思う。
『いつかパラソルの下で』
- 森絵都 角川書店 2005.4
父のキャラの源流を求めて、兄・姉妹の三人の子供たちがその足跡を探っていく。父は堅物だった。それも異常なまでに鉄壁のやつ。それを子供に押し付ける。そんな父がなんと、まったくもって想いもかけないことをやっていた。この源流をめぐる旅は、佐渡に行き着く。佐渡は一度、たっぷり堪能したことがあった。だから、読んでいて想像しやすかった。ただ、佐渡は東京方面の人たちにとって、特別な異空間?そんな印象が残った。森絵都のタッチが、父との和解、なんて重々しいテーマを、ゆるくほんわかと演出していく。彼女の描くオトコのキャラは、読んでいていつも楽しい気持ちになる。オトコの機微ってもんが、分かってる女流作家だ。そう思う。でも、ときにオンナの願望の具象化されたオトコキャラ・ゆるゆる版みたいなのが出てくる。で、それがまたいい。本書の達郎と野々の関係なんて、森絵都おはこのほんわかタッチで描かれていて、その双方のだらしなさは、なぜかこころを癒してくれる
『風に舞いあがるビニールシート』
- 森絵都 文藝春秋 2006.5
森絵都の短編集。どれも出色。ほんわかものからシリアスものまで。最後の章におさめられた表題の短編は、UNHCRで働く男に恋をしてしまった女の人の物語。テンポも切れも良いうまいとうならせる短編。ふつうはそういった短編は内容はいまいちの場合が多いのだが、この作品は例外。じーんとこころの壁に結露を作り出すように悲しくもでも人の強さを感じさせる物語だった。ジェネレーションXも面白かった。日常生活というどんよりよどんだ粘性の高い液体の中を泳がざるをえないような夢を失った中年親父が、一見礼儀知らずのどうしょうもない若者の一皮剥いた姿と青くも貴い夢に惚れてしまい、木更津へ向けてアクセルを踏み込む一瞬のシーン。これがたまらない。森絵都は中年男を虜にする。
- <その他・ランダムに>
『温暖化の<発見>とは何か』
- ワート みすず書房 2005.3
まるでSF小説のようだった。それも、壮大な大河ドラマ風。むずかしい科学の話がたくさん出てくる。でも、素人がなんとなく想像できる次元までかみ砕いてくれているので、議論の筋道を追うことはできる。気候科学の発展が、実に様々な専門分野の研究の間の、国際的な協働を通じて展開してきたこと、しかもそれは実は大きく偶然に左右されつつしかし時に現れる卓越したプロジェクト・リーダーの力によるものであったこと、これはもう奇跡の物語とさえいえそうだ。微生物、塵、風、雲、太陽、天気予報、海、火山、農業、核兵器、軍事作戦、考古学などなど、関連する単語を紙に書いて壁に貼っていくと、家中が百科事典の項目のように無数のことばに囲まれてしまいそうだ。科学の営みの凄さから、人間の凄さを感じられると同時に、一つひとつの専門分野の狭い世界で一生を過ごしていく科学者たちの人生を想うと、息が詰まってもくる。けれども、その一つひとつの狭い部屋のおそらくは天井近くの小さな小窓から、地球規模の気候の変動という壮大な認識領域の開拓を想像していく気分は、きっと、実に爽快なものに違いない。1世紀の時をまるまる超える科学の大河物語。ただひとつだけ無い物ねだりをすれば、気候変動がもたらす悲惨な現実について、肌感覚でイメージできるような記述があったならば、読者がより実感をもって温暖化問題に身を震わせることができたかもしれない。
『詩の構造についての覚え書』
- 入沢康夫 思潮社 1968.2
解説によると、入沢詩論のエッセンスがつまってるらしい。あるいは良質の入門書。詩の構造などという、いかめつくしかも退屈そうな題名にもかかわらず、一般向けの内容で、しかもSF調なエンターテイメント満載の宇宙論のように興味をそそられ読みつづけることができた。すでに詩論の域を越えて、認識論さらには存在論へと、読者の思惟を誘ってくれる。そんなノートでもあった。いや、そもそも詩論の書なるものはもっともすぐれた認識論・存在論の書であるというべきか。著者・入沢の極論的な理論的問いかけは、淡泊ながらもよくよく考え込んでみると、じつにワクワクさせられる。本書最後の方に補遺として入れられた文書には、こんな問いかけがあった。本文よりも長字数の題名をもつ詩というものもありえるだろうか。題名が存在する場所が問われているわけで、考えてみると、本文の世界でもなく、読み手の解釈する世界でもない、なんとも中途な存在様相が浮かび上がってきて、題名について考えてみる刺激的なツボ的問いかけになっているようだった。全体として著者が問題にしたのは、ことばの関係であった。構造化されるはずのことばの関係は、書き手と読み手のそれぞれで二重になる。著者・入沢のまなざしは、この構造化された二重のことば関係が壊れるところにも注がれる。答えのない問いの放浪をしているようで、思惟は着実に詩論の領野の奥深く入り込んでいく。安全なところにゆっくりと座って珈琲を飲みながらついていけばいい読者としては、著者の悩みやその苦しさはよそに、詩論の宇宙がその先に通ずる認識論と存在論の深みを想像しながら知的刺激を受け、ワクワクと楽しむことができる。
『ベートーベン』
- 長谷川千秋 岩波書店 1938.11
コミックのようなノリの伝記だった。出版されたのが昭和10年代であり、出版媒体が岩波新書であることを考えると、もしかしたら画期的なスタイルの本だったのかもしれない。ほとんど思いこみの断言調がところどころにあり、読前には伝記的研究書を想像していたこともあいまって、最初は違和感の尽きることなく湧き出る読書となってしまっていた。けれども、読み進めるうちに、だんだんと、その違和感が薄らいでくる。そうか、これはコミックなんだ、そう思えばいい。割り切ると、とたん、面白くなってきた。なんといっても、テンポが良い。しかも、漫画のカット割りに描き込まれたベートーベンの息吹まで伝わってきそうだった。
『コヨーテ・ソング』
- 伊藤比呂美 スイッチ・パブリッシング 2007.5
詩的な小さい物語の短編集、そんな感じの作品だった。荒野の平原をゆくコヨーテ。別段、取り立てて変わったところのある生き物でもない。いわんや、宇宙からやってきたわけでもない。フツウにアメリカの荒野の平原に何世代にもわたって存在してきた犬のような存在である。女の子が好きで、性的なことばかり考えていて、小さなプライドにこだわり、都合の悪いことはなかったことにしようとする小賢しさも中途半端な男的存在。そのコヨーテが主人公のようでいて、実は書き手の彼女の脇役でもあった。コヨーテは彼女にとって、どんな存在なのか。考えていると、書き手の彼女は実はとてもシンプルな人間であるような気もしてくる。いつもながら、彼女の手にかかると、ありとあらゆる性的艶的恋的などなどのすぐれて香水的な生の悪臭ごまかしグッズが、安っぽいプラスチック製品に想えてきてしまう。人間存在の原点がむき出しにされる。でも、それにつきあっていくと、なぜか、癒されてくる。だから読んでいてとても不思議な感じがしてくる。
『私』
- 谷川俊太郎 思潮社 2007.11
ことばへのこだわりが、ことばへの信頼へ昇華していくと、とても良いと思う。この作品は、それがうまくいった例のひとつではないだろうか。小説より詩の方が好いんだと、そううたう作品でさえ、卑下の裏返しの傲慢にはならず、思い上がりの根拠なき断定でもなく、石清水が渇いたのどを通ってクウフクの胃袋まで染み渡っていくように、自然と読むことができた。やさしいタッチでことばを紡ぐ。その技量は抜群だと思う。水が川や湖や海や雨や水道水や泥水や、いろいろな水になりながら地球にあって循環しつつ滞在しているように、ことばもまた、契約書や条約や日記や愚痴や芸術作品や恨み言やラブレターになりながら、地球でめぐりめぐってずっと人々のもとに存在しつづけているというアナロジー、これは実在の相をまるでパステルカラーの童話の絵本で描き出したような感じだった。ことばから逃げるための沈黙ではなく、ことばにやさしく接するための沈黙。ことばとともにありつづけることをこれまでずっと意識してきた人の中の、さらに選ばれた人だけが、そんな大切な沈黙を経験できる幸運に恵まれるのかもしれない。
『対岸の彼女』
- 角田光代 文藝春秋 2004.11
女の生や生き様について、題材も展開もごくごくありきたりの今風小説。なのに、とにかくおもしろい。読ませる。引きずり込む。だから、とても不思議だった。ドラマのシナリオみたいな作風。コミック的でもあるか。ただ、キャラの作り方は文学だった。登場人物の息づかいが聞こえてくる。男は、ろくでもないやつばかり登場、きわめて女の世界シフトの著しい作品。タクシー運転手のおとーさんの一シーン、ただそれだけが男の存在意義だったのだけれど、唯一のそこはとっても味の良い場面だった。ごくごくあたりまえの時代的な事柄をそこそこ誇張しながらフツウの予測可能な物語が編まれているのに、読み手を引きずり込ませる筆の力を発揮している作品である。
『青が散る』
- 宮本輝著 文藝春秋 1985.11
新設大学を舞台にした青春小説。もう何十年も前に、一度、読んだことのある本だった。ふと何気なく手に取り、再びページをめくりだすと、もうとまらなくなってしまった。青春小説って何?と聞かれたら、この本を例に出せばそれで十分。典型的な青春小説。ヒーローは誰一人出てこない。うまくいかないことだらけ。それぞれに背負ってる荷を下ろすことができず、あてどもなく、右往左往する。この著者の物語は、独立の命を吹き込まれ、独りでに動き出す。登場人物も映像を見ているようにくっきりと描かれる。大江健三郎のように深く突き詰めた思想に貫かれることはなく、村上春樹のようにポップにクールにおしゃれでもない。地べたを這って泥臭くなった生身の人間の、どぶの匂いが漂ってくる、そんな作風だ。ある特定のキャラの作りが抜群で、この作品では祐子だろう。決して美人じゃなく華やぐところもないのに、男を静かに惹きつける魅力を備えた女性。しかも、生活力、つまり生き抜いていく力は除草剤をまかれた後にも成長し続ける雑草のように強い。精神を病んだ安斎も、この著者得意の人物だ。逃れられない業。著者のキーワードの一つ。生身の人間のどぶ川の匂いを漂わせながらも、でも、この作品では、まるでキリンレモンの味がするように青春が描かれている。どうして青春小説が人気ジャンルとして確立してきたのか、ようやく分かった気がした。何十年も前にこの作品を読んだときは、もちろん面白かったのだけれど、いまほどその物語や登場人物の中に入り込んでいかなかったと記憶している。それが、40を過ぎたいま、惹きつけられてならない。過ぎ去った月日の眺望。これなくして生きられない年齢に至ったか。青春小説は、歳くった者たちのために存在しているのだと思う。とくに、この著者の人間を見る目のやさしさが、40男のこころを締め付けてくる。でも、20代の内に読んでおくことによって、40代での再読がよりいっそう深みのある経験となるわけだ。ぜひいまのうちに読んでおいて欲しい一冊だ
『Breakfast at Tiffany's』
- Truman Capote Kodansha International 1990
魅力的な人物を創造するのが、文学の魅力的な役割のひとつだと思う。カポーティの描いたホリディ・ゴライトリーは、まちがいなくその実例だ。でもその彼女は、オードリー・ヘップバーンの存在感によって誤解されてしまってるように思う。もちろん、旅行中と書かれたネーム・プレートや、バーでの会話、デートの最中の仮面のかわいい万引き、そしてネコという名の猫を見つめるあのまなざしなど、オードリー・ヘップバーンを想像せずに読むことはできなかった。眼にこころに焼き付いてしまっている。映画には原作以上にカリカチュアされたへんちくりんな日本人が出てくるが、差別だなんていきり立たず、アメリカのメディアの無知をそっと悲しむ程度で良い。オードリー・ヘップバーンの魅力は、それ自体、貴い絶対的なものだ。でも、そんな彼女の存在感が、原作の読みをゆがめてしまう。カポーティの筆が創り出したホリディ・ゴライトリーというキャラは、絶対の自由を絶対的に自由な手段でもって追い求めていく何ものかの象徴である。ただそこには、ニヒリズムも感じられる。ネコに名前を付けないのは、名前を付けることでそのネコの自由を奪ってしまうからだと思うのだけれども、名前をつけないことはすべてのものごとから距離を確保することでもあり、それはやはり、とてもさびしいニヒリズムだと、そう感じてしまった。彼女のトークをすべて理解できたら、もっともっとそのキャラの醸し出す魅力に迫っていけるだろう。でも、残念なことに語学力が足りなかった。辞書にも限界があるようなたくさんの語彙。本書を読み終えていま一番心に残っている想い――鯨が空を泳げるほどの土砂降りの雨の中で、ホリディ・ゴライトリーのネコを探してみたい。
- <手持ちぶさたな春の一時のちょっとしたエンターテイメント・村上春樹の短編>
『東京奇譚集』
- 村上春樹著 新潮社 2005.9
この人の短編はとてもいい。もちろん、本質的に短編作家だということもないだろうけれど、この人独特の味を一切の嫌み感ずることなく堪能できる。長編だと、またか、っていった感覚に陥ることがあるので、短編だと安心できる。この短編集の最後の作品、品川猿には、安部公房的な匂いがした。もちろん、下水道を闊歩して気に入った女の子の名前を盗んでしまう猿が登場するのだから、有名料理屋の味がディナーのコースを予約せずともランチで十分楽しめてしまうような感じで、この作家の味を味わうことができる。どろどろねちねちしたこころの闇の世界をそのつらさ苦しさはそのまま保冷しながらクールにパステル・カラーで装飾されたコスモポリタンの風景にしてしまうのだから、超一流の筆をもった作家だといえるだろう。
『回転木馬のデッドヒート』
- 村上春樹 講談社 2004.10
日常生活の中でぽっかりと開く非日常的な穴、これがたしかにその卓越した筆致で見事に描き出されていた。誰かから聞いた話で、それ自体が話されたがっている物語、という何気ない設定も、文学的な何ものかをいろいろなものから自由に創り出していく上で、なかなかにうまい方法だったとおもう。この短編集の一番最後にあるナイフの話、これが特に興味深かった。村上の世界ではないような気もした。たしかに異質な、実験的な、練習のための、しかも短編のくせに深い深い奥行きを感じさせ、物語全体の雰囲気を切れ目のない一枚の布地に仕立て上げるような、そんな印象を抱かせる作品であった。秀逸だと思う。回転木馬のデッドヒートなんて題名で、作者が村上である。これによって読者はすでに期待を抱く。あるいは正確に言い換えれば、洗脳される。洗練されたシティ・ストーリーがファッショナブルに展開されていくはずだと、そう思いこまされる。しかし、本書の小作品群は、冷たい水で顔を洗って、ソファーでなく机に向かって読み直せば、そんな期待からはほど遠いということがすぐ分かる。彼の世界の深まりゆく可能性の一端が現れている。
『1973年のピンボール』
- 村上春樹 講談社 1983.9
ある本が名作であるための条件はいくつもあるかもしれないが、ひとつ大切にしたいことがある。雰囲気だ。その作品を読めば甦る雰囲気。良質の作品には独特の雰囲気がある。そして、それが忘れられなくなる。1973年のピンボールは、最初、20代のときに読んだ。今回、40代になって、つまり20年ぶりに読んでみた。やはり、あの雰囲気を味わうことができた。しかも、当時よりもいっそう重厚に。ピンボールのスペースシップ、そしてジェイも鼠も、あの時代あの時期あの場所に、永遠に存在しているはず。深夜のかつて養鶏場だった倉庫でのシーン、永遠にこころに残ることになるとおもう。今年度一番のおすすめ!
『風の歌を聴け』
- 村上春樹 講談社 1982.7
軽いタッチのポップな青春ものの体裁をとりながら、ズンとディープなテーマが扱われている。けれども、安易な張りぼて小説にはなっていない。佐々木マキの装幀がなかったら、異質な作品になっていたような気もする。表紙のイラストがイメージを創り出している部分、小さくないようにおもう。生と死、青春と絶望、生き続けるために自分を世の中に寸分の狂いなく合わせなければいけない状況にあって、自分自身の居場所を都会に穴掘って確保しようとするニヒリスティックなスタイル。日常生活のフツウのシーンにそこからの抜け道の存在を知らせる神秘的な出来事を経験して、でもかえってただ痛みを発するだけの空っぽの自分を再発見するだけでおわってしまうつらさ。こんなことがらが、なんてスタイリッシュに描かれていることだろう。とても80年代前半に書かれた作品だとは想えない。しかも、この作品の後、1973年のピンボールという名作が出されるのだから、ため息。ただ、やはり他の多くの場合と同じく、処女作が最高傑作か?『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』は別格として、その後の村上の作品に、この二冊を超える質を感じたことがない。



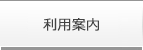
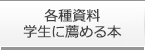

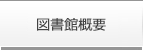





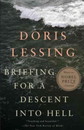


















走ることをモチーフにした小説としては、やはりなんといってもアラン・シリトーの『長距離走者の孤独』である。読んだのは、たしか中学生の時だったと思う。作品の世界に入り込むことができた。あれからうん十年、月日の経つのは早い。学校の体育の時間という苦行から解放されて以来、あえて走るという行為を行うことは、まったくもってなくなってしまった。電車に遅れそうになって走ることはあったけれども、それは決して、魂を何かから解放するための行いではなかった。しかも、遅れたら遅れたでかまわないと、日常世界のコードにこだわらない生活を送ってしまえば、非日常の世界に入り込むために走るということからますます遠ざかってしまう。走ることが歩くことの延長線上にあって、しかも歩くことから走ることに移行するのは何かの一線を超えることであって、日常生活の空間に突然ぽっかりと開いた別の世界に入り込んでいくことにさえなるかもしれないと、そう想像できるようになるためには、小説やエッセイの力を借りるしかない。『長距離走者の孤独』からうん十年、3冊紹介してみたい。
森絵都はすばらしい。彼女は児童向きとヤングアダルト向きと純正アダルト向きという、三つの世界を一つにしてしまった。まるで本の年齢別という領域の垣根を取り払って、子供から大人まで誰でも楽しめる大きな空き地を作ってしまったようだ。本書『ラン』では、自転車モナミ1号が光の道を"向こう"の世界に向かって走りぬけてゆく。でも、いろいろあって、主人公は自分の足で走ることを決心する。ドコロさんはじめ仲間たちのいきいきとしたキャラ設定がとてもいい。紙面がブラウン管になってしまったようだ。ひとりひとり何かを抱えたド素人ランナーたちの息づかいが、はっきりと聞こえてくる。
あさのあつこの『ランナー』は、ヒット作品『バッテリー』の陸上版。でも、長距離走者が抱えて走る重たいものの一例を、おもわず目頭抑えてしまう物語の展開の中で、はっきりと胸元にかざしてありありとみせてくれる。野球のピッチャーと長距離走者は、あさのあつこの世界ではかなり似ているようだ。読んで納得。ヤングアダルトものが龍だ魔法だの奇々怪々オカルトものばかりになってしまった昨今、彼女にはがんばって欲しい。
最後に村上春樹のエッセイ。彼自身の、走ることについてのパーソナルな歴史について書かれた本。しかし、彼自身による作品論も散見され、ファンには必読の書といえそう。もちろん、ファンならずとも、読んでいて引き込まれる。走ることのつらさが、紙面から湯気を立てて読み手に伝わってくる。この本を読んで、村上春樹の海外での優雅な生活に、売れっ子小説家の華やかさを読み取る向きもあるかもしれない。けれども、本書には一語も書かれてはいないが、売れっ子小説家の抱えるプレッシャーの重さは、読者には計り知れないものがあるのではないか。下手なものは書けない。好きなものだけ書いているわけにもいかない。走ることのつらさは書くことのプレッシャーと同じだけの負荷を身体に与えるのかもしれない。でも、走ることは書くことと同じで、こころを何か重たく臭くべちゃべちゃとげとげしたものから、すっきりと解放してくれることもある。そんなことを想像しながら読み進めることができた。