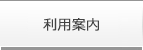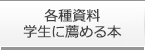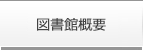図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2005年版
臼井 陽一郎
『魔の山』
- トーマス・マン 岩波文庫 1988.10
2004年夏、久しぶりに、すべての仕事を忘れて引き込まれた。遅々として進まぬ研究の焦りも、大学の鬱蒼とした雑務の苛々も、すべて忘れさせてくれた。とにかく、そのエンディングである。ブラウン管に躍動する落合ドラゴンズの大活躍に忘れられ、まっくろに焦げてしまったフライパンの餃子の名残のように、私的心象世界に焼きついてしまった。100円ショップで買った高級めらみん研磨スポンジをしても、取り去ることのできない焦げあとである。8年前大学着任当時に経験した新潟の嵐の霰のように、完全なるニヒリズムの言語的暴力にすぎない討論的口論がセテムブリーニとナフタに闘わされ、サナトリウムを一歩出ればその妖しき性の魅力がすべて吹き飛んでしまうクラウディアのそそられる残酷さや、人物なることばの現実の本質がとりまきのたんなる幼稚さにすぎないことをはっきりと目の前に突きつけてくれるペーペルコルンの破壊的形象や、軍隊の規律と名誉に人生のすべての意味を見出そうとするヨーアヒムへの悲しきいとおしさや、、、。サナトリウムがひとつの確固とした有機体としてその存在をたしかに主張し、18リットル灯油缶二缶を同時にもってマンションのベランダに運ぶときのように、その重さをずっしりと読者に感じさせてくれるトーマス・マンの筆の力は、タマモクロスに挑んでいったオグリキャップのように、ドストエフスキーに迫っている。とにかく、エンディングである。まったく予想できなかった。リンデンバウムの歌を口ずさみつつ、ひたすらに黙々と第一次大戦の前線の戦野を歩み進むハンス・カストルプに、いったいなんの象徴を感じればよいだろうか。欧州統合研究者への知的挑戦である。実は、結局落合ドラゴンズの優勝を見届けられぬまま夏の海外出張に旅立ってしまった。帰国後、涙なしに語れない大学行政の悲しき楽しさに時を奪われ、結局エンディングを読み終えたのは、サンタクロースのバンドが拡声器でクリスマス・ソングを歌いねりあるくスキポール空港で、ラージ・サイズのハイネケンを飲み終えたときであった。
『雪国』
- 川端康成 新潮文庫 1987
2004年冬、他大学とのゼミ合同合宿で、湯沢に行った。足湯をたしなみに湯の町を歩き、ひょっとしたことで川端記念館的な建物にはいった。ノーベル賞に何の特別な意味も与えないようなその平凡にすぎるコンクリートの建物には、好感すら感じられる。で、中で学生に聞かれた。「先生、川端康成って、どんな印象をもってますか。」応えられなかった。だって、読んでなかったから。。。帰宅するやいなや、すぐ手に取ったのはいうまでもない。うつくしい文章、それに尽きる。ただそれだけの書物である。越後は湯沢が主な舞台であるが、そこに生きる人の生(なま)の姿は何もない。そこに流れてきた女二人と、そこに遊びにきた男一人、生(なま)の人の姿はただこれだけ。越後はここでただのキャンバスにすぎない。しかし、とにかくうつくしい。このうつくしさは、モネだって描けるわけはない。それだけに、物語の前提となる当時の日本の社会構造が、びっしょりとした雨に濡れたウールのコートのように、気持ちを重たく圧しつぶそうとする。しかし、それにしてもうつくしい文章である。志賀直哉を楽に越える水準である。東京は府中の上がり3ハロンで、ミスターシービーがけっして抜くことのできなかったシンボリルドルフのように、圧倒的なうつくしさである。鉄の構造に規定された社会と人の本質を抉り出し、その直接の表象を読者の心象世界に再構築するするという、小説に期待したい役割がほとんど幼稚なほど軽くあしらわれている、それでも、夏目雅子の域にも達するほどのうつくしさが、日本語によって可能になるという日本語スピーカーとしてのうれしさ、それを実感させてくれる書物である。