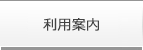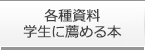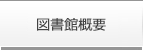図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2007年版
臼井 陽一郎
『真知子』
- 野上弥生子 新潮文庫 1966年
すべてが最後の一頁の、さらにその中のほんの一行のために書かれた物語だ。そんな気がしてならない。これは単純に美しい恋愛小説である。決して社会は思想小説として読んではいけない。なお、著者に文章がうまいといったら、お世辞どころか、嫌みになる。野上弥生子の他の作品と比べて、なにゆえこれほどのギャップが生じているのか、理解に苦しむ。真知子の描き方など、単純きわまりない。これほど分かりやすい人物など、女性の裸がグラビアにすり込まれた週刊誌の連載小説以外、なかなかお目にかかる機会はない。高貴なるはずの金持ち階級のおばさまたちの描き方も、そこには人間が存在していない。ただの戯画だ。無産運動を繰り広げる労働者の味方たちだって、ロボコンに出場するロボットたちほどの人間味も感じられない。単純だ。破壊的な単純さだ。ことばを交わし合う際に戯画的ならざるをえない弱き人間も、そのこころの奥底には、さまざまな悩みがあるはずだ。ただ、にもかかわらず、たった一人の人物の描かれ方と、人間性の複雑さを暴力的に平均化して描かれた人物たちの周辺の空間や事物や時の経過の美しき描写は、実に同じ方法で、見事な筆の力を実証している。背景に沈んだ人物と周辺の描写が、その者や物事の、思わず暖かく引き込まれるやさしい炎色を醸し出している。河合という人物像は、彼女ならではの筆致によってはじめて、うつくしさを獲得できるのではないか。ただ、真知子の単純な描かれ方は、迷いながらもまた弱さをさらけ出しながらも、芯のぶれない強さをどこからか与えられた魅力的な女性像の存在を可能にしている。真知子に嫌われる人間であることに自己嫌悪した読者は、少なくないはずだ。
『秀吉と利休(改版)』
- 野上弥生子 新潮文庫 1992年
質の良い小説にはいくつか条件がある。自分勝手な空想的押しつけではあるが、自分なりに大切にしたいと思っている。第一に、脇役の挿話的なストーリーに引き込まれること、またそのストーリーがメインの登場人物のストーリーに現実的に絡み合いながらも空想的にはそこから解放されていくこと。第二に、情景描写が人物のこころもようの変化と対応していること、もしくは、情景描写を通じて人物のこころもようの変化を読み取れること。そして第三に、人物のこころの襞の瞬間的で微妙な移り変わりが美しい言語を通じて青空に映える鎌倉の紅葉のように浮かび上がってくること。野上弥生子の秀吉と利休は、この三つのすべてにおいて最高点を付けられる。ぼくにとっては、絶対の傑作である。利休の息子と、利休の妻の兄の女の物語は、桃山時代の堺の悲劇的なインターナショナルの雰囲気を、官能的な美しさで彩っている。
『中欧の分裂と統合―マサリクとチェコスロヴァキア建国』
- 林忠行 中公新書 1993年
チェコスロバキア建国の立役者マサリクとその右腕ベネシュが、その人生を通して敢行しようとした仕事は、ハプスブルク末期のチェコ人たちの絶望的な冒険を象徴しているのだろう。その悲劇は、21世紀の欧州にも引き継がれていくだろうか。それとも、マサリクのぎりぎりのレトリックで描き出された夢と構想が、現実のものとなってゆくのだろうか。「マサリクは将来の国際関係についてつぎのように説明する。歴史は統合の過程であると同時に、分解の過程でもあり、組織化された多様性へと歴史は向かっている。すなわち、ヨーロッパは民族国家へと分解する一方で、それらを単位とする連邦を形成しつつある。そしてつぎのように続ける。『主権は相対的であります。なぜならあらゆる民族の経済的、文化的相互依存は拡大しているからです。ヨーロッパはますます連邦化され、機構化されています。この所与の状況と発展のなかで小民族は、成長しつつあるヨーロッパ機構へ平和な手段で加入する権利を要求しているのであります』。」(151ページ)。欧州統合とEUの研究者にとって、これほどこころをびりびりしびれさせてくれることばは、そうそう存在しない。EUの東方拡大がどれほどの歴史的偉業なのか。マサリクとベネシュの冒険を、チェコ軍団のシベリア横断を、パリやロンドンや東京やワシントンでの政治の駆け引きを、映画監督のつもりで、もしくは次回作を企画するシナリオ・ライターの感覚で、タバコの煙を煙らせながら想像してはじめて、EUの東方拡大の熱さを肌で感じることができる。現代物を勉強している研究者にとって、すぐれた歴史物は肌感覚を鋭くしてくれる。とても貴重な業績だ。これほどの筆の力をもって本を書けるようになるには、やはり対象に惚れ込まないといけないのかもしれない。
『遠い山なみの光』
- カズオ・イシグロ ハヤカワepi文庫 2001年
雰囲気を描ける書き手は、なかなかいない。もちろん、物語にとって大切なのは、人物像と話の展開である。魅力的な人物を飽きのこない話の展開で書き込んでいく小説こそ、売れ筋に乗ること間違いない。けれども、周辺の風景が登場人物とともに醸し出す雰囲気もまた、良質な物語の条件だと思う。
カズオ・イシグロの描き出す世界は、この雰囲気に魅力がある。回想が幾重にも織り込まれる独白と会話の双方には、彼の筆の力によって初めて可能であるかのような、独特の時制の用法がある。それによって、彼の描く雰囲気に浸る読者は、自らの帰るべき場所にあるような優しさと穏やかさに包まれていく。が、しかしその暖かな炎色の雰囲気の世界で、絶望的な悲劇の進行を直視させられる。終戦直後の長崎と女性と自殺、この三つの単語を並べれば、怒りの矛先の曖昧ならざるをえない情景を容易に想像できるかもしれない。
ただ、本書は英語で書かれ、英国で出版された。彼は英国の読者にどのような読みを願ったのだろうか。5歳で渡英し、以来日本語と別れ、英国で物語の書き手になっていった彼にとって、日本はいつもそこにあるとともに、こちらとそこの間には分厚い強化曇り硝子が立てられているに違いない。なお、彼の作品の日本語訳の中では、おそらくこれが卓抜の出来だといえそうだ。
カズオ・イシグロの描き出す世界は、この雰囲気に魅力がある。回想が幾重にも織り込まれる独白と会話の双方には、彼の筆の力によって初めて可能であるかのような、独特の時制の用法がある。それによって、彼の描く雰囲気に浸る読者は、自らの帰るべき場所にあるような優しさと穏やかさに包まれていく。が、しかしその暖かな炎色の雰囲気の世界で、絶望的な悲劇の進行を直視させられる。終戦直後の長崎と女性と自殺、この三つの単語を並べれば、怒りの矛先の曖昧ならざるをえない情景を容易に想像できるかもしれない。
ただ、本書は英語で書かれ、英国で出版された。彼は英国の読者にどのような読みを願ったのだろうか。5歳で渡英し、以来日本語と別れ、英国で物語の書き手になっていった彼にとって、日本はいつもそこにあるとともに、こちらとそこの間には分厚い強化曇り硝子が立てられているに違いない。なお、彼の作品の日本語訳の中では、おそらくこれが卓抜の出来だといえそうだ。