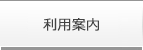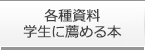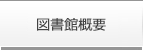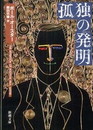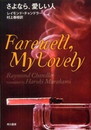図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2011年版
臼井 陽一郎
『ブラフマンの埋葬』
- 小川洋子著 講談社 2004年
さまざまな芸術家を受け入れる創作者の家が舞台。その家でお世話係を務める主人公が、小動物のブラフマンと出会い、別れを迎えるまでの短い時を描いた作品。創作者の家は、古代墓地の近くにあった。遺跡の石棺が数多く残され、いずれにも死者を悼みその記録を残す美しいことばが彫られていた。たとえば、父の慈しみと母の優しさだけを与えられた赤子、といった感じで。石棺にことばを彫る仕事はいまに受け継がれていて、主人公が創作者の家で出会った唯一の友がその仕事を続けていた。死者の永遠の居場所となる石棺は、詩のことばの本来のあるべき場所であるかのようだった。死と芸術を見守る孤独がとにかく美しく描かれていた。名作。
『真剣師小池重明』幻冬舎アウトロー文庫
- 団鬼六著 幻冬舎 2007年
賭け将棋を生業とする真剣師の生涯を描いたノンフィクション。アマ名人に2年連続で輝き、プロ棋士を負かしまくって、将棋界に旋風を引き起こした伝説の男は、やがて何度も詐欺に手を染め、駆け落ちした人妻にも逃げられ、どん底に落ちてゆく。人生について、人間について、もっと深く知りたいと思ったとき、最良の一冊。
『海の上のピアニスト』白水社Uブックス
- アレッサンドロ・バリッコ著 白水社 2007年
大型客船のダンスホールに置かれたピアノ、その上に赤子が捨てられていた。赤子はやがて、希代のピアニストに育っていく。彼は生涯一度も、その船を下りて、陸地に足を踏み入れることがなかった。しかしその人生を通じて、海を旅するさまざまな人々の話を聞き、その一人ひとりの人間を通じて、陸の世界を映像のように想像してゆく能力を備えていった。唯一の親友のトランペット吹きの語りで彼の物語が展開していき、やがてラストシーンでピアニストの独白がはじまり、物語の幕が閉じられる。彼は一度、陸地から海を眺めてみたいと思い立ち、船を離れようと決意するが、タラップの三段目で、思い返し、船に戻ってしまう。彼が畏れたもの、封印したもの、別れを告げたものが何であったのか。彼の独白は、人間存在の意味について、深く考えていくためのすばらしいヒントに充ちている。彼は言う、ピアノは88の鍵盤に限定されていて、その先は存在しない、でも、その限定された世界で、人は音楽を無限に奏でることができる。リアリズム・ファンタジーの美しい作品。
『オラクル・ナイト』
- ポール・オースター著 新潮社 2010年
いくつもの悲劇の物語が重層的に展開する。主人公は小説家。死の淵から奇跡的に生還し、偶然出会った不思議な文具店でポルトガル製の青ノートを手に入れ、小説家としての再起をかけてあらたな執筆を始める。題名のオラクル・ナイトは、その主人公の再起をかけた小説の小説内物語。激しい性と暴力が展開するのに、場面毎の描写がとにかく美しい。憎しみの塊の暴力が場合によってはある種の救いをもたらしうる奇跡について、きわめて示唆的なラストシーンが忘れられない。ブラームスの弦楽四重奏曲のような濃密な美しさ漂う作品。
『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』 (村上春樹全作品 : 1979-1989 ; 4巻)
- 村上春樹著 講談社 1990年
二つの世界の物語が同時平行で進行する。情報を守るための計算士の組織(システム)と情報を盗むための記号士の工場(ファクトリー)が相争う世界がひとつ、もうひとつは自分の影を切り離されこころを消滅させられてしまう壁に囲まれた世界。実は壁の世界は主人公である計算士の表層意識の下層深くに存在する世界だった。彼はその世界で一角獣の頭骨に指を這わせ、古い夢を読み続ける。計算士と記号士が争う世界では、天才老人科学者とその娘の太めでピンクの似合う17歳の娘、夫がバスで若者に鉄瓶で殴られ死んでしまった図書館司書の女性、地下深く生息する憎悪の固まり・ヤミクロなどなど、まさにワンダーランドが展開する。こころを消されてしまう壁の世界では、刃物を研ぎ死んだ一角獣の頭を切り落とすのを生業とする大男の門番、母の唄の痕跡をかすかに感じる夢読み手伝いの女の子、影を切り捨てこころを消滅させることを老いて決意したかつての兵士・大佐、影を捨てきれずまたこころを追いかけもしない中途半端な存在の発電所の若者などなど、こころの消滅した世界の終わりが美しく描かれる。意識下の物語の生成に身をゆだねる作家の内的生活を描いているかのようであり、またアイデンティティ(もしくは宿命論的な自己承認)の物語でもあり、SF的なファンタジーの色彩が作品に忘れられない魅力を与えている。
『羊をめぐる冒険』(村上春樹全作品 : 1979-1989 ; 2巻),
- 村上春樹著 講談社 1990年
友人の<鼠>と羊の写真をめぐって、奇跡の美しき耳をもつコールガールの彼女と主人公の<僕>が、北海道を舞台に、冒険の旅に出る。自分を失って資本主義システムの甘い暴力にとらわれてしまい、意識の暗黒の領域に引きずり込まれてしまうことに対する抵抗戦が、いろんなメタファーをちりばめられながら、ファンタジーの色彩たっぷりに描出される。名作。
『ダンスダンスダンス』(村上春樹全作品 : 1979-1989 ; 7巻),
- 村上春樹著 講談社 1991年
高度資本主義社会のなかで自分を大切に保ち生き続けるためのサバイバル物語。主人公の<僕>は、この同時代からの退出一歩手前で踏みとどまっていた(暗闇の壁のその向こうへの消滅、もしくは死)。その孤独で静かな自分自身のなかでぎりぎりの闘いを戦うまさにそのとき、かつて訪れた札幌のいるかホテルで、誰かが<僕>のために泣いている夢を、何度も何度も見る。高度資本主義社会のフィールドに掘った安全地帯の井戸、そこに引きこもった状態から、<僕>は這い出し、札幌のいるかホテルに向かう。しかし、いるかホテルはいまや、高度資本主義社会を象徴具現するような、超高級ドルフィンホテルに変貌していた。そこから不思議な出会いの連鎖が始まる。コールガールのキキとメイ、パーフェクトなアイドル俳優の五反田君、羊男、13歳の美少女ユキとその母アメ、アメの助手兼愛人の片腕の白人男、そしてドルフィンホテルで働くユミヨシさん。バブル直前の80年代日本社会の腐った豊かさが、生と死をめぐるメタファーに変換され、舞台はハワイにまで飛ぶ。異常な家庭環境を背負う13歳の少女ユキに対して、主人公の<僕>が語りかけることばが、澄んだ青空に響く鐘のように、透明で素晴らしい。また、自我が100%の暗闇の壁の向こうに消滅してしまわないように、ダンスのステップを踏み続けていなければいけないという羊男のメッセージが、心に残る。
『ティンブクトゥ』
- ポール・オースター著 新潮社 2006年
詩人を主人にもった犬の物語。犬の彼、ミスター・ボーンズは、英語を解することができる。主人の詩人は、ナチス時代のポーランドから脱出した両親をもち、アメリカで生まれ育った。やがて精神が崩壊、テレビに映ったサンタクロースの啓示を受け、クリスマスと名乗りはじめ、ミスター・ボーンズとともに、慈善のための放浪の旅に出る。詩人クリスマスは、膨大な詩を書き残し、駅のコインロッカーに放置したままだった。その詩人、ミスター・ボーンズにみずから発見した約束の地ティンブクトゥについて、熱く熱く語っていた。主人亡き後、ミスター・ボーンズは、主人を回想しながら、ティンブクトゥで主人と再会できる日を夢見つつ、生きるための冒険を続けていく。ミスター・ボーンズは、ティンブクトゥにたどり着けるだろうか。カルフォルニアの高速道路のラスト・シーン、光りの洪水が忘れられない。
『人のセックスを笑うな』
- 山崎ナオコーラ著 新潮社 2004年
美術専門学校生の19歳男子がスクリーンになって、その学校の美術講師・既婚39歳・女性の心理や生理の断面が映し出される。どろどろした不倫ものとは分けが違う。この媒体としての男の子、設定キャラがいわゆるオトコ的でなく、純粋にオンナ的でもない。双方の特徴を見せながら、どちらでもない。ニュートラルというのとも違う。不思議な透明感が感じられる。それなりに悩み傷つき感傷的になって涙を流すのだけれど、愛欲の慟哭など皆無。山崎豊子も三浦綾子もぜったいに描くことのなかった男子像であるように想う。恋愛も生活も自然も、すべてひたすら感じるだけの存在(そこには思惟の跡らしきものが一切見られない)。自己の才能に幻滅した美術講師のつかの間の逃げ場としての遊び的恋愛ゲームに、致命的なダメージを受けてしまうこともない。こうした構図がさらりと流れる透明な文体で描かれていく。不思議な魅力が感じられる作品。
『ムーン・パレス』
- ポール・オースター著 新潮社 1997年
叔父・祖父・父親三人それぞれの人生物語が、主人公の青年を通じて語られていく。その青年、精神の彷徨に迷い、道を見失っていた。偏狭な自我に縛られ身動きできなくなってしまった青年の生のあがきが、痛いほど紙面から伝わってくる。この苦悩のまっただ中に生きる青年を通じて語られていく叔父・祖父・父親それぞれの数奇な人生物語の切なさは、人生に彷徨い足掻く青年をスクリーンとすることによって、数倍にも増幅され、読者のこころに響いてくる。彼につかの間の生の充実を贈ってくれた中国人の恋人の強さとかわいさが、作品の魅力をさらにいっそう引き立てる。オースター十八番の物語内物語の連鎖が、本作でもたまらなく魅力的である。物語のなかでいくつもの物語を反響させていく手法、ほんとうにすばらしい。
『孤独の発明』
- ポール・オースター著 新潮社 1996年
300頁あまりの文庫本に、いくつもの珠玉の物語が折り込まれた作品。自伝的体裁を取ったフィクションのようであり、フィクションに隠した自伝的実話のようでもある。二部構成で、前半は父の姿が描かれる。これは孤独それ自体の純粋な像の描写。後半はAと呼ばれる人物の記憶の書。これは記号化された書き手本人の半生の記録。Aはやがて小説の書き手として飛躍していく。随所に展開される物語論が素晴らしい。たとえば、<小説に描かれた人生>と<実人生を記録した書>を分け隔てるものは何かという問いの鋭さ。Aが独白する鋭利な考察に魅了された。
『 夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 』
- 村上春樹著 文藝春秋 2010年
村上春樹のインタビュー集。彼の物語創作技術論であり、物語論そのものでもある。両者がセットになった論攷集のような発言記録。ところどころちりばめられる他の作家への言及も魅力的。カーヴァーやフィッツジェラルドやサリンジャーといった村上の定番はもちろん、トマス・ピンチョンやカズオ・イシグロを評価した一言の深さは、ほんとうにすばらしいと想う。高性能掘削機で一瞬のうちに掘り終えた深い深い井戸のよう。インタビュアーの問いかけに対する彼の真摯に回答しようとする姿勢も、強く印象に残る。ちなみに最初の読者・かみさんに書き直しなさいといわれケンカになったこともあるらしい。まさにファン必見(必読)の書。
『神様のカルテ2』
- 夏川草介著 小学館 2010年
魅力あふれるキャラたちが今回もまた抜群の味を出す。新キャラも登場。地方の医療の凄惨な現場で、うつくしくじーんとくるシーンがいくつもちりばめられる。ゆるキャラの現代的な英雄が、いのちの最前線でどこまでも人間をいつくしむ物語。読み終えたあと、夜空に星を探そうと外へ出て上を見上げたくなる。それから、日本酒が恋しくなる。主人公のイチさんと友人の男爵が酒を酌み交わすシーンがたまらない。
『幽霊たち』
- ポール・オースター著 新潮社 1989年
ニューヨークを舞台にした探偵物語。しかしドラマチックな展開はない。探偵が追跡するのは本を読んでものを書く男で、その平凡な変化のない生活には、一切の事件性が認められない。バイオレンスシーンはもちろん、ラブロマンスもない。奇想天外な冒険的展開など、さらさらない。にもかかわらず、平凡な変化のない生活をおくる男を見張る男のモノローグに、いくつもの物語が織り込まれ、その一つひとつに引き込まれていく。意味を求めて生きることのむなしさが、底なし沼に落ち込んでいくように追体験できる一方で、探偵が語るかつて観た映画の脇役の盲目の少年のカッコ良さが、こころに火を灯してくれる。
『原稿零枚日記』
- 小川洋子著 集英社 2010年
女流作家の日記。生と死の、こちらとあちらの二つの世界を取り結ぶ物語が、日記を通して現れてくる。それは彼女が抱えるとってもしんどいものがだんだんと明るみに出されていくプロセスでもあって、読み進めるうちに胸が締め付けられていく。日常の中の非日常をファンタスティックに描き出すスタイルは、この作品でもずばぬけてすばらしい。彼女の濃密でいて軽くところどころ大胆に官能的な文体は、現代作家の中でも指折りのものだと想う。生の向こう側の世界への入り口を空気の隙間に見つけ出す微細な筆使い、なんともすばらしい。
『シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々』
- ジェレミー・マーサー著 河出書房新社 2010年
問題を起こして国を逃げ出したカナダの犯罪記者が、逃避行先のパリであてもなくセーヌ河畔をさまよい、金も尽きかけ、精神も限界に近づいたとき、偶然、その書店に辿り着いた。その書店、いたるところにベッドがあり、奇妙な人々が住み着いていた。詩人や小説家やその他さまざまな夢見る芸術家たちが、その書店に巣食って、明日を夢見ていた。店主のジョージはすでに86歳、鉄の意志とどこまでも人間を愛する無限のハートを持った永遠のコミュニストで、若い頃から世界中をナップサックひとつで歩き回ってきた。いまだに20歳の女の子に本気で恋をしてプロポーズしてしまうすごい男。日曜日ごとのパンケーキのお茶会で繰り広げられる人間模様、詩人や小説家の朗読会、赤貧の若者たちのパリの街でのサバイバル術、書店の住人に恋をしてパンを届けるようになったデンマーク大使館の女コック、アナイス・ニンと店主ジョージの妖しいカンケイ、そのジョージの奔放な生き方と人を見抜く眼、5年もの間この書店に寄生しすでに50歳を超えた詩人が詩の本場アイルランドの田舎町に招待され朗読会を開き一躍注目されていくサクセスストーリー、そしてそんな書店の様子のレポーターとなって読者にさまざまな現場を報告してくれるカナダの犯罪記者の、人間性の再生。辛いのや酸っぱいのや甘いもの、シリアスものからコメディものまで、いくつものすばらしい物語がモーツアルトのシンフォニーのようにうつくしい組曲となって読者に癒しの時を与えてくれる。一家に一台、人生に一冊、そんな傑作だった。
『幻影の書』
- ポール・オースター著 新潮社 2008年
飛行機事故で妻と子を失い絶望の淵に追いやられた男、謎の失踪を遂げた無声映画のディレクター兼アクター、その彼を愛する女たち、絶望の暗闇に微かに滲む再生の光、ニューメキシコ州の砂漠に立てられた撮影所、誰にも見せず死後廃棄することを条件に撮影された作品たち、絶望の淵に立った男の前に現れ、その作品たちを見せようとする女、その女は美しかった、顔の半分を覆う青痣さえ目に入らなければ。ひとつの物語がいくつもの物語から創り上げられていく。男が翻訳しようとするフランス人の人生記、謎の失踪を遂げた男の手による映画の物語、絶望の男が分析し解釈するその映画の世界、映画を撮った男をめぐる人々ひとり一人の人生。すべてが縫い目なしの一枚の絹の絨毯のようで、美しい。こころの痛みの激しくなる場面がファンタスティックに描かれる。現代文学の最高峰に位置する作品。
『さよなら、愛しい人』
- レイモンド・チャンドラー著村上春樹訳 早川書房 2009年
私立探偵フィリップ・マーロウのハードボイルドなやさしさがカッコいい。彼のまなざしに映るアメリカは、いつもながら腐臭すら感じられる真っ黒な重たい影に覆われている。でも、彼の行く先にはかならず、まだまだ捨てたもんじゃないヤツが現れてくる。そんなときのマーロウとのトークのやりとりが、たまらなくカッコいい。マーロウのシニカルで斜に構えた態度の奥底にある熱さには、こだわりをもって人生を生き抜いていくことの尊さが感じられる。どうしようもなくしぼんだ皺だらけの汚れた世界となんとか折り合いを付けて人生を過ごしていかなければいけない多くの人々にとって、そんな世界と対峙するマーロウの構え方は、人生の意味の確かさを手にとって熱く感じられるように示してくれている。村上春樹の訳がすばらしい。
『ガラスの街』
- ポール・オースター 新潮社 2009年
都市の迷路に入り込み、私立探偵を演じるハメになり、やがて迷路から逃れられなくなってしまった男の物語。自己のアイデンティティを意識するときの、高波のような激しいゆれ、ニューヨークの街並みと一体化した底辺の人々に向けられるまなざし。先へ先へとひっぱっていくストーリー展開のおもしろさとともに、人の意識の流れが混濁していくことの怖さに魅了される作品であった。重厚なテーマを軽いタッチで描き出す、卓越した筆使いがすばらしい。
『同時代ゲーム』
- 大江健三郎著 新潮社 1979年
現代という時代にあっても、文学が<神話>を構築しうることを証明した作品。この神話、兄が双子の妹に宛てた書簡形式で紡がれていく。四国の山奥の、周囲から隔絶された小共同体が舞台。時の権力からの独立をどこまでも追求するこの共同体は、最後は大日本帝国と一戦交えるまでにいたる。<壊す人>が率い開拓したこの小宇宙では、<壊す人>の命と意志がどこまでも貫かれていく。人間が共同体を生きることのリアルな姿が、ときにファンタジーな感じを織り込みながらも、重厚なタッチで描き出されていく。日本文学のひとつの到達点。
『猫を抱いて象と泳ぐ』
- 小川洋子著 文藝春秋 2009年
指し手どうしで詩を紡ぐチェスのすばらしい対話の世界を詩のことばで幻想的に美しく描き出した作品。主人公は自分の世界に閉じこもり安住しようとしながらチェスの世界で無限に羽ばたき冒険を繰り返す。死闘ではなく詩の共同創作が彼のテーマ。成長することを拒否した彼は、リトル・アリョーヒンと呼ばれ、リトル・アリョーヒンという名の人形に入って操作して、決して人前に姿をさらし出すことなく、チェスの棋譜という盤上の詩を織りなしてゆく。地上に降りられなくなった象インディア、壁からでられなくなった少女ミイラ、そして甘い菓子の大好きなバスの住人マスターとともに、リトル・アリョーヒンはチェスの無限の大海を旅してゆく。ラストのすばらしさは人生の大切な記憶として残り続けていきそうに思う。本当にすばらしい小説に出会うことができた。
『ハーモニー』ハヤカワSFシリーズJコレクション
- 伊藤計劃著 早川書房 2008年
パーフェクトな世界がついに訪れようとしていた。医療技術の進歩は人の身体にデータベースとつながったとある仕組みをインストールしてあらゆる病・疾患・痛みから人間の身体を解放することに成功、この技術はやがて人の意識の操作にまで及ぼうとしていた。しかし、その果てにあるのものは? すでに病床にあったのか、その直前であったのか。著者・伊藤計劃の筆は身体的にも精神的にも人間をいたぶり続けてきた痛みというやつを、生の証として見事に描き出していた。SFというジャンルの可能性をどこまでも開拓していく貴重な書き手はもはや失われてしまっているのだが、本書が残された意義は大きい。意識と意志の存在をどう理解するかは人間の存在の意味を問う問いに深くかかわる。そうした本書のテーマの存在論上の意義が、エンターテイメント小説としてのすばらしさと見事に違和感なく同居している。まさに希有な作品。
『虐殺器官』ハヤカワ文庫
- 伊藤計劃著 早川書房 2010年
SFという文学フィールドのもつ大きな可能性をパーフェクトに示した作品。意識と存在を明確に分け隔てることのできない曖昧な領域、これをどう描くかは文学的クオリティを左右する大切なチェックポイントだと思う。この作品、これが実に見事。どこまでが自分という存在で、どこからが自分ではない存在なのか、自己意識の境界の不分明なる部分に直面して抱く不安の深さ。主人公の問いかけは、生命についての倫理的難問に激烈な痛みをともなってコミットしていく。社会的必要性から人の生命を絶ちきることを強いられた人間の絶望的な贖罪願望。主人公のこころの煩悶を描き出す著者の筆の切れ味は、永久に融けることなき氷の断片のよう。巻末の解説は著者・伊藤計劃の人生についてのたんたんとした事実報告。このすごい作家、もはやこの世に存在しない。
『ロング・グッドバイ』ハヤカワ・ミステリ文庫
- レイモンド・チャンドラー著;村上春樹訳 早川書房 2010年
私立探偵物は、人間と社会をそのダークな本質部分からリアルに描き出していくのに、すぐれたジャンルだとおもう。しかもそこに決して柔なわけじゃない優しさの美学を学ぶことができる真正ハードボイルド物語が語られているとしたら、それはもう一生涯にわたって手元に置いておきたい書物となる。読み終えたその瞬間から、主人公フィリップ・マーロウがこころの中で生涯リアルに生き続ける存在になってしまった読者は、全世界できっと1万人はくだらないかもしれない。会話の一言一言が眼に焼き付いてくる。沈黙の瞬間の時の流れが100頁もの情報量をもって耳にささやきかけてくる。たばこと酒と、銃とナイフが人物の表情や身振りと一体になって、一つ一つの場面がもつ物語全体の中の大切な意味を生み出していく。まさに奇跡の筆だとおもう。そして、村上訳が冴える。
『ピストルズ』
- 阿部和重著 講談社 2010年
1200年の歴史の彼方より綿々と受け継がれてきた菖蒲家の秘技、秘伝の薬草による洗脳術、その歴代の継承者は男子であったが、今回、一子相伝の掟がやぶられる。ついに女子の継承者が登場する。しかも彼女あやめは、歴代にない飛び抜けた能力を発揮しはじめる。彼女の調合する香りは彼女の歌声と相乗し、意のままに人を操るが、その効果たるや師匠の父をも恐怖させるほどであった。著者・阿部のホームグラウンド、神町を舞台に、菖蒲家のメンバーとともに秘伝の洗脳術継承を強いられた一族の物語が綴られていく。菖蒲家のフラワーガーデンで繰り広げられるパーティーの優雅な模様、継承の過酷な修行シーン、神町の人々の集団暴力衝動、薬物に取り憑かれていく若者たち。菖蒲家と神町のサガ、これが町の本屋の主人と継承者あやめの姉あおばの二人の語り手によって、たんたんとしながらも大きなスケールで語られていく。ラストに意外な展開あり。洗脳によるコントロールというモチーフが主旋律、植物と人間の関係が重奏低音となって、雄大な物語が展開される。