図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2011年版
越智 敏夫
戦争文学とは何か。これはむずかしい。日本では『平家物語』などの軍記物までさかのぼるのも可能かもしれない。近代の反戦小説はどうだろう。従軍記のようなノンフィクションは戦争文学か。
戦争文学とはいえ文学。読んで面白くないといけない。人が極限状況に追いつめられ、殺されているいるのに、それがこれほど「面白い」とは。でもこの不謹慎さと文学の関係は重要な論点でもある。イデオロギーの左右、反戦と好戦、男女、年齢、国籍、侵略と被侵略、歓喜と受難、そうした著者や作品の属性とは関係なく、文学になっている「戦争」と、文学になっていない「戦争」がある。でも所詮は文学。戦争経験者は「本当はもっとむごい」と読みとばし、未経験者は「気分はもう戦争 (c)矢作、大友」と真剣になったふりして読みとばす。
と、おちゃらけてないで、安田武『定本 戦争文学論』(安田武復刻著作集、朝文社)などをまず読むべきなのかもしれない。けれどもこの1964年初版の本書を現在の大学生がどのように読むのかは若干気になるところ……と、いま思った瞬間に、自分もとことんおっさんになったなあと思ってしまった。
ということで鎮魂(大嘘)の5冊。
『戦艦大和ノ最期』講談社文芸文庫
- 吉田満著 講談社 1994年
永久に沈まない船などない。ましてや戦闘に参加する軍艦でそんなものがあるわけない。5歳の子どもでもわかる事実である。ところが「不沈戦艦」という表現をあからさまな欺瞞、矛盾にみちた真っ赤な嘘だと思わない時代と社会があった。大衆を操作するための悪意に満ちたその詐欺的手法は、詐欺をもくろんだエリート指導者たち自身の脳髄までも蝕み始めていた。その最果ての錯乱としての特攻。貴重な戦闘機とともに熟練した兵士をただひたすら虐殺するという愚かな行為(作戦とさえ言えない)をなぜ誰も止められなかったのか。その社会の末路の象徴としての戦艦大和。
だから大和の最期について書くことは戦前の日本社会の構造について書くことでもある。その意味で本書はノンフィクションではなく思想の書。鶴見俊輔が『戦時期日本の精神史』で指摘したように、本土を離れてからの艦橋はすさまじいまでのリベラルな空間となった。こうした空間が可能となった条件とはなにか。実社会においてなぜそれはいともたやすく不可能となるのか。そういえば、日本をアメリカ海軍の不沈空母にするぞぉ、と騒いだ政治家がいたなあ。好きなんでしょうねえ、この手の言葉が。
だから大和の最期について書くことは戦前の日本社会の構造について書くことでもある。その意味で本書はノンフィクションではなく思想の書。鶴見俊輔が『戦時期日本の精神史』で指摘したように、本土を離れてからの艦橋はすさまじいまでのリベラルな空間となった。こうした空間が可能となった条件とはなにか。実社会においてなぜそれはいともたやすく不可能となるのか。そういえば、日本をアメリカ海軍の不沈空母にするぞぉ、と騒いだ政治家がいたなあ。好きなんでしょうねえ、この手の言葉が。
『西部戦線異状なし』(改版), (新潮文庫)
- エーリッヒ・マリア・レマルク著 新潮社 2007年
ドイツ人学生パウルの手記の形をとるフィクション。第一次世界大戦が舞台。実際の戦争終結の10年後、1929年にドイツで出版されベストセラーとなるも、1933年にナチスが政権掌握。すでにスイスに逃げていた著者レマルクはドイツ市民権を剥奪されアメリカへ亡命。そのあいだにネタを探していたハリウッドが1930年に本作を映画化。監督ルイス・マイルストンは在米ロシア人。ドイツ文学をロシア人がアメリカで映画化。アメリカ人俳優(リュー・エアーズ、彼の人生もすごい)演じるドイツ人主人公がドイツなまりの英語をしゃべる。このあまりに多国籍な反戦映画を見る体験はちょっと変だけれど、僕の場合もそっちが先で、あとから小説読みました。
小説のほうの面白さは映画版より多彩な人物造形か。教え子を戦場に送りだすことに後ろめたさのかけらさえもたない教師。初年兵に意外な温情を示す戦場の古参兵とか。さすがに小説は描き方が深い(というかほんとに面白い)。ラストはとても映像的なので、ここは小説よりも映画のほうが良。
ちなみに今回ひさしぶりに本書を手にとって翻訳者が秦豊吉だったことに驚いた。帝劇社長、東宝社長、「額縁ショウ」発案者、丸木砂土、行動する異端、いろんな別名がある秦が訳していたとはなあ。知らなんだ。どうでもいいことですか。
小説のほうの面白さは映画版より多彩な人物造形か。教え子を戦場に送りだすことに後ろめたさのかけらさえもたない教師。初年兵に意外な温情を示す戦場の古参兵とか。さすがに小説は描き方が深い(というかほんとに面白い)。ラストはとても映像的なので、ここは小説よりも映画のほうが良。
ちなみに今回ひさしぶりに本書を手にとって翻訳者が秦豊吉だったことに驚いた。帝劇社長、東宝社長、「額縁ショウ」発案者、丸木砂土、行動する異端、いろんな別名がある秦が訳していたとはなあ。知らなんだ。どうでもいいことですか。
『真空地帯』
- 野間宏著 新潮社 1972
これも学生さんはどう読むかなあ。今、自分で読んでも、ある時代精神というか、単なる古さというか、そういう違和感は感じる。でも著者の経験をもとにしたフィクションとしてはよくできていると思う。軍隊という特殊な、けれども逆にその社会全体の病理が極端に現れる空間を舞台にした戦争文学。それも戦う兵隊ではなく、兵営内の内務班という単位に限定して描く。だからこれは戦場や戦闘が出てこない戦争文学。非日常下の日常生活。しかしながら、そこは世界に●たる日本軍。●●をやっつける前に味方の兵隊を半殺しにしつづける。ここは●●の●●●さえ届かない「真空」。こんな●●ではケロロ軍曹さえ●●のあまり、●●であります(各自、自由に●●を想像するように)。
ちなみに本作を映画化した山本薩夫監督自身も内務班でリンチにあっていたというのも有名な話。山本は戦闘がほとんど出てこない戦争映画として『暁の脱走』(原作は田村泰次郎『春婦伝』)も撮ってます。この山口淑子の演技がすごい。それを鈴木清順がリメイクしたものが『春婦伝』。こっちは野川由美子で、彼女の演技にもびっくりします。こちらもどうぞ。
ちなみに本作を映画化した山本薩夫監督自身も内務班でリンチにあっていたというのも有名な話。山本は戦闘がほとんど出てこない戦争映画として『暁の脱走』(原作は田村泰次郎『春婦伝』)も撮ってます。この山口淑子の演技がすごい。それを鈴木清順がリメイクしたものが『春婦伝』。こっちは野川由美子で、彼女の演技にもびっくりします。こちらもどうぞ。
『宇宙の戦士』ハヤカワ文庫
- ロバート・A・ハインライン著 早川書房 2010年
宇宙戦争ものの元祖。『機動戦士ガンダム』の元ネタのひとつ。
僕らの世代にとって本書の刊行は歴史的事件だった。とにかくその表紙。大学図書館ではカバーを捨てざるをえないのがつらいけれど、スタジオぬえ(正確には加藤直之?)デザインの強化服 powered suit がすばらしい。それを着装する機動歩兵 mobile infantry。これらの単語だけで、そのての世界観爆発。その概念を読者の想像力を(遥かにではなく)微妙に越えながら画像化したことが、あるジャンルのデザイン、世界観にパラダイムを提供し、ここからいろんなものが始まった……と言っていいのかなあ。
原著刊行も歴史的事件だった。主人公はアムロ・レイならぬジュアン・リコ。連邦軍に入隊した彼は苛酷な訓練や異星人との戦闘によって大きく成長していく。しかし1959年という冷戦まっただなかに発表された本作には「立派な兵士こそが立派な市民である」という世界観が強く打ち出されている。面白ければなんでもええのか、ということになって、この異常に面白い「好戦小説」はアメリカでも日本でも大論争の的となった(というより、今も継続中)。読めばわかるが、実は主人公が白人でない、というのもとても重要な気がする。こういうところがハインラインを単純な右翼作家にしてないところなんでしょうねえ。
ちなみに映画版 Starship Troopers はゴミなので言及する必要ない。バーホーベン監督の「お下品ネタ」としては面白いけれど。パワード・スーツも出ないし。そこが最低。
僕らの世代にとって本書の刊行は歴史的事件だった。とにかくその表紙。大学図書館ではカバーを捨てざるをえないのがつらいけれど、スタジオぬえ(正確には加藤直之?)デザインの強化服 powered suit がすばらしい。それを着装する機動歩兵 mobile infantry。これらの単語だけで、そのての世界観爆発。その概念を読者の想像力を(遥かにではなく)微妙に越えながら画像化したことが、あるジャンルのデザイン、世界観にパラダイムを提供し、ここからいろんなものが始まった……と言っていいのかなあ。
原著刊行も歴史的事件だった。主人公はアムロ・レイならぬジュアン・リコ。連邦軍に入隊した彼は苛酷な訓練や異星人との戦闘によって大きく成長していく。しかし1959年という冷戦まっただなかに発表された本作には「立派な兵士こそが立派な市民である」という世界観が強く打ち出されている。面白ければなんでもええのか、ということになって、この異常に面白い「好戦小説」はアメリカでも日本でも大論争の的となった(というより、今も継続中)。読めばわかるが、実は主人公が白人でない、というのもとても重要な気がする。こういうところがハインラインを単純な右翼作家にしてないところなんでしょうねえ。
ちなみに映画版 Starship Troopers はゴミなので言及する必要ない。バーホーベン監督の「お下品ネタ」としては面白いけれど。パワード・スーツも出ないし。そこが最低。



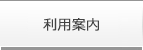
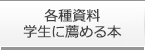

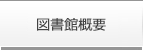




後半、主要登場人物が次々に非業の死を遂げ(月並みな表現だけどこう書くしかない)、海上の殺戮は敵味方のすべてを滅ぼすまで続くように思えてくる。にもかかわらず、読み進めるにつれて読み終わるのが惜しくなってくる。どうしてこんな話にこれほどまで引き込まれるのだろう。多くの絶賛書評もそれぞれ核心を突きそこねているような気もする。やはり「絶望」というところから読み解くべきではないか。論評する能力も根性もない私がこういうことを書いてもしょうがないけれど。
ちなみに、ファンのあいだで言われているように、原題の "H.M.S. Ulysses" を「女王陛下の……」と訳したことに問題はある。H.M.S. は His/Her Majesty's Ship の略で、「国王陛下または女王陛下の艦船」だから、単純に「英国軍艦ユリシーズ」あたりが正確なところ。まして第二次世界大戦期はジョージ6世の治世下。エリザベス2世は即位してないので「女王陛下の……」は完全に誤訳。しかし本書を読み終えたあと、なぜかこの邦題しかないと思うのも事実である。不思議だけど。