図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2008年版
臼井 陽一郎
『スプートニクの恋人』
- 村上春樹著 講談社 2001年
面白く読むことができたとおもう。『ノルウェーの森』と『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の双方のモチーフが実験的に織り込まれていた?そんな印象を持った。この作品、長編にもできたし、短編にまとめることもできた、そんな実験的な作品だったと想う。でも、そのどちらにもならなかった。そんな中途半端な作品でも、独立の生命を与えられた物語として、記憶にしっかり刷り込まれていく。
小説の書き方について悩みがでてくるところは、とても好感が持てた。『神のこども・・・』の中の短編にも、書くことの悩みが吐露される作品があったと思う。悩みを持たない作家は終わりだ。悩み続けながらその過程を嫌みなく作品に投影できる作家は一流だ。彼はやっぱり、その意味で一流だと想う。そんな一流作家の中途半端な実験的中編小説。のめり込んで楽しんでしまった。
スーパーマーケットの、スチールパイプ椅子が冷たく置かれた、万引き犯を問いつめるじめじめした暗い部屋の方が、ギリシャのとある島の夕闇時の港のそばのオープン・カフェよりも、はるかにこころに刻みつけられたのは、なぜだろう。
小説の書き方について悩みがでてくるところは、とても好感が持てた。『神のこども・・・』の中の短編にも、書くことの悩みが吐露される作品があったと思う。悩みを持たない作家は終わりだ。悩み続けながらその過程を嫌みなく作品に投影できる作家は一流だ。彼はやっぱり、その意味で一流だと想う。そんな一流作家の中途半端な実験的中編小説。のめり込んで楽しんでしまった。
スーパーマーケットの、スチールパイプ椅子が冷たく置かれた、万引き犯を問いつめるじめじめした暗い部屋の方が、ギリシャのとある島の夕闇時の港のそばのオープン・カフェよりも、はるかにこころに刻みつけられたのは、なぜだろう。
『自伝からはじめる70章 : 大切なことはすべて酒場から学んだ』
- 田村隆一著 思潮社 2005.1
まったりとした雰囲気に包まれる、そんな本だった。とにかく、お酒が飲みたくなる。全70章におよぶ本書のエッセイの中でも、とりわけ、人類の進化のはじまりを酒の発明に求めるエッセイを紹介するくだりなど、読んでいると、目の前にビールがおいてあったらそれが神々しく光り出す錯覚さえ覚えてしまう。
彼の詩の作品を右に開き、左に本書を開いて、どちらも田村隆一の名を隠しておいたら、いわゆるこの利き読みに成果を出せる読み手など、きっと存在しないに違いない。こんなにも異次元な世界を構築できる筆の使い手は、なかなか存在しないと思う。物書きの真骨頂は、雰囲気を醸し出すことにある。そんな自分自身の文章哲学をあらためて確認する一冊だった。
もしも疲れ切った身体を引きずる人がいたら、その人は糖尿のリスクと背中合わせにアリナミンEXプラスを飲むよりも、田村隆一のエッセイを手に取るべきだ。
彼の詩の作品を右に開き、左に本書を開いて、どちらも田村隆一の名を隠しておいたら、いわゆるこの利き読みに成果を出せる読み手など、きっと存在しないに違いない。こんなにも異次元な世界を構築できる筆の使い手は、なかなか存在しないと思う。物書きの真骨頂は、雰囲気を醸し出すことにある。そんな自分自身の文章哲学をあらためて確認する一冊だった。
もしも疲れ切った身体を引きずる人がいたら、その人は糖尿のリスクと背中合わせにアリナミンEXプラスを飲むよりも、田村隆一のエッセイを手に取るべきだ。
『ぼくの航海日誌』
- 田村隆一著 中央公論社 1991年
2時間かからないだろう、読み終えるのに。詩の形をとって、一人の人間の人生が表現されていた。アニメを使った良質のショート・フィルムといったところか。しかもアニメに利用されるイラストは、一級品だ。そんな印象をもった。
とにかく、押しつけがましいことばがひとつもない。どう考えても、どう想像しても、その舞台は車のワイパーがまったくきかない土砂降りの雨の中、どろどろになって次の一歩を踏み出すのに十代の体力が要求されるようなひどい気候の下なのに、マリ・クレールの連載というポップな雰囲気を作り出しながら、自分の人生を透明な影絵でもって表現してしまうのであり、しかもしっかりとアルコールは効いていて、詩作の意味まで問うてしまうのだから、この人はただ者ではない。
安部公房の作品のように、読む者がこころをがぶっと食われ、外科的な治療が必要になってしまうことはないのだけれど、彼のこの書き物は、身体全体にいつのまにか回ってしまうフルーティでコクのあるビターな飲み物であり、やみつきになってしまう。不思議だ。雪のつもる季節に鍋でもつつきながらこたつで読むのに最適だ。
とにかく、押しつけがましいことばがひとつもない。どう考えても、どう想像しても、その舞台は車のワイパーがまったくきかない土砂降りの雨の中、どろどろになって次の一歩を踏み出すのに十代の体力が要求されるようなひどい気候の下なのに、マリ・クレールの連載というポップな雰囲気を作り出しながら、自分の人生を透明な影絵でもって表現してしまうのであり、しかもしっかりとアルコールは効いていて、詩作の意味まで問うてしまうのだから、この人はただ者ではない。
安部公房の作品のように、読む者がこころをがぶっと食われ、外科的な治療が必要になってしまうことはないのだけれど、彼のこの書き物は、身体全体にいつのまにか回ってしまうフルーティでコクのあるビターな飲み物であり、やみつきになってしまう。不思議だ。雪のつもる季節に鍋でもつつきながらこたつで読むのに最適だ。
『箱男』
- 安部公房著 新潮社 1973.3
作中人物は、段ボールの箱を頭からかぶった箱男だ。彼は自分の行動を記録するため、ただひたすらノートに筆を走らせる。生きていくことはノートに筆を走らせるためであって、決してその逆ではないかのようだった。
たとえば、箱男がノートに筆を走らせるのと、数学者が黒板に白墨で数式を書き続けるのとでは、天動説と地動説ほどのちがいがある。箱男は、純度100%の記述それ自体に依存し続け、その状態の継続に生の幽かな意味を見出そうとする。黒板に白墨で数式を書き続ける数学者は、記述に終始すればそれは失敗だと観念することで生じる恐怖と闘い問い続ける。つまり、記述の目的は問いを解くことにある、だから解かれるべき答えをもっているわけだ。でも、箱男にそんなものはない。箱男と数学者の間には、架橋不能な根本的差異が存在する。
箱男がその中にすっぽりと入り込む段ボールは、自分という存在を消去するための道具であった。そんな彼には、愛する看護婦がいた。段ボールに身を隠して街を徘徊しながら、その看護婦の裸体を想像しつづけた。看護婦は彼を段ボールの外へ連れ出してくれるだろうか?彼のノートの終わりを想像しながら読んでみてほしい。
たとえば、箱男がノートに筆を走らせるのと、数学者が黒板に白墨で数式を書き続けるのとでは、天動説と地動説ほどのちがいがある。箱男は、純度100%の記述それ自体に依存し続け、その状態の継続に生の幽かな意味を見出そうとする。黒板に白墨で数式を書き続ける数学者は、記述に終始すればそれは失敗だと観念することで生じる恐怖と闘い問い続ける。つまり、記述の目的は問いを解くことにある、だから解かれるべき答えをもっているわけだ。でも、箱男にそんなものはない。箱男と数学者の間には、架橋不能な根本的差異が存在する。
箱男がその中にすっぽりと入り込む段ボールは、自分という存在を消去するための道具であった。そんな彼には、愛する看護婦がいた。段ボールに身を隠して街を徘徊しながら、その看護婦の裸体を想像しつづけた。看護婦は彼を段ボールの外へ連れ出してくれるだろうか?彼のノートの終わりを想像しながら読んでみてほしい。
『密会』
- 安部公房著 新潮社 1977.12
世の中、ひどいことがたくさんある。そのいろいろなひどいことを生起せしめる現代社会の構造のようなものについて、なんとなく想像してみても、それによって嘔吐を感じることはそうそうないだろう。けれども、文学作品によってそれが表現されると、嘔吐感の止まらなくなることがあるはずだ。密会は、まさにそんな本だった。
この作品で安部公房は、人間存在の一切から価値という価値を剥離することに成功した。こんなことを可能にする筆の力は彼しかもちあわせない。あらゆる価値を剥離され露わになった人間の存在は、さわるとべとべとしているのではないか。きっとそうに違いない。もしもこの密会という作品が現実の社会の精密な複写であるとするなら、このべとべと感も、気の迷いではないはずだ。
それにしても、安部公房はすごい。ため息が出る。出だしの雰囲気は、いつもの彼のメロディーとリズムが感じられるのだけれど、読み続けるうちに、気がつくと、いつもとはまたひと味違った印象で、ガムテープにより体中をぐるぐる巻きにされたような感覚を強いられる。その感覚に酔わされたときしか見えてこないような世界におびき寄せられてしまう。嘔吐の世界が現実の社会か。
この作品で安部公房は、人間存在の一切から価値という価値を剥離することに成功した。こんなことを可能にする筆の力は彼しかもちあわせない。あらゆる価値を剥離され露わになった人間の存在は、さわるとべとべとしているのではないか。きっとそうに違いない。もしもこの密会という作品が現実の社会の精密な複写であるとするなら、このべとべと感も、気の迷いではないはずだ。
それにしても、安部公房はすごい。ため息が出る。出だしの雰囲気は、いつもの彼のメロディーとリズムが感じられるのだけれど、読み続けるうちに、気がつくと、いつもとはまたひと味違った印象で、ガムテープにより体中をぐるぐる巻きにされたような感覚を強いられる。その感覚に酔わされたときしか見えてこないような世界におびき寄せられてしまう。嘔吐の世界が現実の社会か。
『An Artist of the Floating World 』
- Kazuo Ishiguro Vintage Books 1989, c1986
良い本だった。単純に素直にそう表現しておけば、それで十分だと思える、それほどに良い本だった。彼の筆のタッチはとっても優しい。こころの切なさをやわらかく包んでくれる。しかも、かならず救いが用意されている。こどもの登場人物イチローくんの最後の一言は、真冬の凍りついた湖の上に取り残された老人が、ふとポケットの中から見つけ出したホッカイロみたいなものだった。もういちどオールを漕ぐ力とその楽しさが自然と現れてくる、そんな希望の暖かさを贈ってくれる一言だった。
戦前、アジアにおける大日本の実現を目指して動いた画家は、戦後、居場所を失う。主人公の彼は、貧困のなか鋭い眼をむき出しにする子供たちの上に、中国大陸へ進出していこうとする日本の軍隊を描いていた。他方で、欧米の圧倒的な文明を背景とした植民地支配に対して、日本文化の優越性を示していこうとしていた。けれども、彼の弟子の一人が警察に連行されてしまう。一番優秀な弟子だった。その弟子は、師匠の方針に対抗しようとしていた。その弟子に期待していた師匠の彼は、内務省のプロジェクトに参加していて、名前も影響力を行使できそうなくらい売れていたのだけれど、反政府的な絵を描くようになったその弟子を、助けることはできなかった。こういった経緯は、本書の中のほんの一部で簡単に触れられているに過ぎない。でも、戦後の彼の日常生活の背景を予想させるには、そのほんの数ページの記述で十分である。
彼とその弟子たちは、中国大陸に対して、日本政府の方針に沿ったとあるプロジェクトを進めていた。戦後、彼の弟子の中でもっともできの悪かった者が、彼に対して、自分はそのプロジェクトに関係していなかったと証言して欲しいと頼みこむ。このシーンは、70年代までに青春時代を過ごし終えた世代の日本人には、ぜったいに描くことができないのではないと想う。この時期の日本については、かならずや、正と邪、正義と悪の二分法で描くことになってしまわないだろうか。でも、カズオ・イシグロのこの作品では、政治の硬く冷たい構造に手足を固定され首を絞められるふつうの人たちのこころの風景が、とっても切なく美しく描かれている。彼の筆のタッチは、奇跡に近い。
彼の描く日本は、ふと、日本人が中国の文化の品々に抱くイメージで装飾されているような、そんな印象を抱かせる。たしか、主人公の彼が2番目の師匠のもとを去っていく直前、その師匠との会話のやりとりが描かれるシーンだったと思う、ランタンに次から次へと火がともされていく場面があった。光と影のゆらめきが、こころをとってもやわらかく包んでいくように描写されていた。言語芸術には、色も音も温度も匂いも、こころに入り込むありとあらゆる存在を描くキャパシティがある。彼の作品は、それを見事に証明している。
長崎を舞台にした『A Pale View of Hills』と本書は、『When We were Orphan』とセットで読むべきかもしれない。彼のポスト・コロニアリズム的な色彩が感じられる。日本の政治論にも、それは必要ではないだろうか。欧米の植民地支配を問題にすると、日本では右翼扱いされる傾向がある。欧米の植民地支配に対抗しようとした日本の解放路線を論じようとする場合、日本が中国や韓国やASEAN地域に対して行った蛮行が、不問に付される傾向がある。どっちもどっちだ!『When We were Orphan』では、イギリス・日本・中国軍閥および中国共産党それぞれの鬼畜的な行為が、それぞれに異なった色彩で描かれていた。
構造の圧倒的な重さが、一人ひとりの人間を押しつぶしている、そんな背景画の中で、その一人ひとりの人間の生き方が、締め付けられるような切なさで描き出されていく。ただ、必ず救いの灯火が読者に贈られる。『When We were Orphan』もそうだし、本書もそうだった。硬く冷たい圧倒的な構造を、ほとんど直接的には触れずに、でもありありと舞台の背景画として描き出しながら、そんな切ない人間の生の日常の生き方を淡々と彫拓していく彼の筆のタッチは、言語芸術に対する限りない可能性を予想させてくれる。
こころを描く彼の遠近法は、機械時計では測ることのできない時間の流れを具象化する。この技法は、時間の逆行や重複や伸び縮みを可能にする。彼の時制の使い方に、きっと秘密があるに違いない。もしも彼にこの技術がなかったら、あるいはその習得が中途半端だった場合、先に挙げた三作は、文学を政治の手段に貶めてしまう駄作として読んでしまったに違いない。政治の構造の中にふつうの人々のこころの遠景・近景の重複・逆転を描き出そうとするその試みは、一歩間違えば、政治的な立場によって感動されたり忌避されたりする、そんな情けない文学の模造品に堕していたのだと思う。カズオ・イシグロの筆の力は、これを超えている。
戦前、アジアにおける大日本の実現を目指して動いた画家は、戦後、居場所を失う。主人公の彼は、貧困のなか鋭い眼をむき出しにする子供たちの上に、中国大陸へ進出していこうとする日本の軍隊を描いていた。他方で、欧米の圧倒的な文明を背景とした植民地支配に対して、日本文化の優越性を示していこうとしていた。けれども、彼の弟子の一人が警察に連行されてしまう。一番優秀な弟子だった。その弟子は、師匠の方針に対抗しようとしていた。その弟子に期待していた師匠の彼は、内務省のプロジェクトに参加していて、名前も影響力を行使できそうなくらい売れていたのだけれど、反政府的な絵を描くようになったその弟子を、助けることはできなかった。こういった経緯は、本書の中のほんの一部で簡単に触れられているに過ぎない。でも、戦後の彼の日常生活の背景を予想させるには、そのほんの数ページの記述で十分である。
彼とその弟子たちは、中国大陸に対して、日本政府の方針に沿ったとあるプロジェクトを進めていた。戦後、彼の弟子の中でもっともできの悪かった者が、彼に対して、自分はそのプロジェクトに関係していなかったと証言して欲しいと頼みこむ。このシーンは、70年代までに青春時代を過ごし終えた世代の日本人には、ぜったいに描くことができないのではないと想う。この時期の日本については、かならずや、正と邪、正義と悪の二分法で描くことになってしまわないだろうか。でも、カズオ・イシグロのこの作品では、政治の硬く冷たい構造に手足を固定され首を絞められるふつうの人たちのこころの風景が、とっても切なく美しく描かれている。彼の筆のタッチは、奇跡に近い。
彼の描く日本は、ふと、日本人が中国の文化の品々に抱くイメージで装飾されているような、そんな印象を抱かせる。たしか、主人公の彼が2番目の師匠のもとを去っていく直前、その師匠との会話のやりとりが描かれるシーンだったと思う、ランタンに次から次へと火がともされていく場面があった。光と影のゆらめきが、こころをとってもやわらかく包んでいくように描写されていた。言語芸術には、色も音も温度も匂いも、こころに入り込むありとあらゆる存在を描くキャパシティがある。彼の作品は、それを見事に証明している。
長崎を舞台にした『A Pale View of Hills』と本書は、『When We were Orphan』とセットで読むべきかもしれない。彼のポスト・コロニアリズム的な色彩が感じられる。日本の政治論にも、それは必要ではないだろうか。欧米の植民地支配を問題にすると、日本では右翼扱いされる傾向がある。欧米の植民地支配に対抗しようとした日本の解放路線を論じようとする場合、日本が中国や韓国やASEAN地域に対して行った蛮行が、不問に付される傾向がある。どっちもどっちだ!『When We were Orphan』では、イギリス・日本・中国軍閥および中国共産党それぞれの鬼畜的な行為が、それぞれに異なった色彩で描かれていた。
構造の圧倒的な重さが、一人ひとりの人間を押しつぶしている、そんな背景画の中で、その一人ひとりの人間の生き方が、締め付けられるような切なさで描き出されていく。ただ、必ず救いの灯火が読者に贈られる。『When We were Orphan』もそうだし、本書もそうだった。硬く冷たい圧倒的な構造を、ほとんど直接的には触れずに、でもありありと舞台の背景画として描き出しながら、そんな切ない人間の生の日常の生き方を淡々と彫拓していく彼の筆のタッチは、言語芸術に対する限りない可能性を予想させてくれる。
こころを描く彼の遠近法は、機械時計では測ることのできない時間の流れを具象化する。この技法は、時間の逆行や重複や伸び縮みを可能にする。彼の時制の使い方に、きっと秘密があるに違いない。もしも彼にこの技術がなかったら、あるいはその習得が中途半端だった場合、先に挙げた三作は、文学を政治の手段に貶めてしまう駄作として読んでしまったに違いない。政治の構造の中にふつうの人々のこころの遠景・近景の重複・逆転を描き出そうとするその試みは、一歩間違えば、政治的な立場によって感動されたり忌避されたりする、そんな情けない文学の模造品に堕していたのだと思う。カズオ・イシグロの筆の力は、これを超えている。
『記憶する水』
- 新川和江著 思潮社 2007.5
臨海学校で岩場で遊び、奥へ奥へといくうちに迷い、ふと周りを見渡すと海から離れ山の中に入り込んでいて、空気は透明なままだけど手で触れてその膜を感じられるようになった、そんな神秘の瞬間、清涼水がわき出る泉を見つけたとしたら、そんなときにこころが取り込まれてしまう雰囲気は、きっと、この人の詩に沈静したときと、とても似ているような気がする。とてもすがすがしいのと、せつなくてしょうがないのと。ふたつの空気の流れが別荘地の深閑とした美術館のようにひっそりとうつくしくグラデーションを創り出している。好きになりそうな世界だった。
『伊藤比呂美詩集』
- 伊藤比呂美著 思潮社 1988年
楽器なし、肉体だけの大地の踊り。ただし朝、じゃなくて夕暮れどき。そんな印象がふくらんできた。ことばはリズムを打てるだけでなく、メロディーも奏でられるらしい。この人の詩を眺めながら、そう思えてきた。精神とか、思想とか、そういったこと一切考えず、目をつぶって浸りながら、土の中に身体が溶けていきそうになる。そんなふうな感じだった。ヒトひとり、完全に虜にしてしまう雰囲気を創り出せる数少ない書き手の一人なんだと思う。この人の放つことばは、天才外科医が手術で愛用するこころ凍るような鋭利なメスにもなれば、原始人間ギャートルズたちが野球をやるとき使うような棍棒にもなる。ただ者ではない。
『ラヴソング』
- 伊藤比呂美著 筑摩書房 2004年
ことばのつむぐ大地の舞とでも言いたくなるいとうひろみの踊りのリズムと肉体の打楽器に引き込まれ、もっともっとその世界の奥深いところに立ち入っていきたくなる、そんな読み物だった
『ナンバーファイブ(吾)』1巻~4巻
- 松本大洋著 小学館 2005年
松本大洋の世界は何度も何度も楽しむことができる。ふつうは使い捨ての漫画を、耐久消費財にしてしまったアーティスト。中でもこの作品は名作だと思う。人間の世界の多くの大切なことがらの一つ一つについて、日常の我を忘れてファンタジックに沈思できる、そんな作品だった。世界のすべてが無限の優しさと愛情に包まれるのならば、それと引き替えにすべての人々がその自我を喪失してもかまわないと想う、そんな抗しがたい大きな意識の諭しにどこまでも抵抗して、個の自由を守り続けようとする孤独な男。理性の進化が世界に何をもたらすかを知ってしまい、ある日突然成長することを自ら拒否して惰眠と堕食に身を投げた天才少女。1巻から4巻まで一気に読み通すまで、他の何ごとにも手が付かなくなる、そんな経験ができるんじゃないかと想う。
『生存者の回想』
- ドリス・レッシング著 水声社 2007年
翻訳は良いできとはいえないのだけれど、レッシングの世界の一端が、そのもともとの作品の威力で、こちらのこころにねじりこむようにやっくる。あらゆる秩序、人間らしさを一切否定するライアン一族、大人という大人を狩りの対象にする地下の4、5歳の子供ギャングたち、あらゆるものを覆いまたその核心に存在する「それ」、その向こうに空想的な現実が展開する「壁」、そして醜い獣ヒューゴゥ。こうしたメタファーがリアルにこころに響いてくる。さまざまなまなざしが交差し・反映し・複雑にからみ合いながらも、ひとつのクリアな世界が浮かび上がってくる。その筆の力たるや、ノーベル文学賞を一流の賞に浮上させるだけのものがあった。人の織りなす社会とその内面の世界、その双方をつらぬく構造を冷厳にもファンタジーとしても描き出せるその力量は、人類による言語芸術開拓史の一翼をになっているとさえいいたい。
『暮れなずむ女』
- ドリス・レッシング著 水声社 2007年
場面場面の描写が、心的風景と社会構造とうまい具合に解け合っていて、どこまでも引き込まれていく。レッシングの作品を読み続けることによって、きっと、どこか広く深い巨大な空間に行き着くことができるのではないか。そんな予感がしてくる。
あざらしの夢、スペインの片田舎のシーン、世界食糧会議の動き、そしてロンドンの労働者階級と中上流階級のそれぞれの居住地区の対比。これらがすべて渾然一体となって、主人公の心的世界に照射されてくる。その心的世界のうごめきの中で、社会的世界の多面的な姿が、もやの中にあってしかし上向きのヘッドライトを浴びたように浮かび上がってくる。
心的世界と社会的世界をつぎはぎなしに一体化させながら、夢や幻想やSF的状況に温度と匂いを感じさせるようなリアリティを浮かび上がらせてゆく、そんな彼女の作品には、まさに現代世界の鉄の構造が紙面に言語で焦げ目ができるほど熱く照射されているのだけれど、そのような思想史的批判性と社会学的再構築性の極限まで高められた作品の中にあっても、一人ひとりの個人の切ない小さな物語がしっかりと描き出されていて、読者はその物理的な肉体の存在の維持という日常の必要を、すっかり忘れてしまう危険にさらされてしまう。
あざらしの夢、スペインの片田舎のシーン、世界食糧会議の動き、そしてロンドンの労働者階級と中上流階級のそれぞれの居住地区の対比。これらがすべて渾然一体となって、主人公の心的世界に照射されてくる。その心的世界のうごめきの中で、社会的世界の多面的な姿が、もやの中にあってしかし上向きのヘッドライトを浴びたように浮かび上がってくる。
心的世界と社会的世界をつぎはぎなしに一体化させながら、夢や幻想やSF的状況に温度と匂いを感じさせるようなリアリティを浮かび上がらせてゆく、そんな彼女の作品には、まさに現代世界の鉄の構造が紙面に言語で焦げ目ができるほど熱く照射されているのだけれど、そのような思想史的批判性と社会学的再構築性の極限まで高められた作品の中にあっても、一人ひとりの個人の切ない小さな物語がしっかりと描き出されていて、読者はその物理的な肉体の存在の維持という日常の必要を、すっかり忘れてしまう危険にさらされてしまう。
『一億百万光年先に住むウサギ』
- 那須田淳著 理論社 2006年
とっても楽しんで読むことができた。ヤングアダルト文学というジャンルがあるということ、この本ではじめて知った。ヤングアダルト? ヤングなアダルト。なんだそれ? 若いのに大人? 大人一歩手前の思春期時代御用達本? よく分からないけれど、40過ぎた男が中学時代をこんな風に過ごせたらとっても楽しかっただろうなあと想像するのに格好の読み物だった。
作者の那須田さん、絵本作家として活躍しているらしい。この本はもしかしたら、本職の合間に楽しみで昔を想像しながら書いたのかもしれない。書いていて筆が勝手に波に乗っていく、そんな感じじゃなかっただろうか。そんな印象の快適な文章だった。あったかいのに清涼な感じもして、ひとこと、うまいなぁという印象。もちろん、プロだ。当たり前か。
ただ、ヤングアダルト的なものだ。最初は読んでいて、こそばゆくなるような、恥ずかしくて思わず活字から目をそらして中空漂う羽毛を見つめたくなるような、そんな場面記述も心理描写も多かった。でも、読んでいくうちに自然と引き込まれてしまった。
鎌倉の雰囲気も良く出てた気がする。鎌倉が舞台だ。この本がつまらないわけがない。鎌倉は日本で一番の街だと、ぼくは思ってる。
銀河系外開拓団の星磨きウサギの話は、読後しばらくはこころに居座ると思う。いい話だ!この本を読んで涙も何も流さず、うまいなぁと作者の筆の運びを感心しているのだから、歳をとったというものか。作者はぼくより年上だと想うのだけれど、空想の世界ではまだまだ若々しいのかもしれない。
作者の那須田さん、絵本作家として活躍しているらしい。この本はもしかしたら、本職の合間に楽しみで昔を想像しながら書いたのかもしれない。書いていて筆が勝手に波に乗っていく、そんな感じじゃなかっただろうか。そんな印象の快適な文章だった。あったかいのに清涼な感じもして、ひとこと、うまいなぁという印象。もちろん、プロだ。当たり前か。
ただ、ヤングアダルト的なものだ。最初は読んでいて、こそばゆくなるような、恥ずかしくて思わず活字から目をそらして中空漂う羽毛を見つめたくなるような、そんな場面記述も心理描写も多かった。でも、読んでいくうちに自然と引き込まれてしまった。
鎌倉の雰囲気も良く出てた気がする。鎌倉が舞台だ。この本がつまらないわけがない。鎌倉は日本で一番の街だと、ぼくは思ってる。
銀河系外開拓団の星磨きウサギの話は、読後しばらくはこころに居座ると思う。いい話だ!この本を読んで涙も何も流さず、うまいなぁと作者の筆の運びを感心しているのだから、歳をとったというものか。作者はぼくより年上だと想うのだけれど、空想の世界ではまだまだ若々しいのかもしれない。



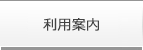
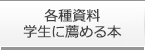

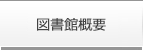




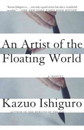







ストーリーはこんな感じ。あなたといると空気の固まりと暮らしているみたいと言われ離婚されてしまった男がUFOの降り立つ釧路のラブホテルのベッドの中で自分を見失い、家出をしてきた少女が茨城の海岸で焚き火作りの名人の40男の腕の中で心中直前にやすらかな眠りに落ち、男に裏切られ子供をおろした過去をもつ病理学専門医の女性がタイで出会った中身を完全に失った男に導かれ夢の中である時を待つよう決心し、新興宗教にこころも生活もすべて吸い取られた美しく若い母親をもつ少年が自分の父親に違いないとにらんだ男を追いかけて深夜の草野球のグラウンドに足を踏み入れ身体全体で泣きながら踊り続け、結婚の機会もなく他人の失敗の尻ぬぐいのためだけに誰の目にも留まらず感謝されず人に憎しみを与えるだけのとても危険な債権取り立ての仕事を東京の信用金庫で延々と続けてきた男がかえるくんといっしょにみみずくんと闘い東京を大地震から救い、くまのまさきちととんきちの物語の出口を探し求める男がようやく出口を探し出して親友の男と別れた親友の女に求婚することを決意し、その娘と女の中身が小さな木の箱に吸い取られることのないように一生かけて二人を守り抜く決心を固める、といった、お風呂3回分で読み終える一連の物語だった。
すべての物語に神戸の震災がいろいろな形で登場する。そういえば、昨年の秋の話だけれど、神戸市役所の展望台から六甲山のようやく色づき始めた紅葉を眺めていたとき、すぐとなりに初老のカップルが手をつないで巨大な窓の向こうをまるでそんな窓など存在しないかのように見やりながら、好い感じでデートしていた。
じいちゃん 「よくこんなに早く復興したもんやなぁ」
ばあちゃん 「そうやなぁ」
この二人のこれからの生活には、かえるくんの存在は必要なさそうだ