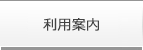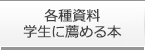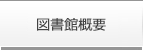学生に薦める本 2022年版
越智 敏夫
一ノ瀬直二と加島祥造と最所フミ
小学校の終わりころ、テレビで『華氏451』(フランソワ・トリュフォー、1966年)を見た。あまりにあまりな話に驚くが、たぶんこれがレイ・ブラッドベリという名前を知った最初だと思う。完全にはまりました。長編もすばらしいけれど、短編もすごい。さらにその短編集のタイトルもかっこよくて、R Is for Rocket を『ウは宇宙船のウ』と訳したのはうまいなあと思っていたら、その後に出た短編集の原題が S Is for Space だった。「ウ」はもう使ってしまったし……と思っていたら、『スは宇宙(スペース)のス』とルビつきで「ス」に置き換え。訳者の名前が一ノ瀬直二だった。
こうしてブラッドベリなどを読みはじめ、その頃に何度も読み返した小説がハリー・クレッシングの『料理人』。これも一ノ瀬直二訳。あまりに読みやすい文体。もちろんストーリーも面白くて本欄の2001年版でも紹介しているけれど、『エルマーのぼうけん』などの児童書を除くと、これが自分が複数回読んだ最初の小説だと思う。それくらい名訳だったのだろう。その一ノ瀬による訳者解説もおもしろかった。他の翻訳書の解説でも、どうしてこの人はなんでも知っていて、それをどうしてこんなに面白く伝えることができるんだろうと不思議だった。
また同じころ『ポケット一杯の幸福』(1961年)をテレビで見る。それがフランク・キャプラの遺作だったと知るのはだいぶあとのことだけれど、とにかくそのぎらつきながらも多幸感に満ちた画面とベティ・デイヴィスの演技に驚き、その後、同作品を見るたびにいろんなことを見つけるが、東京で一人暮らしを始めたころ、原作者のデイモン・ラニアンという作家の翻訳が新書館から出ていることを知って、手に入るものはすべて読んだ。その翻訳がどれも加島祥造(1923-2015)という人によるもので、その訳文のあまりのうまさに驚いた。
その加島がラニアンの解説か何かでリング・ラードナーという作家を紹介していて、新書館と新潮社から加島による翻訳が出ていたので、これもまたすべて読んだ。それらを読みつつ、自分の世界観にかなりの影響を与えている『シンシナティ・キッド』(ノーマン・ジュイソン、1965年)や『M★A★S★H マッシュ』(ロバート・アルトマン、1970年)の脚本家であるリング・ラードナー・ジュニアの名前を思い出し、ラードナーのご子息かと思ったら、ほんとにそうだった。
ただラニアンやラードナーの作品には訳されてないものもけっこうあって、それらの内容が気になったのと、原著を読むのはかっこええやろというすけべごころもあり、彼らのペーパーバックを古本屋で買って読むようになる。英語には今でも苦労しているけれど、そのころはもっと悲惨で、少しでも何とかしようと訳者の加島による英語指南本にも頼るようになった。
そのころの一連の英語のお勉強で知ったのが最所フミ(1908-1990)の著作だった。第二次世界大戦前に津田塾、ミシガン大を卒業し、さらにミシガンの大学院で学んだ最所は、戦前、戦中、戦後のアメリカと日本をその卓越した英語力で泳ぎ切る。JAPAN TIMESには英文の映画評を四半世紀以上にわたって書き続け、本人も自慢気味に書いているように、内容どころか英語表現の一片たりともアメリカ人スタッフは修正しなかったという。
その最所の著作には「辞典」という題名のものも複数あり、あれを辞典と呼んでいいのか、そこは気になるけれど英単語の日本語による説明文としては孤高の存在だと思う。各英単語の違いを日本語でどう表現するか、列挙されている単語数もすごいけれど、その説明の的確さと説得力は類例を見ない。ところが当時、残念なことに最所の本は絶版のものも多く、これらもまた古本で買って繰り返し読んだ。
ということで自分にとって英語のうまい人、というよりも自分が私淑する英語の先生はいつのまにか、一ノ瀬直二、加島祥造、最所フミの三人となっていた。
その自分が大学院を終えるころ、加島が老子についての本をパルコから刊行した。それも老子の文章の英訳から日本語への重訳である。その文章によくわからん写真を加えた豪華愛蔵版みたいな(物理的に)重い本だった。なんで老子やねんと思っていたら、その頃に加島は長野の伊那谷に引っ越したみたいで社会的イメージはほんとに仙人化しつつあった。そのあと加島は『求めない』という、ほとんど「相田みつを」状態の詩集を出し、それが売れに売れた。その後ははっきりいって高齢化社会のアイドル路線まっしぐらのように思われた。
その後、自分が本学に赴任して英語論文の読み方なども偉そうに教えるようになったころ、英語教育に関心のある人たちのあいだで最所フミの再評価が始まっていた。そして2003年に『英語類義語活用辞典』が筑摩から復刊される。その解説が加島によるものだった。ふーん、とか思いながら読んでいたら、最所に関する以下の表記に接し、本当に驚いた。
“いまは懐旧談をする場ではないから、ごく簡略に述べるが、当時の東京人の多くと同様に、彼女も私も家のない不自由な暮らしをしていた。私は思いついて彼女に1冊のアメリカ・ベスト・セラー小説の翻訳権をとってもらい、それを訳し、ある社から2人の名で出版してもらった。かなり売れて、その印税で目黒に小さな土地を購った。彼女が会社から借金もして小さな家をつくり、共に住んだ。私が1952年にアメリカに留学するまでの3年ほど、彼女から、英語について聞くことが多かった。いま私が少しは「英語のできる人間」とみられているのも、彼女から受けた英語イニシエーションによるのだ。特に英語の語感について深く教えられた”(p.420)
上記のとおり最所は1908年、加島は1923年の生まれである。それにしてもイニシエーションとわ。続けて復刊された最所の『日英語表現辞典』でも加島は解説を書いている。そのなかでもかつて「親しい間柄」だった最所の英語能力をたたえているが、戦後日本で最所と同等に英語ができたのは吉田健一だけだったとのことである。(p.635)
この最所が加島と別れたあとで結婚した相手が詩人の鮎川信夫(1920-1986)である。ただし鮎川は私生活をいっさい公表してなかったので、鮎川の死後かなり経ってから、本欄でも紹介している宮田昇『戦後翻訳風雲録』で最所との関係を知ったとき、これもまた本当に驚いた。一方、加島が老衰で他界したのが2015年の暮れである。いくつかの追悼文を読んだが、それらのひとつで早川書房が一ノ瀬直二は加島祥造のペンネームだったと発表したとき、僕は気を失うほど驚いた。
以上が最所と加島の二人と僕のつながりらしきものである。この二人がいなかったら僕の人生はまた別のものになっていただろうし、少しは英文が読めるのも二人のおかげである。出会えてよかったと思う。しかしこの二人の人間関係は日本の戦後文化史的にいえば詩誌『荒地』を中心とした一大叙事詩的な光景の一部でもある。
『荒地』創刊に関わった田村隆一 (1923-1998)、北村太郎(1922-1992)、鮎川信夫とともに加島も同誌の同人となっていた。加島の実兄が早川書房を創業した早川清(1912-1993)と小学校の同級生だったことから、加島は英米の小説の翻訳を手掛けるようになる。そしてそれら翻訳の仕事を他の『荒地』同人の詩人や研究者にも紹介するようになる。おそらく詩だけでは食っていけない多くの人がハヤカワ文庫や創元推理文庫での仕事によって(ある程度は)安定した収入を得るようになっていった。
こうした人間関係のなかで、出生年を見てもわかるように鮎川や田村でさえ、最所よりひとまわり若い。その年齢差のみならず、英語力においても『荒地』同人に比べて傑出していたであろう最所が同人たちを子ども扱いしていたことは容易に想像できる。いろんなところで引用されている「荒地詩人のゴッドマザー」という呼称も無理はないような気もするが、加島や鮎川との関係を考えるとマザーではなく他の単語を探すべきだろうとも思う。
それはともかく、彼女がいたからこそ荒地同人による翻訳の質も維持されたような気さえしてくる。そのあたりは戦後文化史のひとつの重要事項として詳細に論じるべきだろう。すでに誰かが研究しているのかもしれないが、寡聞にして知らない。いかにもアメリカの日本文化研究者が博士論文にしそうな気もする。ということで、以下、加島祥造と最所フミに関連した書籍。
『料理人』
- ハリー・クレッシング 早川書房 1972年
『英語類義語活用辞典』
- 最所フミ ちくま学芸文庫(原著:研究社) 2003年(原著:1979年)
『日英語表現辞典』
- 最所フミ ちくま学芸文庫(原著:研究社) 2004年(原著:1980年)
『私のなかのアメリカ』
- 鮎川信夫 大和書房 1984年
『新編 戦後翻訳風雲録』
- 宮田昇 みすず書房(原著:本の雑誌社) 2007年(原著:2000年)