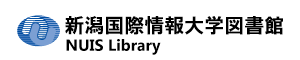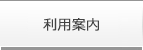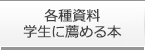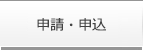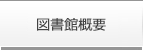図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 1996年版
石川 真澄
新書と文庫の中から5冊を選んでみました。いずれもきわめて読みやすく、しかし豊 かな内容をもつ本です。
『歴史とは何か』
- E.H.カー著、清水幾太郎訳 岩波新書 1962年
「歴史家と事実」「社会と個人」「歴史と科学と道徳」「歴史における因果関係」 「進歩としての歴史」「広がる地平線」と並んだ目次を見ただけで、魅力的な主題に ついて書かれていることが分かるでしょう。最高の歴史家が長年の歴史研究から滲み 出た哲学を、平易なことばで静かに語ったものです。これは歴史研究だけでなく、す べての学問に共有されるはずの上質な研究態度を知るうえで、学生諸君にぜひ読んで もらいたい本です。
『日本の思想』
- 丸山真男著 岩波新書 1961年
丸山さんの本では『現代政治の思想と行動』(未来社、旧版1956~7年、増補版1964 年)が、ひところは学生必読の書とされていましたが、今の大学1年生には書かれた 内容の時代背景などの点で難し過ぎるかもしれません。この新書についても同じ心配 が若干ありますが、「ササラ型とタコツボ型」「<である>ことと<する>こと」と いった、日本人の考え方や行動の仕方を論じるときに常に持ち出される問題が示され ていますし、「政治―科学―文学」といった広い範囲の連関も興味深い話題になって います。その意味でけっして古びたりしない本です。
『科学の方法』
- 中谷宇吉郎著 岩波新書 1958年
雪博士として知られるばかりでなく、寺田寅彦を継いだエッセイストとしても著名な 科学者の書いた科学論。冒頭が「科学の限界」という章であることが大切です。たと えば、幽霊はなぜ科学の対象にならないかを考えることによって「科学とは何か」と いうことの一面が分かるというあんばいに、説得力のある議論が豊富な事例によって 展開されています。
『動物と太陽コンパス』
- 桑原万寿太郎著 岩波新書 1963年
渡り鳥は何千キロもの距離を季節的に飛行します。ミツバチは巣に戻り、花のありか を仲間に正確に教えます。サケは生まれた川に数年後に戻ってきます。これらの動物 の行動はどういう仕組みによって可能なのかが、この本ではさまざまな実験や思考に よって追求されていきます。それはさながら推理小説を読むような緊張感のある世界 に読む人を誘います。科学の面白さを満喫できるのです。同じ著者の『動物の体内時 計』(岩波新書、1966年)も同じ主題を同じように面白く読ませます。
『職業としての政治』
- M.ヴェーバー著、脇圭平訳 岩波文庫 1980年
現代政治学の名著を1冊だけ挙げろと言われれば、多くの学者がこの本を選ぶでしょ う。ここには大衆民主主義のもとでの政治指導のあり方の問題、政治と倫理との特殊 な関係についての問題などが、真摯な態度で論じられています。「心情倫理と責任倫 理」といった、政治家を論じるときによく持ち出される言葉について、この本で知っ ておくのも無駄ではないでしょう。