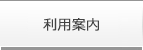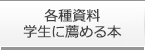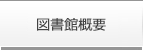図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2006年版
池田 嘉郎
文学から三冊、選んだ。内訳は、私の専門である西洋史から一冊、ロシア史から一冊、それに単に好きだということで一冊、である。
『果てしなき逃走』
- ヨーゼフ・ロート(平田達治訳) 岩波文庫 1993年
帝国というと抑圧的なイメージがつきまといがちである。だが、多様な民族がとにもかくにも一つの政体の下で共存する制度として見るならば、帝国を全否定するのはあまりに惜しい。かつてはヨーロッパにも幾つかの帝国が君臨し、地域の安定にそれなりに寄与したものである。そこに暮らす者の感覚を知りたければ、『果てしなき逃走』が一つのヒントになるかもしれない。物語の主人公はハプスブルグ帝国のユダヤ系臣民で、第一次大戦に従軍して捕虜になった後、革命ロシアの大冒険を経てやっとのことで故郷に戻ってくる。だが彼の育った帝国は既になく、チェコ人やハンガリー人やドイツ人の新しい国々にも居場所を見つけることができなかった。これはロート自身の物語で、彼はその後故郷喪失者として、帝国の追想に余生を捧げることになるのである。
『かもめ』
- アントン・チェーホフ(湯浅芳子訳) 岩波文庫 1976年
作家志望の息子がろくな才能もないのにバカな芝居をかける。それを見せられた母親はゲンナリするが、彼女とて大女優だったのは昔の話、今は時代から取り残され、息子に構っている場合ではない。どころか愛人にも捨てられそうな具合である。こいつは名の売れた作家だが結構悪いやつで、女優の息子のガールフレンドに手を出している。それで母親も息子も苛々している。穏やかに話していたのが突然切れて怒鳴り合う。そしてまた突然しみじみとした会話に戻る。誰も幸せになれずに、時だけが過ぎていく。芸術を志す者の業を『かもめ』ほど切なく描き切った作品は少ない。