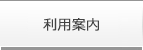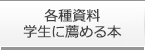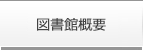図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2006年版
臼井 陽一郎
『他人の顔』
- 安部公房 新潮文庫 1989.8
文芸批評のアマチュアであってよかったと、胸をなで下ろすときがあった。日本文学の研究者でなくて助かったと、深呼吸するときもあった。公房さんのこの作品に、もしプロとして出会っていたら、大変なことになっていたと思う。安部公房研究者で一生を終えることになってしまったかも知れないのだ。こんなアンチ公房的生き方、安部公房フリークには断じて許されない。だから、この作品は心の醇となるせつない恋物語として読むことにしたい。決して、顔という人間の本質に社会関係のすべてが織り込まれている様相を100%の原色で描き切った作品だとは、考えないようにしたい。かなりムリをしてそうしている。ヒトが人となったのは、直立二足歩行ゆえではない。顔がその全存在の中心に固定されたからだ。こんなことを考え出すと、この作品の凄みがますます削られてしまう。これは、現象学的手法でもって存在者の存在に迫る一級の解釈学研究の書などではない。一万カラットのダイアモンドのようにひかる、妻と夫の恋物語なのである。
『夢の逃亡』
- 安部公房 新潮文庫
この書物は短編集である。短編集はそのうちの一本の作品で、全体の性格が決まってしまう。この書物も例外ではない。「名もなき夜のために」が織り込まれたゆえ、これは書物ではなくなった。映像があるからだ。しかもただのトーキーではない。においまで漂う。さらに付け加えれば、そしてこれがもっとも大切なことだが、夜の闇の重さを感じられるのである。夜の山手線は、恋人や友だちと別れて家路につくための、ちょっとだけ寂しい通路ではなくなった。車体のリズミカルな軋みは車内の白色灯をゆらし、心の闇をやさしい色に染めていく。公房さんはそんな山手線を、メリーゴーランドにしてしまった。スティングに出てくるやつより、いっそうもの悲しく、もっとせつなく、さらに切羽詰まっている。そんなメリーゴーランドだ。もしかすると、「彼」に会ったことがあるかもしれない。
『燃えつきた地図』
- 安部公房 新潮社 2002.11
街に出るときは、いつも帰り方を確認する。旅に出るときなど、なおさら徹底する。まるでドアを一歩出たときから帰路についているようなものだ。だから、いつも外出を楽しめない。そんなキャラクターだから、よけい、名刺に「旅行中」としたためたニューヨークのペップバーンに憧れる。けれども、ヘップバーンだから、公房さんの世界にあらわれても大丈夫なのであって、飛行機に乗った瞬間から降りるときのことを心配しているつまらない人間にとっては、地図が燃えつきてしまうと、大変なことになる。しかも、絶対に「ここ」に存在したはずだとの確信を検証するため何度も「ここ」を低徊し、そのうち自分という存在者への意識が失われていくことだって、たしかにありうるのである。公房さんの燃えつきた地図の世界に引き込まれれば引き込まれるほど、ティファニーで朝食を取り、夜のテラスでギターを弾くヘップバーンの、しなやかで絶望的な美しさが、脳裏に心に瞼に、原色で甦ってくる。
『東京裁判から戦後責任の思想へ』
- 大沼保昭 東信堂 1997.9
こころ動く社会論に、久しぶりに出会ったような気がする。昔は良く感動したものだ。それが最近は、とんと、ご無沙汰であった。知的に血湧き肉躍るような感覚は、それが知的であるがゆえに、こころを静かに、しかし着実に、そして圧倒的に支配してゆく。計算高くも真の理性を意図的に捨て去った何人もの暴徒たちが傍若無人に走り回ったあとのストリートのようにめちゃくちゃにされた国際裁判、そこから普遍的な理念と規範を取り出し、その意味と意義を構築していくという知的試みは、社会科学に従事する者たちにとっての、英雄的行為であるといえないだろうか
『詩人』
- 金子光晴 講談社 1994.7
ハードボイルドはアウト・ローにかぎる。ただし、彼の場合、そんな公式を超越している。ブブカが5メートルのバーを跳ぶようなものだ。こころの悪性腫瘍をゾーリンゲンのナイフでみずから抉り出す。これを70年続け、なお、闘う相手を時代の中に見い出す。しかも、腐臭はない。いっさいの倫理を拒絶して映える美しさ、これをことばで編み続けている。つきあい方は、これが難しい。無時間の迷路に引きずり込まれてしまう。そうなると、運良く抜け出せるのは、抜け殻の身体だけだ。
『絶望の精神史』
- 金子光晴 講談社 1996.7
だれがメガフォンをとるべきだろうか。日本の近代史が、映画になる。ちりばめられた生の断片は、それぞれの存在の深さを実感させるとともに、その存在が埋め込まれた社会の構造の、気が遠くなるほどの分厚さもまた、たっぷりと触感に訴えてくる。そんなショートストーリによって、全体がトムとジェリーの追いかけっこのようなめまぐるしさで、回っていく。絶望の意味について熟考するための論攷などではない。さまざまな絶望の形を、人間存在の日常に照射していくその手法は、読み手の気分にありとあらゆる感情を次から次へと浴びせかけていく。これは、叙情詩でも叙事詩でもなければ、いわんや、私小説などでもない。ジャンル分けしたとたん、この書の価値は劣化してしまいそうだ。
『終りし道の標べに』
- 安部公房 講談社 1995.1
何のために書くのか。まったくもって野暮な問いかけだ。いや、それどころではない。中国東北部の大地も凍る厳寒の土牢でノートに鉛筆を走らせる彼にとって、蟻さえ群がろうとはしない形だけの蒸しパンとスープの方が、はるかに価値ある存在だろう。OK。ならばぼくは問いたい。だれのために書くのか。自分を見つめるもう一人の自分にとって、その見つめている自分が絶対の他者となって現れ襲いかかりこころを食い尽くそうとするとき、食い尽くされるこころがいったいどちらの自分の所有物なのか、判然としなくなってしまった状況では、できることはただ一つ、白い紙に鉛の粉を付着させることだけなのかもしれない。でも、いったい、だれのために?存在を象徴するものどもやことがらの向こうに横たわっているはずの存在そのものに手を伸ばそうとするのは、いったい、だれのためなのだろうか。何のためという問いの無意味さは了解しよう。が、だれのためと問うことがないと、ぼくにとって終わりし道の標べにと名づけられた24歳の書き手の紡ぎ出す世界は、凶器以外のなにものでもなくなってしまう。小説というなまえは、果汁10%未満のソフトな作り話にこそふさわしく、終わりし道の標べにという活字が鋼の機械で印刷された文庫と呼ばれるこの紙の物体は、その存在のあり方にふさわしい名称が追い求められねばならない。ぼくにとってこの作品は、まさに存在象徴の向こう側にひっそりと冷たく横たわっているはずの、名づけえぬもののありかを突きつけてくれる。それを小説という名札の着いた引き出しに放り込むことはできない。しかしそれにしても、処方箋なき劇薬である。取扱注意の麻薬である。だれのためにと問い続け読み進めることによってのみ、存在象徴に囲まれた慎ましやかな日々の生活の中で、象徴であることにいささかのいたさもつらさも感じようとすることなく、ゆったりとした気分で、次の日曜日のデートコースを想像しながら、珈琲の香りを堪能することができるのである。
『詩を書く』
- 谷川俊太郎 新潮社 2006.3
氷とグラスがふれあう夏のカルピスは、欲望をさわやかに取り繕ってくれる。みかんの香りと連れ合う冬の緑茶は、欲情をやさしく包み隠してくれる。彼という存在を通じてときはなたれることばたちは、ぼくにとって、そんなカルピスであり緑茶であった。決して、人の存在の悪臭を、不躾に鼻先に突きつけるような、バーボンでもなければウオッカでもなかった。ぼくにとって散文は、とっても大切なことばのファッションであり、彼の散文集を読み終えた今、彼の飛び跳ねることばたちの魔法が、トナーを変えたばかりのプリンタから印字された活字のようにありありと、見えてきたような気がしてならない。そのことばたちは、夏のカルピスと欲望の、また冬の緑茶と欲情の、境界をなくしてくれるのである。欲望や欲情はポンポン跳ねてファンタジックになり、カルピスや緑茶はどろどろにぬるくなってこころにまとわりついてくる。芳ばしい香りと腐敗の悪臭、銀河を旅する木製の宇宙船と生ごみをはい回るゴム手袋と長靴、これら一切がひとつの世界で躍動するのである。いったい彼は何を食べてこんなにことばたちに好かれるようになったのだろう。