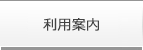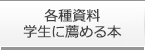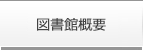図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2012年版
越智 敏夫
奇譚。変なことを思いついたらそれをそのまま作品にしても、ただの変な文章になるだけ。それをひとつの小説にするためには、それが短編であろうと長編であろうと、そのための地味で複雑なスキルが必要である。それがなければ映画『ブラック・スワン』のごとく、ただの悲惨なお笑いくずれになってしまう。以下、奇譚としての成功例(と言っていいかどうか悩むものもあるけれど)5編。みなさん、卒論を書くときにも注意しましょう。
『香水――ある人殺しの物語』文春文庫
- パトリック・ジュースキント著 文藝春秋 2003.6
奇譚、その1。王道の長編。匂いをめぐるピカレスク・ロマン。18世紀のフランスに生きた主人公は香水を作る天才で殺人狂。当時の都市や農村には臭いものや臭い場所が多かったことだろう。だからこそ匂いに執着することで自己実現をはかる人生。これはきつい。小説のテンポの良さに反比例して主人公の懊悩は深まる。アラン・コルバン『においの歴史――嗅覚と社会的想像力』(藤原書店)もあわせてどうぞ。ちなみにジュースキントはドイツ人。奇譚を堪能するには、このあたりも要注意。
『天来の美酒/消えちゃった』光文社古典新訳文庫
- アルフレッド・エドガー・コッパード著 光文社 2009.12
奇譚、その2。短編集。この邦題の間抜けさかげんにうんざりしながらも読み始めると、これが比類なき独特の世界。孤高とさえいってよい。恐怖小説のようであり、ユーモア小説のようでもあり、人生訓のようでさえあり。コッパードは20世紀前半の英国作家。労働者階級に生まれ、極貧のなか育ち、様々な職業を経験した彼はなぜこのような世界を文章として構築できたのか。それ自体が大きな謎のような気がするが、ともかく何ものにも似てない。収録作のなかでは「マーティンじいさん」が特に好き。
『飛蝗の農場』創元推理文庫
- ジェレミー・ドロンフィールド著 東京創元社 2002.3
奇譚、その3。小説にルールはあるのか。始まりから全体の8割くらいまでは圧倒的におもしろい。台詞のリアリティなど筆力の高さもあるが、設定や展開の面白さもあって、ついつい一気に読んでしまう。問題は最後の2割。この部分を小説としての規範(「お約束」というのも可)を欠いたぐだぐだと見るか、禁じ手ぎりぎりのサイコ・ミステリーの妙なる楽の音と評価するか。ミステリーを逸脱し(たふり?)ながら、やっぱりミステリーになっているというところが面白い。各種書評でも毀誉褒貶あふれてます。
『フラットランド』
- エドウィン・アボット・アボット著 日経BP社 2009.3
奇譚、その4。想像力の限界。1884年初版の古典……とはいうものの、この小説の世界は立体ではなく平面しかない二次元の世界。そこでの権力闘争の話。人間(といっていいかどうかわからない)もみんな平面上に存在し、体積ではなく面積しかない。これが本当のひらべった族。ということで、想像力を働かせる見本のよう。翻訳も大変。日本ではこれまで2回翻訳され、ともに絶版。とくに最初の講談社版は高校生が読んでも誤訳だらけと気づくほどひどかった。三度目の正直の今回はイアン・スチュアートの注釈付。
『胎児の世界――人類の生命記憶』中公新書
- 三木成夫著 中央公論社 1983.5
奇譚、その5。言いたいことを言ってみたら、奇譚になっていたという例。簡単にいえばトンデモ本。有名なヘッケルの反復説「個体発生は系統発生を繰り返す」、つまりある動物が受精してから生まれるまでの過程は、その動物がたどってきた進化の過程を繰り返す、というかなり危ない思想に胎児の記憶(それも民族単位!)というファクターを添加。妄想全開。ばりばり。人間が羊水に浸っていたときの記憶は個体を超えて、種としての民族に共有される。さらにその記憶は太古の海で誕生した生命進化(よーするにプランクトンとか)の記憶の再演である、とか言われるとねえ。もう「永劫」とか出てくると爆笑ものの大奇譚。気分転換にバッティングセンターに行くような読書体験としてどうぞ。これが中公新書だよ。