[ ▲ページの先頭へ ]
新潟国際情報大学 情報センター図書館
〒950-2292 新潟市西区みずき野3-1-1
Tel: 025-239-3760(直通) Fax: 025-264-3001
Copyright (C) Niigata University of International and Information Studies. All rights Reserved.
〒950-2292 新潟市西区みずき野3-1-1
Tel: 025-239-3760(直通) Fax: 025-264-3001
Copyright (C) Niigata University of International and Information Studies. All rights Reserved.
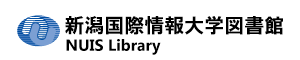


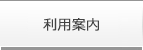
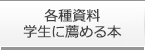
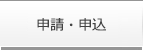
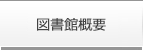

あらすじを書くと、いわゆる「ネタバレ」になる危険がありますが、簡単に紹介します。
15歳のミヒャエルは、通学途中で気分が悪くなり、偶然通りかかった年上の女性ハンナに看病された事がきっかけで知合います。
ミヒャエルは、ハンナに乞われて本を朗読して聞かせることが習慣になります。最初は、ミヒャエルの父が書いた本のカントの分析論についての一節を、次は、トルストイ『戦争と平和』などを。
ある日、勤勉なハンナに昇進の話が出た直後、突然彼女は姿を消します。
次にミヒャエルが彼女の姿を見たのは、法学部の大学生になり、ゼミでナチスの戦争犯罪者を裁く裁判を傍聴に行ったときでした。
彼女は、第二次大戦中に強制収容所で看守をしており、その時の事件に関する罪を問われていました。
彼女は、実際の罪よりも重い判決を受けることになるのですが、抗弁せずに判決を受け入れました。
ミヒャエルは、ハンナの服役後8年目から、18年間にもわたってハンナのために『オデュセイア』やチェーホフやシュニッツラーを朗読し、カセットテープを刑務所に送り続けました。
最初の朗読を送ってから4年目に初めてハンナから拙い文字のお礼の手紙が届きました。
最初に朗読を送ってから18年目に、ハンナの恩赦が認められ事になりました。
ミヒャエルは逡巡しますが、結局彼女の出所後の面倒を見ることを決意しました。
決意後、刑務所を訪れ、老人になったハンナに再会し、これからの生活のプランを話し、ハンナも承知したかのように見えました。しかし、出所の朝ミヒャエルが迎えに行くと、ハンナは自殺していました。
(これから先は、「朗読者」を読む可能性がある方は、読まないでください。)
この物語のポイントは、ハンナが読み書きができないこと。それを他人に知られないように生きてきたことです。
ミヒャエルは、判決後、様々の事実を重ね合わせて推察し、彼女が読み書きができないこと確信しました。
昇進のためには、書類の記入が必要であること。不利な判決を受入れたのも記録を読むこともできず、報告書の「筆跡鑑定」を避けるため。
彼女は、不当な判決を受け入れてまでも読み書きができないことを隠し通したのです。
朗読のテープを送り始めてから4年目に初めて彼女から届いた手紙でミヒャエルが彼女が字が書けるようになった事を知り、喜ぶ場面は感動的です。
貧困のため教育を受けられなかった勤勉な人間は、特に戦争に関しては、しばしば厳しく罰せられます。
ルース・レンデルの『ロウフィールド館の惨劇 』も趣は全く異なりますが、同じモチーフのミステリーです。
現在では、読み書きができない人は先進国には少なく、ユネスコの2002年調査では、15歳以上の日本人の99.8%が読み書きができるという報告が公表されています。
「読み書き能力(識字)」をリテラシーといいますが、現在では、「情報リテラシー」、「メディアリテラシー」、「コンピュータリテラシー」など、様々な分野でのリテラシーが必要とされています。
ハンナだけでなく、誰にとっても知識やリテラシーが人間にとってのライフラインでです。自由に本を読めることがとても幸せだと感じさせられた1冊です。