図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2014年版
越智 敏夫
幽閉小説4+1。ペローやグリムの『眠れる森の美女』『いばら姫』『髪長姫』をあげるまでもなく、主人公がどっかに閉じこめられて出られない状況をひとつの童話や小説にしてしまうというのはよくあることかもしれない。
しかしバルザック『谷間の百合』(1835年)、ゴーティエ『死霊の恋』(1836年)、スタンダール『パルムの僧院』(1839年)、大デュマ『モンテ・クリスト伯』(1844年)、同『ダルタニャン物語:鉄仮面』(1847年)、ユゴー『レ・ミゼラブル』(1862年)と並べてみると、七月革命、二月革命期のフランスロマン主義(とくくるのもどうかと思うが)の巨匠たちは、なぜそろいもそろって「わたし、お城のなかで身動きとれません」みたいなお話をたくさん書いたのか。おそらくこの点について専門研究者が論じたものはたくさんあるのだろうが、でもまあ不思議だなあと思う。
ということで「近代市民社会は人間をそこまで息苦しくしているということだ」という安直な結論を出さないためにも、以下、その手の本の現代版、5冊。
『山椒魚』
- 井伏鱒二【著】 新潮社 ※表題作初出1929年
西洋に幽閉小説が多いのは、その巨大で強固な城塞や高塔、教会という建築的特性とも大きく関連しているのは当然。とすれば紙と木でできた建築物に暮らす日本人は幽閉されようもない。座敷牢や島流しなど、そういうちょっと違った方向の作品は可能かもしれないけど。
ということで、日本ものの幽閉小説としてはこれを推したい。著者の人生全体を通じて改作されつづけた異色短編。特に1985年の新潮社版「自選全集」収録の際は大胆な文章削除がおこなわれ、小説全体の意匠が根底から変貌したほどである。あのときはびっくりしたなあ、と過去を振り返る私も山椒魚みたいなものかもしれない。蛙君だろうか。けろけろ。
ともあれ、自分の人生なんか何かに幽閉されるようなもんだと開き直りたい方はこの日本版「プラトン洞窟の比喩」をどうぞ。それにしても、いったい何に幽閉され、どうやって逃げようとしてるんでしょうねえ、わたしらは。「今でもべつにお前のことを怒ってはいないんだ」という台詞も人生で一回くらいは言ってみたい。
ということで、日本ものの幽閉小説としてはこれを推したい。著者の人生全体を通じて改作されつづけた異色短編。特に1985年の新潮社版「自選全集」収録の際は大胆な文章削除がおこなわれ、小説全体の意匠が根底から変貌したほどである。あのときはびっくりしたなあ、と過去を振り返る私も山椒魚みたいなものかもしれない。蛙君だろうか。けろけろ。
ともあれ、自分の人生なんか何かに幽閉されるようなもんだと開き直りたい方はこの日本版「プラトン洞窟の比喩」をどうぞ。それにしても、いったい何に幽閉され、どうやって逃げようとしてるんでしょうねえ、わたしらは。「今でもべつにお前のことを怒ってはいないんだ」という台詞も人生で一回くらいは言ってみたい。
『サラの鍵』
- タチアナ・ド・ロネ【著】 高見浩【訳】 新潮社 ※原著2007年
これは来ますよ。なにがどこにどう来るのかはぜひ読んで体験してもらいたい。こんなおちゃらけた文章のなかで紹介するのも躊躇するほど重い。重いという言葉が不適切だと思えるほど重い。タイトルのもとになったエピソードのみならず、その前後左右を囲う人々の在り方まで読みとってもらいたい。
映画化されたものも良くできているとは思ったけれど、これもまた小説のほうがはるかに良い。おそらくは読む人によって印象に残る場面も異なるであろうし、感情移入できる登場人物も異なってくるだろう。読後、世界の風景が変わるほどの作品だとは思うが、あまり誉めすぎても本学の学生さんは退いてしまうだろうという危惧からこのあたりでやめておきます。でもやはり読んでほしい一冊。これを読んで、時間を返せと言いたい学生さんがいたら、ぜひ研究室に来てもらいたい。心底、その感想を聞きたいので。
映画化されたものも良くできているとは思ったけれど、これもまた小説のほうがはるかに良い。おそらくは読む人によって印象に残る場面も異なるであろうし、感情移入できる登場人物も異なってくるだろう。読後、世界の風景が変わるほどの作品だとは思うが、あまり誉めすぎても本学の学生さんは退いてしまうだろうという危惧からこのあたりでやめておきます。でもやはり読んでほしい一冊。これを読んで、時間を返せと言いたい学生さんがいたら、ぜひ研究室に来てもらいたい。心底、その感想を聞きたいので。
『驚きの介護民俗学』
- 六車由実【著】 医学書院
小説ではありません。が、不謹慎かつ月並みな表現ながら、そこらの小説より面白いので。個人的なことだけれど、実父やら義母やらの介護の問題が生じてから、やっとまじめに考え始めたこの問題。はい、わたくし、阿呆です。しかしそういう自分の近くの現実に接したからこそ、介護も幽閉だなあと厭世的に思ってしまう。でもこれはたぶん多くの方も同意するところではないだろうか。
介護において「ケアされることを強制されない権利」はどのようにして維持できるのか。上野千鶴子によれば介護とは「ケアする側とケアされる側との相互行為」である。じゃあ幽閉してるのは私なのか。ともあれ何かにすがろうとして読んだ本書。(おそらくは)いろいろあって大学教員を辞めた民俗学者が、(おそらくは)いろいろあって特別養護老人ホームの介護職員となる。その日常のルポ。いやあこれまた重いけれど、読みはじめるととまらない。学生の皆さん、人生なんて、あっというまです。
介護において「ケアされることを強制されない権利」はどのようにして維持できるのか。上野千鶴子によれば介護とは「ケアする側とケアされる側との相互行為」である。じゃあ幽閉してるのは私なのか。ともあれ何かにすがろうとして読んだ本書。(おそらくは)いろいろあって大学教員を辞めた民俗学者が、(おそらくは)いろいろあって特別養護老人ホームの介護職員となる。その日常のルポ。いやあこれまた重いけれど、読みはじめるととまらない。学生の皆さん、人生なんて、あっというまです。
『The face of fear』
- Dean R. Koontz 【著】 Berkley
天才クライマーだった Graham は5年前にエベレストで滑落。心身ともに深い傷を負う。そのため登山から離れ、現在はニューヨークで山岳雑誌編集者として暮らしている。しかし彼はその事故後 clairvoyant となり、透視能力を身につけることにもなった。その彼がゲスト出演したテレビの生番組で連続強姦殺人の現場を透視してしまう。そのため犯人は彼の命を狙いはじめる。
……という滅茶苦茶な設定の小説。しかし真冬の深夜、超高層ビルのオフィスに恋人の Connie といる Graham が、階下から殺人犯が上がってくる像を透視したところから、ストーリーは一気にジェットコースター化。エレベーターはこの殺人鬼によってすべて止められ、階段で出会えば、必ず殺される。追い込まれた Graham は編集部に置いてあった登山用具を取り出し、暴風雪のなか、超高層ビルの外壁を移動して犯人から逃げようとする。
どんどん消耗していく Graham の軟弱な精神と対照的に、勁草とよべるほど魅力的な Connie のキャラ。また彼らを利用して(?)犯人を逮捕しようとするニューヨーク市警刑事 Ira Preduski の設定のうまさ。犯人の設定もかなりひねっている(ように見える)。
Koontz が人気作家になる前、Brian Coffy 名義で書いた本作は上記プロットを読めばわかるように、トレヴェニアン『アイガー・サンクション』(河出文庫、原著1972年)やラングレー『北壁の死闘』(創元推理文庫、原著1982年)などの山岳冒険小説の基本プロットを踏襲。しかしその構造をとりながらも、閉じこめられた男女二人の脱出行という別の話にしているところがまたずるくてうまい。
翻訳の『マンハッタン 魔の北壁』(なつかしの角川ホラー文庫!)はたぶん絶版だし、これも英語で読んだ方が面白いと思う。「誰が何を考えたか」という英文は読むのが大変なときもあるけれど、「誰が何をしたのか」という英文は読みやすいのが常。それに、人生、何かからの逃避と考えればこれもまた必読(しつこいですか?)。
……という滅茶苦茶な設定の小説。しかし真冬の深夜、超高層ビルのオフィスに恋人の Connie といる Graham が、階下から殺人犯が上がってくる像を透視したところから、ストーリーは一気にジェットコースター化。エレベーターはこの殺人鬼によってすべて止められ、階段で出会えば、必ず殺される。追い込まれた Graham は編集部に置いてあった登山用具を取り出し、暴風雪のなか、超高層ビルの外壁を移動して犯人から逃げようとする。
どんどん消耗していく Graham の軟弱な精神と対照的に、勁草とよべるほど魅力的な Connie のキャラ。また彼らを利用して(?)犯人を逮捕しようとするニューヨーク市警刑事 Ira Preduski の設定のうまさ。犯人の設定もかなりひねっている(ように見える)。
Koontz が人気作家になる前、Brian Coffy 名義で書いた本作は上記プロットを読めばわかるように、トレヴェニアン『アイガー・サンクション』(河出文庫、原著1972年)やラングレー『北壁の死闘』(創元推理文庫、原著1982年)などの山岳冒険小説の基本プロットを踏襲。しかしその構造をとりながらも、閉じこめられた男女二人の脱出行という別の話にしているところがまたずるくてうまい。
翻訳の『マンハッタン 魔の北壁』(なつかしの角川ホラー文庫!)はたぶん絶版だし、これも英語で読んだ方が面白いと思う。「誰が何を考えたか」という英文は読むのが大変なときもあるけれど、「誰が何をしたのか」という英文は読みやすいのが常。それに、人生、何かからの逃避と考えればこれもまた必読(しつこいですか?)。



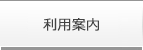
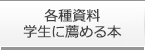

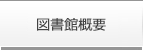




現代の英国ケントに住む25歳のエミリーがいきなり時空間を吹っ飛び、見たこともない異世界で城塞のなかの牢に閉じ込められる。そして牢番以外に会話を交わすことは禁じられながらも、周囲の世界が少しずつ明らかになり……と、ネットにあふれる腐小説のような設定ながら、おそらくは特異な読書経験となるはず。小説の構成がエミリーが隠れて書いた手記のかたちを取るため、いっそう錯綜するこちらの感覚。ラストも「驚愕」と簡単には書けない。1960年代に書かれていながら30年も出版されなかったのもわかるような気がする。ともあれ、読後、研究室に怒鳴りこまれても、当方、責任はもちません。