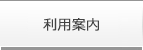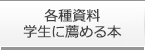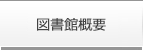図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2018年版
越智 敏夫
「かわいいふりしてあの子、わりとやるもんだね」という歌詞を最初に聞いたとき、その末尾の「やるもんだね」というあまりに古色蒼然たる語感(よーするに、そんな言い方、今時だれがするんや?)もあってか、これはコミックソングだろうと信じたのだけれど、世間の反応はまったく異なり、もしかして本気(まじ?)と恐怖するも、それを歌っていた本人がその後、近鉄から巨人に移籍した内野手(ちなみにこれも深い意味はないが、現在、彼は参議院議員)と結婚したときには、ほれ見ろ(何を?)と思ったけれど、まあそういうことも世の中にはあります。ということで(どういうことか、ほんとはよくわからんけれど)以下、地味なシリーズのなかでびっくりさせられる異形の5冊。
『ルバイヤート』(岩波文庫)
- オマル・ハイヤーム(著) 小川亮作(訳) 岩波書店 1979年
その昔、駿台予備学校(なぜか駿台は予備校と称さない)の世界史の授業で大岡師と関師(なぜか駿台は先生と称さない)がともに推薦していた書。この二人が言うならということですぐに駅前の丸善で買い、寮に帰る総武線車中で読み始めて驚き、一気に読み切った。11世紀後半のペルシアで書かれたこの四行詩の内容はほぼすべて飲酒か性に関するもの。それを材料として自分のあらゆる運命を「ま、いいか」と全面肯定するわけだから、ふつうのレトリックでは詩にならない。まずそこにびっくり。さらにはこんな冒涜的で刹那的な、というよりただの「酔っぱらいのすけべじじい」の寝言のような詩がイスラム圏で書かれ、19世紀ラファエル前派の詩人にまで影響を与え、まわりまわって岩波文庫に入るほどの古典となったことにも驚いた。ペルシア、アラブ、イスラム、中東とか、簡単にまとめてはいかんなあと反省したかどうか、すでに泥酔の極だったので覚えてません。
『北越雪譜』(岩波文庫)
- 鈴木牧之(著) 京山人百樹(刪定) 岡田武松(校訂) 岩波書店 1978年
その『ルバイヤート』が奏功したかどうかわからんけれど、なんとか浪人生活も一年で終え大学に入った直後、たまたま買った本にはさまっていた宣伝用のしおりを見たら、かんじきを履いた蓑姿のじいさんの絵。岩波文庫とも思えぬそのファンキーなたたずまいに驚き、すぐに買ったのが本書。新潟県民の多くはその内容を知っているだろうけれど、これも実際に読んでみたら必ず驚くと思う。著者の科学的好奇心と合理的探求心があまりに近代的(おおげさにいえば『薔薇の名前』のウィリアムみたい)でありながら、出てくる逸話がすべて面白すぎ。この落差はすばらしい。江戸中で評判になったというのもよくわかる。ただ、大学に新潟出身の友人がいたので、自分の出身地、四国の民俗学的びっくりネタを隠したまま、この本をネタにして彼をいろいろといじってしまった。「おまえんとこは雪男がおにぎりをもらいに裏庭まで来るんやて?」とか。ごめんなさい、反省してます。しかし今となっては、こっちもその新潟で政治学を教えているんだから、人生、わからんもんです。
『山海経』(平凡社ライブラリー)
- 高馬三良(訳解説) 平凡社 1994年
上記『ルバイヤート』が岡田恵美子訳で読める(こちらの書名は『ルバーイヤート』)のが平凡社ライブラリー。これもまた岩波文庫におとらず地味に見えるかもしれませんが、その起源のひとつは東洋文庫ですからね。とんでもないもの(もちろんほめことば)が混じっているわけですよ。その典型ともいえるのが本書か。だまされたと思ってページを開くように。人間の想像力がいかに天空を駆けることができるか、という見本。その豪華絢爛、魑魅魍魎な挿絵もすごいが文章のほうが数段上を行く。これを中国古代の地理書というのなら、いったい地理とは何かということまで考えてしまうはず。とか書いてますが、実はこの中国古典研究の世界(だけじゃないか)、中国五千年の遺跡からいろんなものが次々に出土し、従来の「定説」がどんどん否定されていくという光速の世界でもあって、とんでもない深さと残酷さがあります。少しでもへたなことを書くと、もう人格否定の憂き目にもあいそう。そういう事例としてびくびくしながら読んでみるのも可。もちろん解説は水木しげる先生。この部分も必読。
『幻のアフリカ』(平凡社ライブラリー)
- ミシェル・レリス(著) 岡谷公二・田中淳一・高橋達明(訳) 平凡社 2010年
毒を食らわば皿まで。これも平凡社ライブラリーの一冊。1930年代、若き日のフランス人作家・思想家レリスが2年間にわたるアフリカ横断の学術調査団に参加したときの日記。宣伝文では彼が書記兼文書係として書いた公的記録とある。ところが読んでみるとこれがびっくり。全体的なトーンとしては植民地主義という壮大な暴力を批判しているので、政治的には正しいと思う。しかしその批判でさえ個人的呪詛に近いものであり、他にも自分の過去への悔恨、他人の悪口、性的告白、現地でみた夢、果ては単なる妄想まで。そりゃあ上司は怒るよなあという公文書。初版は発禁までくらったそうです。でも読んでいるうちにそれらがとても魅力的に思えてくるのも事実。またその内容もさることながら、文庫本ながら1000ページもあるサイコロのようなたたずまいは価格も3000円超(税込)。上下二分冊にしなかった編集担当者の決断は称揚されてしかるべき。1971年にイザラ書房から<1>という番号のついた部分訳が出て以来、1995年の河出書房新社版(こっちは8000円超!)を経て本書刊行にいたる経緯が書かれた解題は涙なくしては読めない。英訳でさえ昨年(2017年)の夏、コロンビア大学の比較文学者ブレント・エドワーズによる完訳版がやっと出たくらいである。見よ、日本学術出版界のど根性。
『新哲学入門』(岩波新書)
- 廣松渉(著) 岩波新書 1998年
しょせん私の哲学理解など、素人の戯れ言(ざれごと、と読みます)。謙遜ではなく本当にそう思う。しかしこの書を読んだとき、人間にとって「解放」とはなにかということがほんの少しだけわかったような気がした。つまりは気持ちが楽になったということ。本書で展開される認識論、存在論、実践論という言い方は面倒な気もする。しかし強引にまとめれば、人間はどのような阿呆であれ、ものを考えつつこの世に存在し行動するしかない以上、できることならよりよく考え、よりよく存在し、よりよく行動しましょう、と。さらにその結論を要約すれば、やりたいことをやらない人生に意味はない、ただそのやりたいことは本当に自分のやりたいことなのか、一生考えろ、と。そしてそれを考えることは、実は「旧」来のあらゆる世界観を疑うことでもある。その意味で本当の哲学はつねに「新」哲学にならざるをえない。そのことに読者は最後に気づくという「ちからわざ」の一冊。アジテーターとしての廣松。よくもまあ入門書のふりをしてこんなラジカルな扇動の書を岩波新書に入れたもんです。さらには本書もまた内容もさることながら、その体裁にも驚く。各段落の文字数のそろえ方から始まって、章、節、小見出しの題名の文字数までそろえられていることに気づいたとき、著者のこだわり(それを哲学的姿勢と呼ぶのも可)の一端をかいま見た気がして、恐怖のあまり気を失いそうになった。