図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2015年版
越智 敏夫
ペットを飼う者は倒錯者である。と、いきなり嫌われそうなことを書くけれど、他者に頼らなければ絶対に生きていけない存在をつくりあげ、それを自分の近くにおいて自分だけを頼らせる状態を永続的に維持するのは、情愛とか相互理解とかではなくて、虐待や疾患などの表現で考えるべきではないか。たしかに、幼児の情操教育や震災の罹災者等の精神的回復、あるいは独居老人の生きがいの発見における動物使用の実例を考慮すれば、積極的に評価すべきものでもある。しかしそれらを愛玩とまで呼ぶのは、行き過ぎだろう。やはりペット飼育は不気味である。考えてみれば、捕食以外の目的で他種の動物に接近しようとうする動物は人間以外、本当に希少である。それは人間のみがどはずれて残酷な生き物だということでもある。ということで、動物のことを書いているようにみせながら、実は人間のことしか語っていない傑作5編。
『動物のぞき』
- 幸田 文著 新潮社 1998.12 (新潮文庫)
幸田文がシートンを好きだと書いているのを読んで、心底、救われた気がした。何がどう救われたかは言いたくない。説明が面倒なので。かわりに、この本、読んでください。しかし、たとえば「熊は私たちに親しいのである」という幸田の文章は、やはり救済という域に達していると思う。何をどう書き、どう描いていも、「哀」という境地に達する幸田が動物を語って面白くないわけがないという奇跡の書。添えられえた土門拳の写真20葉がまたすばらしい。これらを見るだけでも、ぜひ図書館へ。
『野性の呼び声』
- ジャック・ロンドン著 光文社 2007.9(光文社古典新訳文庫、原著1903年)
常春の国、カリフォルニア州サンタクララ。大金持ちの白人のペットとして、のほほんと暮らしていたセントバーナード(と別種狩猟犬の混血。このあたりの設定もうまい)の子犬バック。ところが突然、盗賊に拉致され、カナダ・ユーコン準州、極北の氷原での労働犬として売りとばされる。鞭と棍棒をもった人間からの搾取に耐えながら生き残るすべを身につけ、労働犬どうしの闘争をも勝ち抜いていくバック。
都会のぼんぼんが過酷な現実に直面して意識変革する、というこの構図は、人工から自然、とか、理性から本能、といった語られ方が一般的だろう。それはそれで面白いし、本作の説明としてはそれ以外にない気もする。実際、読んでいて感動的である。しかしこの構図はまた、北部自由州から拉致され南部奴隷州で叩き売られるアフリカ系アメリカ人を想起させるし、人によってはヘイ・マーケット事件(1886年シカゴ:米国初の労働者と警察の大規模衝突であり、メーデーの起源となった)以降、激烈になった労使対立を思い出すかもしれない。つまりはバックの変化は、被差別者の自己発見であり、階級意識の鮮烈な認識ともいえるだろう。
ジャック・ロンドン(1876-1916)はシートン(1860-1946)より16年遅く生まれ、30年早く死んだ。このサンフランシスコ港の牡蠣泥棒出身の作家が短命であり、最期はモルヒネ自殺だった(他殺ほか諸説あり)というのも、同じ動物という主題を描きながら、シートンとはまったく違うものを語っていたと考えると、やはり哀しいことである。
ロンドンは1901年、アメリカ社会党に入党し、その直後に本作を書いている。ほぼ同時期に『どん底の人びと:ロンドン1902』という傑作ルポルタージュをものした視点は、本作、また次に紹介する作品とも完全に共有している。
実は(と、もったいぶるほどのことではないが)本作の本邦初訳は堺利彦による。これは、(日本においてのみ)『動物記』とともに人口に膾炙することの多い、ファーブルの『昆虫記』を日本で最初に紹介したのが賀川豊彦であり、初訳が大杉栄によるものだということとあわせて、いろいろ議論できるだろう。ちなみに、私が『昆虫記』と賀川、大杉との関係を知ったのは林達夫の文章だった。それがどうした、と言われても困りますが。
都会のぼんぼんが過酷な現実に直面して意識変革する、というこの構図は、人工から自然、とか、理性から本能、といった語られ方が一般的だろう。それはそれで面白いし、本作の説明としてはそれ以外にない気もする。実際、読んでいて感動的である。しかしこの構図はまた、北部自由州から拉致され南部奴隷州で叩き売られるアフリカ系アメリカ人を想起させるし、人によってはヘイ・マーケット事件(1886年シカゴ:米国初の労働者と警察の大規模衝突であり、メーデーの起源となった)以降、激烈になった労使対立を思い出すかもしれない。つまりはバックの変化は、被差別者の自己発見であり、階級意識の鮮烈な認識ともいえるだろう。
ジャック・ロンドン(1876-1916)はシートン(1860-1946)より16年遅く生まれ、30年早く死んだ。このサンフランシスコ港の牡蠣泥棒出身の作家が短命であり、最期はモルヒネ自殺だった(他殺ほか諸説あり)というのも、同じ動物という主題を描きながら、シートンとはまったく違うものを語っていたと考えると、やはり哀しいことである。
ロンドンは1901年、アメリカ社会党に入党し、その直後に本作を書いている。ほぼ同時期に『どん底の人びと:ロンドン1902』という傑作ルポルタージュをものした視点は、本作、また次に紹介する作品とも完全に共有している。
実は(と、もったいぶるほどのことではないが)本作の本邦初訳は堺利彦による。これは、(日本においてのみ)『動物記』とともに人口に膾炙することの多い、ファーブルの『昆虫記』を日本で最初に紹介したのが賀川豊彦であり、初訳が大杉栄によるものだということとあわせて、いろいろ議論できるだろう。ちなみに、私が『昆虫記』と賀川、大杉との関係を知ったのは林達夫の文章だった。それがどうした、と言われても困りますが。
『白い牙』
- ジャック・ロンドン著 光文社 2009年(光文社古典新訳文庫、原著1906年)
順番としては、かならず『野性の呼び声』を先に読んでから、こちらを読んでもらいたい。ロンドンが「カリフォルニアの青い馬鹿」バックのことを書いてからの3年間に何があったのか。こちらはバックとは逆に、犬の血が4分の1混じる狼、ホワイト・ファングが人間の世界に触れていくという、本当にいろんな意味で逆の構造をもつお話。でも(だからこそ)これも面白い。
しかし、実は『白い牙』というタイトルは、私にとっては1970年代中期の大映テレビの傑作『白い牙』のほうが先である。警察上層部と組織暴力の罠にはまって失職した警視庁捜査一課のエリート刑事、有光洋介が主人公のハードボイルド。おそらくは藤岡弘のライダー1号以外、最高の演技である。どんどん主要登場人物が死んでいく展開ながら、共演レギュラーは川津祐介、藤巻潤(大山倍達先生の義弟!)、ジェリー藤尾、佐藤慶という、どうやったらこんなことになったのか、というほどの壊れ方。
けれども、実はこのテレビドラマがロンドンの『野性の呼び声』を(おそらくは)元ネタにしていて、にもかかわらずタイトルを『白い牙』からパクった、ということに気づいたとき、本当に驚いたものでした。違うかなあ。深読みか。でも大映テレビだしねえ。
しかし、実は『白い牙』というタイトルは、私にとっては1970年代中期の大映テレビの傑作『白い牙』のほうが先である。警察上層部と組織暴力の罠にはまって失職した警視庁捜査一課のエリート刑事、有光洋介が主人公のハードボイルド。おそらくは藤岡弘のライダー1号以外、最高の演技である。どんどん主要登場人物が死んでいく展開ながら、共演レギュラーは川津祐介、藤巻潤(大山倍達先生の義弟!)、ジェリー藤尾、佐藤慶という、どうやったらこんなことになったのか、というほどの壊れ方。
けれども、実はこのテレビドラマがロンドンの『野性の呼び声』を(おそらくは)元ネタにしていて、にもかかわらずタイトルを『白い牙』からパクった、ということに気づいたとき、本当に驚いたものでした。違うかなあ。深読みか。でも大映テレビだしねえ。
『The Science Fiction Hall of Fame, Vol.1: 1929-1964.』
- Robert Silverberg, ed. Orb Books 2005年(オリジナル原著1970年)
なんでこの英文アンソロジーなのかというと、
Richard Matheson, "Born of man and woman"
という傑作が収録されているから。人間と獣はどう違うのか、ということを考えると、ついつい思い出してしまう作品。1950年代初頭に雑誌に掲載され、その後、リチャード・マチスン本人の短編集に入り、さらにその後もいろんなところで編まれ、読まれ、恐怖されている短編SF。パロディにされている回数もすごいと思われる。
日本語にもなっているけれど、ぜんぶ絶版だろうし、短い話なので英語で読んだほうが怖い。ほんとに怖い。そもそも日本語題の「モンスター誕生」ってねえ。いくらなんでもひどすぎ。「男と女から生まれた」と訳したほうが1億倍怖い。
マチスンもはずれの少ない高打率作家だけれど、ほんとにこれはもう人間と動物の境界ってなんだろうと思い至り、答えのないまま寝てしまうほどの作品。今、思い出しても初めて読んだ時の嫌な気分がよみがえる。
ところで標記アンソロジーは他の収録作品もすばらしい。同種のSF短編集に比しても、かなり例外的に高い評価を得ているように思う。編者のロバート・シルヴァーバーグは地球上でもっとも多くのSF作品を読んだ人間だろうが、彼自身も信じられないほど多くの作品を量産している。彼がパソコンを使用し始める前、あまりに大量の作品を書いたために叩き潰した英文タイプライターの数は28にのぼるという(←これは大嘘)。
Richard Matheson, "Born of man and woman"
という傑作が収録されているから。人間と獣はどう違うのか、ということを考えると、ついつい思い出してしまう作品。1950年代初頭に雑誌に掲載され、その後、リチャード・マチスン本人の短編集に入り、さらにその後もいろんなところで編まれ、読まれ、恐怖されている短編SF。パロディにされている回数もすごいと思われる。
日本語にもなっているけれど、ぜんぶ絶版だろうし、短い話なので英語で読んだほうが怖い。ほんとに怖い。そもそも日本語題の「モンスター誕生」ってねえ。いくらなんでもひどすぎ。「男と女から生まれた」と訳したほうが1億倍怖い。
マチスンもはずれの少ない高打率作家だけれど、ほんとにこれはもう人間と動物の境界ってなんだろうと思い至り、答えのないまま寝てしまうほどの作品。今、思い出しても初めて読んだ時の嫌な気分がよみがえる。
ところで標記アンソロジーは他の収録作品もすばらしい。同種のSF短編集に比しても、かなり例外的に高い評価を得ているように思う。編者のロバート・シルヴァーバーグは地球上でもっとも多くのSF作品を読んだ人間だろうが、彼自身も信じられないほど多くの作品を量産している。彼がパソコンを使用し始める前、あまりに大量の作品を書いたために叩き潰した英文タイプライターの数は28にのぼるという(←これは大嘘)。



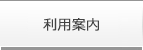
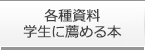

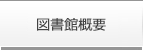





さらには『シートン動物記』をマンガ化さえしているその白土が、実はこれも未完の怪作『死神少年キム』の、未完とはいえその後半にシートン本人をいきなり登場させるあたり、今になって読んでみるとかなり驚く展開である。
もちろん活字のほうも含めてこの「シートン動物記」は日本のみの現象であって、アメリカ、カナダはもちろん他国においてそのようなシリーズ名称はない。このイギリス生まれのカナダ人作家のばらばらの作品群を、さもすべて意図的に編まれたかのように「動物記」と名づけたのは、柏崎生まれの名翻訳家、内山賢次である。その意味では内山がいなければ、戦中から現在にいたるまでの日本の少年少女の読書体験はいっそう貧弱なものになっていたことだろう。
ただし私は内山訳のものはさすがに読んでない(と思う)。猿のごときガキのころ、集中して読んだのは偕成社版『少年少女シートン動物記』なので、おそらくは白木茂先生の名訳だったはずである。現在、文庫でシートンの原作をまともに読めるものが標記の集英社文庫版しかないということも日本の出版文化の衰退を示しているとはいえ、まだこれが読めるだけ幸せなのか。
ということで「狼王ロボ Lobo, the King of Currumpaw 」である。とにかく強く巨大な雄狼がいる。それに率いられた狼の群に家畜を喰われて困った開拓農民たちがシートン本人に駆除を頼む、というそれだけの話ではある。しかし、自分を殺しにくる人間の家来となった猟犬たち(文字どおり「ポチ」ですなあ)を返り討ちにしつづけるロボの人物造形(?)がなによりもすばらしい。これを読まずして、人間、自由について語ってはいかんですよ。そして純白の雌狼ブランカ(この存在感もすごい)登場後、一変するストーリー。これを読んで泣かない者は(これまた文字どおり)人の皮をかぶった狼である……と書いていいのか。
他にも、はっきり言ってこの文庫に入ってるかどうか知らんが、「だく足の野生馬 ムスタング」、「暴れザル ジニー」など、読後、忘れたくても生涯忘れることのできないほどのインパクトを残す作品群。小学校の運動会の行進で左右の手足を一緒に前に出してしまうクラスメートは「ムスタング」と呼ばれたし、テレビでハヌマンラングールを見るたびに「ジニー」を思い出しては悲嘆にくれる人生になってしまった。嘘に決まっているとは思うが、シートンはこれらを実話だと言い張る(ロボの写真まである)ので、その悲嘆はさらに深くなる(のか?)。