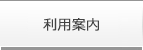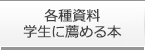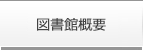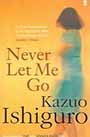図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2020年版
臼井 陽一郎
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』 上下巻 (新潮文庫 )
- 村上春樹 新潮社 1988年
毀誉褒貶の激しい作家、村上春樹。でも、バカにされまくるほうが多いかな。まあ、100万部も売れれば、過激な批判はもちろん、色んな形の揶揄も雨あられ状態。文学作品としての質がどうこう言うつもりはまったくない。夕暮れ時の中央フリーウェイをトップギアで走るおしゃれなユーミン派にとって、夜の営団地下鉄終電のドアが閉まるのをぼおっと見つめてる中島みゆきファンなんて、ダサくてキモくて仕方ないっていうのに、ちょっと似てなくもない(たぶん)。でも、ファンというのは、何連敗してもヤクルトスワローズが好きだったじゃんね。そんなこんなで読み続けてる作家の一人。他人に趣味で頭の中をいじられ(一時的にではあっても)死に行く運命となった自分の不運を抵抗もせず淡々と受け入れる一方の主人公。他方、世界の終わりに連れて行かれたもうひとりの主人公(一方の主人公の別次元の意識)は、しかしその切り離された影がどこまでも諦めずに閉じ込められた死の世界からの逃亡を企てる。アンデルセンの影(シャドウ)のオマージュ的作品かなともおもうけど、意味関係が逆転していて、影は本人を見捨てずどこまでも戦い続けようとする。地下に巣くうヤミクロや世界の終わりの門番が人間のメタファーであることはとても分かりやすく、ファンにとってはけっし安易な物語設定ではなく、何度も楽しめるエンターテイメント要素なのである。戦い続けられる強さをもつのに、意識消滅の運命を受け入れる人間。頭蓋骨から物語を読み取るという図書館での仕事を延々と続けながら心が消滅していくのをただ淡々と待つだけの人間。中途半端にこころをもってしまっているがために街と森の境界で生き続けなければならない発電所の管理人。運命に抗い最後まで抵抗し命の持続を求めていくのは影だけ。その他にも世界の終わりと<非終わり>をイメージする様々なモチーフがちりばめられた作品。人間存在について、いろんなことをあれこれイメージするのに、なかなかのアイテム満載の作品である。なんでこれを取り上げたのかというと(村上作品のウリは本来は人間の再生であり、脇役ではノルウェーの森のれいこさん、主人公では海辺のカフカくんがその最たる例で、そのプロセスの描写には(ファンだからだけど)心打たれてしまう。でもこの作品は再生へ向かわない)、UKはリーズという街にいたとき、シティセンターの大きな本屋さんウォーターストーンに暇さえあれば通って、大きなソファーで本を読んでいたことがあり、そのとき、村上春樹の世界の終わりとハードボイルドワンダーランドの英訳を買おうと思い立って(3ポンドくらいでたしかセールだった、、記憶は定かでないが)、その本を手に取りレジに行くと、おにいちゃんが気怠そうに這い寄ってくる感じでその本を手に取った。感じわりぃなぁっておもってたらそのにいちゃん、おもむろに姿勢正して目を輝かせ、この本を選ぶなんてきみはセンスが良い、これは素晴らしい本だよ、って語り出した。ついつい、ウエメセになって、性格の悪いところ丸出しで、「ぼくはそれ、日本語で何度も読んでるよ、凄く良いよね」って、言っちゃったんだよね。そしたらそのにいちゃん、ものすごく悲しがって、「そうなんだよ、日本語で読みたいんだよ、でもぼくには日本語ができない(池中玄太80キロのもしもピアノが弾けたなら的なノリで)」って、いうんだよね。本当にこの作品が好きなんだなあって思って、その感じ悪かったにいちゃんのことが好きになってしまった。そんな思い出が懐かしい。でも結局、英訳は読んでないままだ。
『Never Let Me Go』
- Kazuo Ishiguro, Faber and Faber 2005年
本には、忘れられない感触というものがある。個人的な読書体験のなかでその最たる例となるのが本書。臓器移植のために生みだされたクローン人間たちの、青春と愛と希望と挫折と絶望が、海に入っていくシーンに凝縮されている(と、思っていた)。主人公の一人の、寄宿学校時代のダメダメな男の子が、自分が本当に好きな相手が誰なのを知って、そして自分の運命も知って、さらにはその運命から逃れられないことも知って、海に入っていくシーン。ガッツポーズをしながら海に入っていくシーン。そのシーンがもう、忘れられなくて、本書には特別な思い入れがあった。臓器移植のためのクローンたちにも人権があるんだと訴え、そのクローン人間たちの教育に精をだした正義の文明人がいた。その正義の文明人のおかげでクローン人間たちは青春時代を送ることができた。でもやがてクローンたちは、卒業となり、自分たちの運命を知っていくことになる。そしてそれを受け入れていく。クローン人間たちにも教育を、人権を、正義をと叫んだ文明人は、クローン人間たちにも人間らしい感情があることを知って、気持ち悪がる。文明と野蛮の構図が見事に描かれるSF小説というものは、実はそれほど珍しくはなく、SFというジャンルの表現のポテンシャルは計り知れないのであり、だから本書も特別なわけじゃない。が、それでも、本当にダメダメな男の子が愛と運命を知って空高く拳をあげ海に入っていくシーンの感触が忘れられなくて、本書は特別な一冊になっていた。その感触を大切にしたくて、本書を読み返すのは特別なときに取っておこうと想い、そのままになっていた。数年前、たまたま何かの機会に読み直すきっかけがあった。そのシーンの感触が──ジョーのクロスカウンターのように──意識にねじりこんできたからだ。人生情況になにかあったのかもしれない。何のきっかけだったか、すっかり忘れてしまったけど、とにかく、そのシーンを探してみた。ところが、どこにもないのである。あのいじめられていたダメダメ男の子の、成長しいよいよ臓器移植の手術が始まろうとしているときの、あの海のガッツポーズのシーンが、どこにもない。全ページ探してみた。でも、ない。かくして、幻の一冊となってしまった。統合を進めEUを作ってきたヨーロッパは、クローン人間に人権を唱えながらも気持ち悪がるあの集合的政治的心性を、完全に克服しえたのだろうか。ヨーロッパのあとを追って帝国の建設に精をだしてやがていまの憲法を手にできた日本はどうなのだろうか。構図の単純化はものごとの実態を見誤らせるのだけれども、本質への問いを失えば、人間と社会を相手にしたどんな研究もその意味を喪失する。幻の一冊となった本書はいまだに、研究の意義を教えてくれている。ガッツポーズのシーンはきっと、どこかの行間に隠れているのかも知れない。
『悲の器』 (高橋和巳作品集 ; 2)
- 高橋和巳 河出書房新社 1971年
高橋和巳を取り上げるならいうまでもなく、邪宗門であるべきなのだが、ごくごく個人的な思い出を引っ張り出すことを目的とすると、悲の器になる。こんなもの、1回読めば充分なのに、数年の時を開けて2回も読んでしまった。戦前を仲間売って体制側で生き残った知識人は人間としてくずだね、ってなだけの、どうでもいいストーリー。それなのに、個人的には惹かれてしまう。なぜだろうと考えてみたのだけど、きっと、本書の主人公に心底、共感できるからなのかもしれない。ぼろぼろになった彼が歩き続けるシーン、そこが好きだった。フォークナーの八月の光も、マッカーシーのザ・ロードも、ポール・オースターのティンブクトゥも(こっちは犬だけど)、歩き続けるシーンが頭に焼き付いて離れないのだけど、その歩き続けるシリーズのひとつが、この『悲の器』。それにしても、学問に真摯に取り組む知識人は、人間性の腐敗したダメ人間を描き出す格好の型にされることが多い。スポンジケーキを焼くための型みたいに。考えれば考えるほどにどうでも好い作品なのだけど、なんともいえない無条件の魅力があって、なんでこんな本に魅力を感じるのかを考え続けることに、なんとなく、酔っているのかも知れない。主人公の学説・現象学的法学理論なるものについて、本書を手に取った若い自分が一生懸命考えていたときのあの神保町界隈のマックかドトールか忘れたけどまだ煙草が吸えた時代のスモークかかったあの思い出が、本書の魅力の正体なのかも知れない。
『地の果て至上の時』 (小学館文庫 ; 中上健次選集 ; 10)
- 中上健次 小学館 2000年
中上健次との出会いは本書ではなく、鳳仙花だった。そのあと、本書に引き込まれ、枯木灘そして岬と、秋幸3部作を逆にたどることになった。3部作とは知らずに。でもその読み方が良かったようで、かえって岬という作品がもつ魅力がたっぷりと身体に染みこんできた。地の果て至上の時は、人間をみるときの条件反射的な優劣断定基準を、完璧に壊してくれた作品。人間がもつべき価値観について考えるとき、そうした価値観をもつことそれ自体の意味についてあわせて考え込んでいくべきなのであるが、これを教えてくれたのが本書であった。この作品を読まなかったらと思うと、そら恐ろしくなる。中上健次の作品世界では、文明と野蛮という二項対立図式が跡形もなくぶち壊される。この破壊作業の現場に立ち会いたくて、彼の作品を読みまくっていった。早稲田通りに文学専門の古書店があって、足繁く通い、でも大抵は何も買わずに出てきてしまうのだが、たまにお金があると、1冊、2冊と買い集めていった。懐かしい。あの頃は夢も金もなかったけど、読書は楽しかった。
『夢の逃亡』
- 安部公房 新潮社 1977年
安部公房にハマったきっかけが本書。いや、文学に感染したというべきか。短編集。なかでも「名もなき夜のために」という作品に痺れた。夜の山手線のリズムと匂いがいまでも瞬時に甦る。強烈なメッセージがしなやかな文体により可能になるのだと体感。自分自身の文体を手に入れなくては先に進めないと、若き自分が青く語ったその姿がほんのり懐かしい。「名もなき夜のために」はリルケの『マルテの手記』がベースとなった短編。安部公房にとってのリルケに当たる人を自分も探さなくてはと、こころに誓った青い自分。その感覚はいまでも残る。同じ人間・同じ街を同じカメラで撮るにしても、カメラワークでまったく異なる絵となる。「名もなき夜のために」で描かれるのは、発作が起きたときの主人公の、その肉体と精神の境界なき震動。紙の上の文字を読んでるだけなのに、息がほんとうに苦しくなってきた。忘れられない経験。文体こそが現実を顕わにするのである。