図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2020年版
越智 敏夫
リン・フレデリック(Lynne Frederick、1954-1994)。その出演作を見た人は一生忘れないけれど、見てない人には存在さえ気づかれないという不思議なイギリス人女優。世界中に新型ウイルスが蔓延して荒廃した都市から人々が逃げ始めるとか、接岸を拒否された巨大客船のなかで人々が不安な日々を過ごすとか、この2020年前半の世界を想起させるような映画もあります。それら彼女が強烈な印象を残した出演作のほうを紹介してもいいけれど、それではつまらんので原作のほうをご紹介。それぞれ面白いし。それにしても1970年代にはこの手の女優がイギリス以外にもけっこういましたねえ。シドニー・ローム、栗田ひろみ、オッタヴィア・ピッコロとか。
『絶望の航海――ナチ・ドイツを逃れて』(原著:1974年、映画化:1976年)
- ゴードン・トマス、マクス・モーガン=ウィッツ ハヤカワ文庫NF 1980年
映画版『Voyage of the damned(さすらいの航海)』(DVD)
- スチュアート・ローゼンバーグ監督 復刻シネマライブラリー 2019年
『ニコライ二世とアレクサンドラ皇后――ロシア最後の皇帝一家の悲劇』
(原著:1967年、映画化:1971年)- ロバート・マッシー 時事通信社 1997年
映画版『ニコライとアレクサンドラ』(DVD)
- フランクリン・J・シャフナー監督 ハピネット 2010年
ロシア革命について知ることは現在の世界に生きる人間として最重要な義務のひとつである。そのためには本学でも教鞭をとられていた池田嘉郎さんの『ロシア革命――破局の8か月』(岩波新書、2017年)を。しかし昨年(2019年)末に亡くなった歴史家、マッシーによるこの歴史絵巻も読みやすい。ここで描かれる血友病とラスプーチンに関わる物語にはマッシー本人の息子も同じ疾病に罹患していたため、ただならぬ気配がある。結論としては13歳の末っ子に至るまで一家全員の処刑、というよりは虐殺……というこの悲史劇を本作をもとにフランクリン・J・シャフナーが1971年にアメリカで映画化。
映画の邦題は『ニコライとアレクサンドラ』。シャフナーはこの前後に『猿の惑星』『パットン大戦車軍団』『パピヨン』と撮り、アカデミー賞を集めつづけていたという全盛期。ところがこの作品でひたすら目立つのはニコライ夫婦の愚かさのみ。それがかえってタチアナ皇女を演じたリン・フレデリックを目立たせている。ここでの彼女の存在感はセルゲイ・ヴィッテ(ポーツマス条約!)役のローレンス・オリヴィエ、トロツキー役のブライアン・コックスあたりに負けていない(なにで?:再)というのがさすがであります。結局のところ実力のない人間を主役においた映画の不幸か。これこそロマノフ王朝のことではないかと思い至る。でも原作のほうはほんとに面白いのでぜひ読むように。
ちなみにこの翌年にもリン・フレデリックは Henry VIII and His Six Wives というBBC制作の歴史絵巻に登場、ヘンリー8世の五番目の王妃キャサリン・ハワードを演じているそうです。未見ですが、シャーロット・ランプリングがアン・ブーリン(二番目の王妃)、ジェーン・アッシャー(P・マッカートニーの最初の婚約者)がジェーン・シーモア(三番目の王妃、ややこしい)を演じているとのこと。怖いもの見たさでどうでしょう。
映画の邦題は『ニコライとアレクサンドラ』。シャフナーはこの前後に『猿の惑星』『パットン大戦車軍団』『パピヨン』と撮り、アカデミー賞を集めつづけていたという全盛期。ところがこの作品でひたすら目立つのはニコライ夫婦の愚かさのみ。それがかえってタチアナ皇女を演じたリン・フレデリックを目立たせている。ここでの彼女の存在感はセルゲイ・ヴィッテ(ポーツマス条約!)役のローレンス・オリヴィエ、トロツキー役のブライアン・コックスあたりに負けていない(なにで?:再)というのがさすがであります。結局のところ実力のない人間を主役においた映画の不幸か。これこそロマノフ王朝のことではないかと思い至る。でも原作のほうはほんとに面白いのでぜひ読むように。
ちなみにこの翌年にもリン・フレデリックは Henry VIII and His Six Wives というBBC制作の歴史絵巻に登場、ヘンリー8世の五番目の王妃キャサリン・ハワードを演じているそうです。未見ですが、シャーロット・ランプリングがアン・ブーリン(二番目の王妃)、ジェーン・アッシャー(P・マッカートニーの最初の婚約者)がジェーン・シーモア(三番目の王妃、ややこしい)を演じているとのこと。怖いもの見たさでどうでしょう。
『ゼンダ城の虜』(原著:1894年、映画化:1979年)
- アンソニー・ホープ 創元推理文庫 1970年
- 【入手困難】
映画版『ゼンダ城の虜』
- リチャード・クワイン監督 ジュネス企画 2011年
「アメリカ人作家第一号」であるマーク・トウェインの『王子と乞食』(1881年)は、16世紀の英国にエドワード6世とそっくりの乞食がいたという設定で、その圧倒的な面白さと含蓄のために歴史に残る作品となった。それを英国人アンソニー・ホープが(おそらくは)パクったのが本作。さらに本作へのオマージュ(便利なことばだなあ)として山手樹一郎が1940年に書いたのが『桃太郎侍』。
それはともかく本作のような「王様や王子にそっくりな一般人の出現が騒動を引き起こす、あるいは騒動を処理する」というパターンはけっこうあります。そのなかでも本作は軽いノリでありながら、最後まで面白く読めるのでたいしたものである。そのためかサイレント期以降かなりの回数、映画化されている。それらのなかで今のところ最後の映画化が、この1979年のリチャード・クワイン版か。
クワインは『刑事コロンボ』の演出もしていて、「ロンドンの傘」「偶像のレクイエム」「意識の下の映像」など、かなり癖のあるエピソードが多い。そのクワインが本作ではリン・フレデリック、ピーター・セラーズ夫妻の共演を演出。1977年、50歳のセラーズと21歳のフレデリックの結婚は世界中を驚かせたが、結局この映画の完成の翌年、セラーズはハル・アシュビー監督の寓話『チャンス』主演による栄光のなか、心臓発作で急逝。その後のフレデリックの不幸な人生(と他人が決めるべきことではないかもしれませんが)は1994年、39歳でのアルコール中毒死まで続く。
それはともかく本作のような「王様や王子にそっくりな一般人の出現が騒動を引き起こす、あるいは騒動を処理する」というパターンはけっこうあります。そのなかでも本作は軽いノリでありながら、最後まで面白く読めるのでたいしたものである。そのためかサイレント期以降かなりの回数、映画化されている。それらのなかで今のところ最後の映画化が、この1979年のリチャード・クワイン版か。
クワインは『刑事コロンボ』の演出もしていて、「ロンドンの傘」「偶像のレクイエム」「意識の下の映像」など、かなり癖のあるエピソードが多い。そのクワインが本作ではリン・フレデリック、ピーター・セラーズ夫妻の共演を演出。1977年、50歳のセラーズと21歳のフレデリックの結婚は世界中を驚かせたが、結局この映画の完成の翌年、セラーズはハル・アシュビー監督の寓話『チャンス』主演による栄光のなか、心臓発作で急逝。その後のフレデリックの不幸な人生(と他人が決めるべきことではないかもしれませんが)は1994年、39歳でのアルコール中毒死まで続く。
- 【入手困難】
『草の死』(原著:1957年、映画化:1970年)
- ジョン・クリストファー 早川書房 1971年
- 【入手困難】
映画版『最後の脱出』
- コーネル・ワイルド監督 復刻シネマライブラリー 2017年
片岡義男の訳によるハヤカワSFのこの一冊よりも、クリストファーの著作として今の日本(だけじゃないか)で有名なのは「トリポッド・シリーズ」だろう。ほんとうはかつて学研から出ていた旧訳題「三本足シリーズ・鋼鉄の巨人」と呼んでもらいたい本シリーズもジュブナイルとはいえ、その終末感は強い。
で、『草の死』であります。新型ウイルスで地球上のイネ科植物が全滅。社会が荒廃し、ロンドンから人々が郊外に逃げ始める。終末の王道。末世であります。その救いようのない小説を原作にした映画の邦題が『最後の脱出』。これもまたもっと正当な評価がなされるべき監督の代表、コーネル・ワイルド(俳優としてもすごいけど)の野心作であります。映像描写も不気味だけれど、やはりその人心の乱れ方が特に救いがない。世の中がこうなったら人間はこうなるだろうなあ、という点がもう嫌になるほど。現今のコロナ禍の日本が本当に平穏に見えてきます。問題もあるけど、なんだかんだいって(今のところは)けっこう良い社会を作ってきたんじゃないか、とか。
そうした落ち着いた社会の対極のような荒れた世界と心を描く本作。映画のほうが後の監督に与えた影響は絶大だと思う。本作がなければ、『ゾンビ』『マッドマックス』あたりはおそらく別の作品になっていたはず。
その地獄図絵のなかで逃げ続けるリン・フレデリック。その終末感があまりにきついので、映画よりも原作を勧めるほどであります。映画は見ないほうがいい。
で、『草の死』であります。新型ウイルスで地球上のイネ科植物が全滅。社会が荒廃し、ロンドンから人々が郊外に逃げ始める。終末の王道。末世であります。その救いようのない小説を原作にした映画の邦題が『最後の脱出』。これもまたもっと正当な評価がなされるべき監督の代表、コーネル・ワイルド(俳優としてもすごいけど)の野心作であります。映像描写も不気味だけれど、やはりその人心の乱れ方が特に救いがない。世の中がこうなったら人間はこうなるだろうなあ、という点がもう嫌になるほど。現今のコロナ禍の日本が本当に平穏に見えてきます。問題もあるけど、なんだかんだいって(今のところは)けっこう良い社会を作ってきたんじゃないか、とか。
そうした落ち着いた社会の対極のような荒れた世界と心を描く本作。映画のほうが後の監督に与えた影響は絶大だと思う。本作がなければ、『ゾンビ』『マッドマックス』あたりはおそらく別の作品になっていたはず。
その地獄図絵のなかで逃げ続けるリン・フレデリック。その終末感があまりにきついので、映画よりも原作を勧めるほどであります。映画は見ないほうがいい。
『Phase IV』(映画化:1974年)
- Barry N. Malzberg, Pocket Books 1973年
映画版『フェイズIV戦慄!昆虫パニック』(DVD)
- ソウル・バス監督 パラマウントジャパン 2014年
上記の映画『最後の脱出』でリン・フレデリックの父を演じるのがナイジェル・ダベンポート。人類映画史上、最高傑作のひとつ、フレッド・ジンネマンの『わが命つきるとも』でトマス・モアの友人ノーフォーク公トマス・ハワードを演じている人(説明になってないか)。そのダベンポートが(何を思ったか)再度、彼女と共演したSF映画が『フェイズIV 戦慄!昆虫パニック』。このしょーもない副題から想起されるものと、映画の内容はあながち違ってもない気もするが、でも面白い映画だと思う。これも世界の終わり系。
でも本作はなんといってもソウル・バス(1920-96)唯一の劇映画として紹介されるべき。最近の映画にはオープニングという概念がなくなってきて、いきなり話が始まってタイトルさえほとんどでないものもある。それに比してある時期の映画はオープニングが凝っていた。題名からキャスト、スタッフ紹介のロゴ、タイミング、音楽。それらタイトルデザインの巨匠、というよりもそのジャンル自体を作ったソウル・バス。ついでにいうとコーポレート・アイデンティティ(CI)という僕の嫌いなジャンルの第一人者でもあります。特にバブル期、日本企業を相手に無法な荒稼ぎ(ごめんね)をしたことは業界では有名(ですか?)。でもああいうのは食い物にされるほうも悪いよねえ。
で、そのバスが撮った終末感は独特で、けっこう他のSF大作と比較されながらも、あまり似た映画はないような気もする。デザイナーが映画を撮るとこうなりました感、つよし。実質的登場人物は3人。それと蟻。それらのなかでいちばん目立つのは、もちろんリン・フレデリック。ラストシーンもこれはけっこうきます。覚悟のうえ、ごらんください。
そのオリジナル脚本をSFおたく界の帝王マルツバーグ(1939- )がノヴェライズしたのがこのペーパーバック。何か面白いSFないかなあ、という質問に「マルツバーグが誉めるものを読んどけばまちがいないっす」と軽く答えるSFファンは多そう。実は越智はこの本を読んだことがなく、読んでみたいからここに推薦したのではないか、という疑問は「あり」です。すいません(多義)。
でも本作はなんといってもソウル・バス(1920-96)唯一の劇映画として紹介されるべき。最近の映画にはオープニングという概念がなくなってきて、いきなり話が始まってタイトルさえほとんどでないものもある。それに比してある時期の映画はオープニングが凝っていた。題名からキャスト、スタッフ紹介のロゴ、タイミング、音楽。それらタイトルデザインの巨匠、というよりもそのジャンル自体を作ったソウル・バス。ついでにいうとコーポレート・アイデンティティ(CI)という僕の嫌いなジャンルの第一人者でもあります。特にバブル期、日本企業を相手に無法な荒稼ぎ(ごめんね)をしたことは業界では有名(ですか?)。でもああいうのは食い物にされるほうも悪いよねえ。
で、そのバスが撮った終末感は独特で、けっこう他のSF大作と比較されながらも、あまり似た映画はないような気もする。デザイナーが映画を撮るとこうなりました感、つよし。実質的登場人物は3人。それと蟻。それらのなかでいちばん目立つのは、もちろんリン・フレデリック。ラストシーンもこれはけっこうきます。覚悟のうえ、ごらんください。
そのオリジナル脚本をSFおたく界の帝王マルツバーグ(1939- )がノヴェライズしたのがこのペーパーバック。何か面白いSFないかなあ、という質問に「マルツバーグが誉めるものを読んどけばまちがいないっす」と軽く答えるSFファンは多そう。実は越智はこの本を読んだことがなく、読んでみたいからここに推薦したのではないか、という疑問は「あり」です。すいません(多義)。



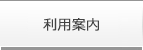
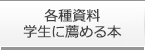

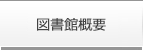







映画の邦題は『さすらいの航海』。グランドホテル形式というのは無理筋だとは思うが、ラロ・シフリン音楽の本作は信じられないほどのオールスター・キャスト(死語)。鑑賞前にロマンス映画を期待したわけではないけれど、映画館で見て絶望の淵に沈んだ。その乗客のなかで弁護士夫婦の娘を演じるリン・フレデリック。共演のキャサリン・ロスに負けてない(なにで?)のはさすがであります。しかしよりによってマルコム・マクダウェル演じる船員を好きになってしまい、悲劇の加速はとどまるところをしらない。
しかし原作は映画化されてない部分も含めてすべて興味深い。あの暗黒のような映画でさえ、いかに史実の明るいところだけを描いていたか。それを知って驚いてもらいたい。