図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2020年版
佐藤 若菜
『うしろめたさの人類学』
- 松村圭一郎 ミシマ社 2017年
私は日々の生活において、うしろめたさを感じることがしばしばあります。それは、自分の目の前に突如あらわれた絶望的なまでの不均衡に対して、公平さというバランスを全力で取り戻そうとしなかったからではないか、本書を読んでそう思いました。例えば、東日本大震災の被災者、いじめられていた同級生、ホームレス、中国で見かけた物乞いなど、過酷な状況を強いられた人びとを知りつつ、自分は平穏な生活を送っていることの申し訳なさを感じながらも、自分の生活を大きく崩さない程度にできることをしたり、もしくはなかったことにしたり、忘却したり、知らないふりをしたり。いつのまにか、国や学校のせいにして、自分とは無関係なものと見做すこともありました。つまり、知らないうちに目を背け、色んな理由をつけて不均衡を正当化していたのかもしれないと。
こういった「うしろめたさ」は私自身や社会のなかに蓄積され、なんだか窮屈にも感じます。心のどこかで、国や学校だけの問題ではないとわかっているし、自分にもできることがまだまだあると確信しているからです。では、どうしたらいいのか。本書にはその答えが書いてあります。例えば、「あたりまえ」の世界を成り立たせている境界をずらし、いまある手段のあらたな組み合わせを試し、隠れたつながりに光をあてること。それぞれの持ち場で、色んな境界のずらし方、スキマのつくり方を見出すこと、こういったことが大切なのだそうです。
文化人類学において、「境界」は重要なキーワードです。特に、排除を生み出すものとして、境界はしばしば議論されますが、それをずらすとはどういうことなのか。ぜひ、本書を手にとって考えてみて下さい。
こういった「うしろめたさ」は私自身や社会のなかに蓄積され、なんだか窮屈にも感じます。心のどこかで、国や学校だけの問題ではないとわかっているし、自分にもできることがまだまだあると確信しているからです。では、どうしたらいいのか。本書にはその答えが書いてあります。例えば、「あたりまえ」の世界を成り立たせている境界をずらし、いまある手段のあらたな組み合わせを試し、隠れたつながりに光をあてること。それぞれの持ち場で、色んな境界のずらし方、スキマのつくり方を見出すこと、こういったことが大切なのだそうです。
文化人類学において、「境界」は重要なキーワードです。特に、排除を生み出すものとして、境界はしばしば議論されますが、それをずらすとはどういうことなのか。ぜひ、本書を手にとって考えてみて下さい。
『文化人類学の思考法』
- 松村圭一郎・中村理・石井美保編 世界思想社 2019年
あたりまえのことに対して問いを投げかける、文化人類学においてはこれが重要です。
人はなぜ美しさを感じるのか?人はなぜプレゼントを贈るのか?人はなぜ戦うのか?いつ子供から大人になるのか?家族とは誰を指すのか?
これらの問いは、考えなくても生きていけるかもしれません。でも、時々、違和感を覚えることがあるはずです。そんな小さな違和感をもう一度考え直すための方法を提案しているのが、本書です。
人はなぜ美しさを感じるのか?人はなぜプレゼントを贈るのか?人はなぜ戦うのか?いつ子供から大人になるのか?家族とは誰を指すのか?
これらの問いは、考えなくても生きていけるかもしれません。でも、時々、違和感を覚えることがあるはずです。そんな小さな違和感をもう一度考え直すための方法を提案しているのが、本書です。
『そして父になる』(DVD)
- 是枝裕和 アミューズソフトエンタテインメント 2014年
『万引き家族』(DVD)
- 是枝裕和 ポニーキャニオン 2019年
日本や欧米諸国においては、家族の絆がしばしば「血のつながり」として表現されます。特に日本においては、生みの親、育ての親、法律上の親が一致していることが多く、親とのつながりのなかには複数の要素が含まれているにもかかわらず、そのことが見えにくくなっています。本映画は、生みの親と育ての親が異なる状況を題材とすることで、親子・家族とは何かを問いかけるものとなっています。類似の作品として、『万引き家族』(是枝裕和、2019)もおすすめです。
『親孝行プレイ』
- みうらじゅん KADOKAWA 2007年
以下、本書の「はじめに:新しい親孝行の時代へ」から抜粋します。本書を読んでみて、特に母娘関係は、文化人類学において、情緒的つながりと説明されますが、情緒だけじゃやってられないよねと、考え直しました。
「親孝行とはプレイである」・・・「親なのに」「子なのに」「親子なのに」これまで、親子関係、そして親孝行に挫け、破れ、去っていった多くの若者たちは最後までそんな命題をぬぐい去ることができなかった。親子という特別な関係なのに、なぜ誰よりもコミュニケーションがうまく取れないのであろうかと悩み、傷つき、倒れていったのだ。・・・しかし、今では諸君にこう教えることができる。「親だからこそ」「子だからこそ」「親子だからこそ」誰よりも気を遣い、誰よりもサービス精神を持ち、誰よりも接待感覚を忘れてはならないのだ。そう、親を喜ばせるという行為は、もはや「心の問題」ではなく、実際にどう行動するか、つまり、「プレイ」の一環なのである。
「親孝行とはプレイである」・・・「親なのに」「子なのに」「親子なのに」これまで、親子関係、そして親孝行に挫け、破れ、去っていった多くの若者たちは最後までそんな命題をぬぐい去ることができなかった。親子という特別な関係なのに、なぜ誰よりもコミュニケーションがうまく取れないのであろうかと悩み、傷つき、倒れていったのだ。・・・しかし、今では諸君にこう教えることができる。「親だからこそ」「子だからこそ」「親子だからこそ」誰よりも気を遣い、誰よりもサービス精神を持ち、誰よりも接待感覚を忘れてはならないのだ。そう、親を喜ばせるという行為は、もはや「心の問題」ではなく、実際にどう行動するか、つまり、「プレイ」の一環なのである。
『甘さと権力:砂糖が語る近代史』
- シドニー・W・ミンツ 平凡社 1988年
なぜ私たちは甘いものが好きなのかと考えたことはありますか。本能的に、ないし身体が求めているから、甘いものを好むのだと考えている人も少なくないでしょう。
本書は、歴史学的な視点から砂糖がイギリスに普及した過程を示しています。砂糖は、1100年頃にイギリスにもたらされ、香料や医薬品、贅沢品・奢侈品として扱われました。その後、マジパンといった装飾用の素材として、富や権力、ステイタスを誇示するものとなったそうです。植民地で大量に生産されるようになると、砂糖を紅茶と混ぜ合わせて飲む習慣とともに、安価な日常必需品として洪水のように普及しました。また、パンと砂糖入り紅茶を組み合わせた食事は、労働機会が増加した女性によって、時間と燃料費を節約できる効率的なカロリー源として受け入れられるようになったそうです。
本書では、砂糖が普及した要因として、生産システムの変化とそれによる価格の低下、また砂糖の色とそのイメージ、他の食品と混ぜ合わせやすい性質、特に苦いものに混ぜると一様に甘くなるという味を指摘しています。加えて、労働スケジュールや家庭内分業における変化や、食事形態の変化(食事時間の短縮化、外食化など)にも言及しています。これらのことから、人間は本能的に甘いものを好むわけではないことがわかります。
著者である人類学者ミンツは、「すべての社会現象は、その本質において歴史的なものであり、ある時点の状況は、過去や未来から切り離された抽象的な存在などではありえない」と述べています。これに加えて、本書を読んでわかることは、私たちの習慣化した営みは、いくつかの外在的要因からもたらされているということです。その外在的要因には、ミクロなものからマクロなものまで様々あるようです。私たちの当たり前を、歴史的な視点から疑ってみる術をおしえてくれる一冊です。
本書は、歴史学的な視点から砂糖がイギリスに普及した過程を示しています。砂糖は、1100年頃にイギリスにもたらされ、香料や医薬品、贅沢品・奢侈品として扱われました。その後、マジパンといった装飾用の素材として、富や権力、ステイタスを誇示するものとなったそうです。植民地で大量に生産されるようになると、砂糖を紅茶と混ぜ合わせて飲む習慣とともに、安価な日常必需品として洪水のように普及しました。また、パンと砂糖入り紅茶を組み合わせた食事は、労働機会が増加した女性によって、時間と燃料費を節約できる効率的なカロリー源として受け入れられるようになったそうです。
本書では、砂糖が普及した要因として、生産システムの変化とそれによる価格の低下、また砂糖の色とそのイメージ、他の食品と混ぜ合わせやすい性質、特に苦いものに混ぜると一様に甘くなるという味を指摘しています。加えて、労働スケジュールや家庭内分業における変化や、食事形態の変化(食事時間の短縮化、外食化など)にも言及しています。これらのことから、人間は本能的に甘いものを好むわけではないことがわかります。
著者である人類学者ミンツは、「すべての社会現象は、その本質において歴史的なものであり、ある時点の状況は、過去や未来から切り離された抽象的な存在などではありえない」と述べています。これに加えて、本書を読んでわかることは、私たちの習慣化した営みは、いくつかの外在的要因からもたらされているということです。その外在的要因には、ミクロなものからマクロなものまで様々あるようです。私たちの当たり前を、歴史的な視点から疑ってみる術をおしえてくれる一冊です。



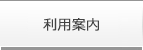
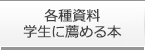

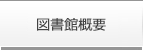








「他者理解」は一見、うつくしい言葉にも思えますが、理解する相手を「他者」と呼ぶことで、「自分とは異なる」という意味を付与しているともいえます。だからこそ、他者への先入観を乗り越え、自分の考える枠組みに変更を加え、他者との間に新しい関係を生み出すことが、最終的には重要です。
佐藤監督の著書『ドキュメンタリーの修辞学』(2006、みすず書房)には、「長期滞在、対象の懐に飛び込むこと、加担することで生じる共犯関係、ラッシュフィルムを見せることで進む人間関係がある」、「民族学的関心や珍奇な風俗習慣への興味といった<大義>にけっして足をすくわれないこと。ただただその人々の日常を凝視することだけに関心を集中させる。世界のはての物珍しい風俗としてではなく、どこでもある家族の日常を描く」と書かれています。
私たちは、国籍が異なる人、病をかかえている人、習慣が異なる人を、「他者」と瞬時にみなし、理解しやすいレッテルを貼りがちです。しかし、文化人類学が推奨する長期的な参与の先には、新しい理解と新しい関係があります。その過程を、このドキュメンタリー映画を通して感じとっていただければと思います。