学生に薦める本 2021年版
越智 敏夫
今年は2冊だけ。竹宮惠子と萩尾望都。それぞれの自伝(的なもの)。しかしこの2冊を熟読して、比べてみてもらいたい。熟読する時間がなければ図書館でちょっとページをめくるだけでも人間社会について豊饒な思索に浸ることができるはず。特に「他人との関係」について悩んでいる人にとっては(即物的なものも含めて)いろいろと役に立つだろうし、あるタイプの考え方を身につけるきっかけになるような気もする。怖いけど。
ほんとは今年の本欄では「マンガ編集者という仕事」で5冊くらい紹介するつもりだった。多くのマンガ編集者が回顧録を書いていて、それらはけっこう面白いし、マンガ家本人のエッセイにしても日常を語ったものは、ほぼ編集者との泥沼の闘争史みたいなものである。おりしも本学図書館にもコミック・コーナー【No.9】(ナンバーナイン)が開設されたことだし、良き哉と。
ほんとは文章の最後あたりでマックス・パーキンズ(Max Perkins 1884-1947:各自、調べてください)なんぞを紹介し、「編集者とは」みたいな話に広げてちゃんちゃん、とまとめるとかっこええやろ、という野卑な企図でもありました。ところが全体の一冊として竹宮惠子の本とともに紹介しようと思っていた萩尾望都の本があまりに衝撃的で……。全体のテーマも変わりました。
ほんとは(←多いなあ、今年は)この拙稿も図書館に提出すべき締め切り日を大幅に過ぎてしまった。すいません。レポート提出の期限は厳守するようにと学生にいいながら、この様である。しかしこの遅れの理由はひとえに萩尾の書籍の刊行(2021年4月30日)を待っていたからであり、そのあげく本文章のテーマまで変わった……と言い訳の多い今年のテーマは何だろうか。「人間の業苦」2冊かなあ(怖)。
『一度きりの大泉の話』
- 萩尾望都 河出書房新社 2021年
竹宮は上掲書で萩尾のことを「萩尾さん」と書き、萩尾は竹宮のことを「竹宮先生」と表記する。本当はこのあたりについてもいろいろと書きたいところだが、話を進める。
こうして竹宮についてすべてを忘れて生きてきた萩尾だが、2016年に竹宮の本が出版されると生活が一変する。竹宮の自伝本について「別にご自分のお話をされるのは構いません」と書いたあとの萩尾の文章が以下(p.4)。
地獄である。これは前書きのなかの表現であって、本文にはもっとひどい状況が描かれている。こうした世間からのアプローチが絶えず、まともな生活も送れないので、「仕方がない、もう、これは一度、話すしかない」と上記の佐藤にインタビュアーを依頼し、誕生したのが本書である。
もちろん本書の表面上の中心は竹宮との絶縁についてである。その原因を萩尾の認識をもとに無理に要約すれば、竹宮と増山が萩尾のマンガを竹宮作品の盗作だと決めつけ糾弾したこと、である。
1973年、萩尾は竹宮との共同生活を解消していたとはいえ、竹宮と増山が共に暮らすマンションの近くのアパートに萩尾は暮らしており、まだ相互の行き来もあった。同年3月のある夜、萩尾は竹宮、増山のマンションに呼び出される。そして萩尾の「ポーの一族」シリーズ最新作「小鳥の巣」が、竹宮が1970年ころから準備していた「風と木の詩」に酷似していると二人から糾弾される。
「頭が真っ白」になり「呆然として」アパートに帰った萩尾はその夜に二人から言われたことをクロッキーブックに書き出し、自分の作品が盗作ではないことを示すためには何を説明したらよいか、「ぐるぐる」と考える。
3日後、竹宮が(めずらしく増山をともなわず)一人で萩尾のもとを訪れ、「この間した話はすべて忘れてほしいの、全部、何も、なかったことにしてほしいの」と言う。驚いている萩尾に竹宮は「私が帰ったら、これを読んでください」と手紙を置いて帰っていく。その手紙を読んだ萩尾は「あの夜以来あまりよく眠れなかったのですが、全く眠れなくなって」しまう。さらには貧血で倒れ、目は充血し、心因性障害からマンガ家にとって最も重要な視覚異常にまでいたる。
この竹宮の手紙の内容についてはぜひ本書を。怖くて引用できない。またこれらの経緯についても、私の下手な要約などで理解するよりも、本人の記述をぜひ直接読んでもらいたい。ただただ人間の業に恐怖するのみである(上記4段落、pp.147-159)。
竹宮、増山と絶縁した後も、萩尾の「トーマの心臓」が「風と木の詩」の盗作であるというような「風の噂」も萩尾のもとに流れてくる。
おそらく多くのマンガファンは、萩尾の「11月のギムナジウム」(『別冊少女コミック』1971年11月号掲載)は「トーマの心臓」(『週刊少女コミック』1974年19号掲載)の原型だと思っていたのではないか。しかし萩尾によると「トーマ」の原案は「ギムナジウム」とは別に、かなり以前から準備されており、ペン入れした下絵が300枚ほどは描かれていたとのことである(p.67)。
その「トーマ」の下絵の一部も本書には収録されている。さらにはその下絵を誰がいつどこで読み、どんな感想を言ったかということも萩尾は細かく正確に回顧、紹介している。その他、大泉とそれに続く時期の萩尾の表現活動について外部の者が少しでも誤解しそうなこと(端的に言うと少しでも盗作の疑いがかかりそうなこと)について、友人のマンガ家などにメールで確認し、その詳細な、というよりも具体的なメールの文章の引用も含め、こと細かく検証している。
これらのページが結果として意味するものは、自作に対するあらゆる「難癖」の拒絶であり、自分が盗作などしていないという無実の検証ではあるだろう。より具体的には「トーマの心臓」も含めて盗作だと噂された萩尾の作品は、時間的にも「風と木の詩」より先に構想されており、内容やテーマも竹宮や増山のものとは無関係だ、という証明である。
しかしそんな下世話な役割を萩尾の記述に見出すよりも、本書で萩尾が表明しているのは、自らの創造性と独創性に対する自らの信頼だと読むべきだろう。さらに読者が思いいたるのは、そうした経緯や説明が付された萩尾の作品群が、竹宮どころか、他のすべてのマンガ家の作品に比べて、いかに異質であるか、いかにそれまでのマンガ表現を革新しているか、いかなるマンガの新たな地平を切り開いていたのか、ということである。
本書を読んでそれらに気づくころには、「マンガの革命」とは何か、それを本当におこなっているのはどういう人たちなのか、という問いのようなものまで伝わってくる。
以上が本書の内容である。萩尾という天才でさえ、こうした文章を著わすことに多大な労力をはらうという事実。天才だからこそ、ともいえるだろうが、この事実を前にして感動しないはずがない。
そのうえで私たちは竹宮の書籍をどう読むべきか。それはみなさんが図書館で考えてみてください。
以上で言いたいことは言ったので、以下、おまけ。
『ポーの一族』1~3巻
- 萩尾望都 小学館 1998年(初版1974年)
萩尾と竹宮の関係や大泉サロンについては、もちろん外部の他者によって書かれた書籍も多くある。しかしそれらの著者には申し訳ないが、そこでの記述が事実認定において、また当事者たちの行為の意味づけにおいて、いかに不正確でまとはずれだったか、というのも、この当事者二名による著作でよくわかる。
もちろん何かを想像で書いたり、欠けたものを何かで埋めて全体を組み立てる作業は大切ではある。しかしこの萩尾の書籍の刊行後、それら不正確な書籍の著者たちがネット上などで多くの言い訳や弁解を展開しているのを見ると、言説の責任についても考えてしまう。ある批評家が「萩尾の本の刊行によって(自分が語ってきた)大泉サロンの神話は完成した」というようなものも読んだ記憶もあるが、人間、どこまで無知で無恥になれるか、という気さえする。
書籍でさえこれである。ましてや二人の関係についての wikipedia の著述など、まとはずれどころか、妄想と虚偽による犯罪的な産物といってよい。wiki を信じることがいかに危険なことか。自戒もこめていうけれど、みなさん、気をつけましょう。
【おまけ2】
竹宮の「マネージャー」増山法恵について上述したが、萩尾には城章子という存在がある。城についても両著作では多く触れられている。大泉サロンに参加した当初はマンガ家を目指していた城は、ある時期以降、萩尾のマネージャーを務めるようになる。萩尾によれば大泉の「全ての事情を知っている」のが城である(p.318)。
萩尾の著書には「大泉サロン解散」の理由を竹宮が話しているということを山田ミネコから聞いた城が「カンカンに怒りました」という箇所もある(pp.254f.)。ほかにも、竹宮の自伝本を郵送で贈られた萩尾が竹宮の名が記されている封筒を開封することさえできなかったため、城がそれを開封したのち中身を読み、「萩尾はもう関わりがないし、これからも関わりません」という短文を添えて竹宮に送り返すシーンもある(p.318)。
萩尾によるこれら城に関する文章や、竹宮の増山に関する記述などを読むと、少女マンガ家のマネージャーというのは、手塚治虫やさいとう・たかを、石ノ森章太郎など、少年マンガ家のマネージャーとはかなり異なる仕事のように思えてくる。が、これもまた別の話ですね。
【おまけ3】
竹宮と萩尾のデビュー当時の担当編集者が『別冊少女コミック』(小学館)の副編集長だった山本順也(1938-2015)である。竹宮本の本文では「Yさん」と表記されている山本は萩尾、竹宮だけでなく、大島弓子、樹村みのり(1949-)、倉多江美などにも同誌に執筆させた。
萩尾はデビューこそ講談社だったものの、同社はその後の作品を立て続けにボツにする。まだ福岡にいた萩尾はそのボツ原稿の束を、先に上京していた竹宮に郵送する。竹宮からその原稿を受け取った山本は(おそらくは)即座に全原稿の買い取りを決める(竹宮文庫本 p.63、萩尾本 p.38)。
のちに山本は萩尾に対して「お前なんか、もういらねえよ」と言い、そのことに萩尾はショックを受けたとも書いてはいる(萩尾本 p.114)。しかしその後、山本は萩尾に「ポーの一族」の当初のプロットを整理させ、それをもとに『別冊少女コミック』での連載を決定。そして1974年5月末、小学館として初の少女マンガ単行本となる『ポーの一族』第1巻の初版が刊行されるが、それを山本は当時としては破格の3万部と大量に刷る。しかしそれらは発売後3日ですべて売り切れ、即日、重版がかかる(萩尾本 p.231)。
この萩尾の才能と人気を他社が見逃すはずもなく、講談社は自社に呼び戻そうと引き抜きにかかる。萩尾は山本に相談したうえで講談社と面談。萩尾の弁によると、コメディを書かされそうだったので移籍は断ったとのことである。その話を聞いた山本は、それまで1ページ3,000円だった萩尾の原稿料を、通常は引き上げるときには500円、1000円単位だったにもかかわらず、一挙に倍の1ページ6,000円に増額する(萩尾本 pp.234-236)。
小学館退社後の山本は2000年4月、竹宮と同時に京都精華大学芸術学部マンガ学科の教員となり、後進の指導にあたる。竹宮はそれを「腐れ縁ですね!」と正直によろこぶ(竹宮文庫本 p.250)。
竹宮と萩尾の二冊の著作はすべてにおいて印象が異なるが、この山本の人物像に関する描写だけは、ずれがない。この点も強く印象に残る。
冒頭で記したように、ほんとは(←しつこい)こうしたマンガ編集者を中心にして書くつもりだった。山本以外にも、萩尾に「百億の昼と千億の夜」(光瀬龍原作)を全盛期の『週刊少年チャンピオン』に掲載させた秋田書店の壁村耐三(1934-1998)や、『週刊少年ジャンプ』の一回目の全盛期を作り上げた西村繁男(1937-2015)などについても多くの書籍があり、彼ら自身による回顧録などもある。そのうち紹介したいとは思うものの、ぜひそれらも読んでみてください。
【おまけ4】
この拙文全体を読んでいただければ、竹宮と増山に対する否定的な文章に読めると思う。ご本人たちがこの文章を読むことはないだろうが、表現されたものに作家は責任をもたないといけないので、私の否定的な記述もご寛恕いただきたい。ただ竹宮ファンの方々には本当に申し訳ないと思う。
そのかわり、と言うわけではないが、実は竹宮を見かけたことは一度ならずあり、そのときの印象は「本当に良い人なんだなあ」というものだったということも書いておきたい。
竹宮を見たのはすべて有楽町の今は亡き有楽シネマだった。名画座からATG上映館、BOW系、名画座へと変わり、よくわからんややこしい映画館だったが、大学院への通学の乗り換え駅にあった(つまりは通学定期で途中下車できる)こともあってよく行っていた。
そこで竹宮を最低2回は見た記憶があるが、初めて見たときは映画の休憩時、「たけみやけいこ様、お電話が入っております」というアナウンスが流れ、こっちは「ああ同姓同名か」と思っていたら本人が前の席から立ちあがってロビーに走っていった。その小柄な感じも意外だったが、試写会ご招待などでなく、一般人にまじって竹宮が映画を見ていることもちょっと意外だった。
実はこの有楽シネマでの竹宮電話呼び出しのエピソードは僕の友人も経験している。ということは、かなりの頻度で竹宮は有楽シネマで映画を見ていたのではないかと思われる。もちろん当時は携帯電話もなく、おそらくは自分のプロダクションか編集者などから急ぎの連絡が入る可能性があり、自分がこの時間は有楽シネマにいることを事前に伝えていたのだろう。
ともあれ、自分のマンガを作り上げるために、とんでもない多忙さのなか、足しげく映画館に通う竹宮に、尊敬の念をいだいたのは当然である。また、そこで見かけたうちの一度はロビーで自分のファンと楽しそうに談笑している光景だった。それらのときの印象は前述したとおりである。
【おまけ5】
萩尾が『別冊少女コミック』1972年9月号から掲載した「ポーの一族」の第1話を山岸凉子がアシスタントとして手伝っている、ということもこの本で知った(p.127)。
この連作を読んだ人は知っているとおり、「ポーの一族」は本編の連載開始前、「すきとおった銀の髪」「ポーの村」「グレンスミスの日記」というタイトルのもとで、スピンオフ3話が先に発表されている。そのあたりも萩尾の稀有な才能と構成力を感じさせるが、その連載途中に掲載された本編第一話(変な表現ですが)を山岸が手伝ったというのも意外だった。それにあの山岸が萩尾のページのどこをどう手伝ったのか。たぶんファンのあいだでは有名な話なんだろうとは思うが、個人的には謎である。



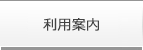
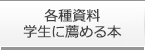

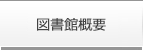



その中核をなす萩尾望都(1949年5月-)と竹宮惠子(1950年2月-早生れで同学年←これは大事)。個人的にはこの二人より数年早く生まれた大島弓子(1947-)や山岸凉子(1947-)、一学年下の倉多江美(1950-)のマンガのほうが好きだった。
しかし萩尾がブラッドベリの短編をマンガ化したもの(「霧笛」と「みずうみ」)を読んで驚き、それ以来、萩尾の作品はデビューまでさかのぼって貪るように読んでいった。好き嫌いを超え、なにか義務のように感じていたのかもしれない。ブラッドベリものだけでなく、「11人いる!」や「百億の昼と千億の夜」など、萩尾のSF作品の質にも圧倒されていた。
それに比すると竹宮のものはほとんど読んだことがない。いくつか読んではみたけれど、自分に合わない。向いてないと感じたのだろう。本流SFである「地球へ…」などは掲載誌を毎号購入していたものの、竹宮のページは読み飛ばしていた。ごめんなさい。そういう越智のマンガ選好を前提にして以下の部分は読んでもらいたい。
萩尾と竹宮はそれぞれ福岡と徳島の出身である。当然のように二人とも早熟な天才(とはいえ、こうした表現が本人たちにとって、いかに的外れで暴力的かということも、この二冊を読めばわかると思う)であって、1970年、ほぼ同時に上京したときには二人ともすでに商業誌に作品を掲載している。その二人が練馬区南大泉にあった「二軒長屋の片方」を借り、1972年まで共同生活を送る。
この2年間、他の少女マンガ家(やその予備軍)たちもこの場所を頻繁に訪問、いつしかそこは「大泉サロン」と呼ばれ、そこに集った彼女たちはその後の少女マンガ界を牽引し、それはまるで少女マンガ版「トキワ荘」のようであった……というのが世間(というかマンガファン)の一般的な認識だろう。
本書はその竹宮の自伝。デビュー直後の竹宮を講談社、集英社、小学館の大手三社が「取りあい」、談合の結果として小学館に「お世話になる」ことに落ち着くというシーンから始まる。最初に読んだとき、このシーンの意味についてもっと考えていればよかった。とはいえ、そういう「隠し玉」のようなシーンを除くと、全体の内容はおそらく読者の予想を大きく超えることはない。
大泉サロンについても上記のような世間一般の「認識」を大きくはずれることはないし、どちらかというとその世間的な共通理解を補強するような感さえある。ああ、やっぱりそうだったか、と。政治闘争に明け暮れた徳島大学教育学部を中退、社会の革命という使命を捨て、マンガの革命を東京でめざす竹宮を中心とした「青春群像」である。
その竹宮。上京当初は作品も順調に量産できていた。しかし萩尾と暮らすうちに、二人の関係、より具体的にいえば竹宮の萩尾に対する「ジェラシー」が原因となり、しだいに精神に変調をきたすようになる。以下、本人の弁(文庫版 p.189)。
こうして竹宮は萩尾に「距離を置きたい」と言って転居し、二人の関係は終わる。おそらく本書を読むすべての人間の最大の関心はこの別離の経緯についてである。どうして二人は縁を切ったのか。その関心や疑問に対して、本書における竹宮による説明はじゅうぶん納得できるものだろう。それだけに、この経緯を竹宮が「ジェラシー」を原因として「正直に」話しているということが、本書の刊行時、他の多くの書評でも好意的に取り上げられていたように思う。
しかし萩尾から見た光景はまったく違うものだった。というよりも、光景の違いなどというものではない。その点については以下の萩尾の書籍のところで。
萩尾に関する叙述以外の部分でこの自伝が興味深いのは、竹宮の「マネージャー」増山法恵(1950-)についても大きく紙幅が割かれている点である。竹宮によって増山のことがここまで書かれているのを僕は初めて読んだ。
増山もマンガファンのあいだでは有名な存在ではあるが、いったい彼女は何者なのか。竹宮のマネージャーと説明すれば楽だが、本書を読むといっそう混乱する。プロデューサーでもあり、原作を担当する共同制作者のようでもある。もちろん竹宮による「マンガの革命」に共鳴する同志であり、革命戦士でもあるだろう。
しかし増山が登場する場面によっては、その受ける印象をひどく失礼な言葉で表現すれば、彼女は竹宮に作品制作どころか、その生き方さえ命令する「女王様」のようでさえある。そういうときの竹宮はまるで増山の言うままに動く操り人形のように見えてくるほどだ。最初は萩尾の友人として竹宮の前に現れたこの人物についても、雑誌やネット上などでは、おそらくご本人も含めていろいろ書かれていると思うものの、それらを読むのも怖い。
ともあれ、本書の本人による文庫版あとがき「炎が煌めく瞬間を」は、「過去の話だけれどいろいろな人に話すと、面白い、と言ってもらえる」と始まり、「この本がいつか誰かを励ますことや、若い日のきらきらした炎の煌めきを応援することにつながれば、何よりのよろこびです」と終わる。学長も務めた京都精華大学を定年退職する直前に書かれた、いかにも大学教員らしい引退挨拶である。
全編に漂うこうした文体の「やさしさ」や、上記の本書巻頭部分の「談合」シーンなどに、だまされたこちらが悪いのか、その分、萩尾の以下の本との内容や温度の差が激しい。
竹宮に悪意はおそらくないだろう。萩尾に対する畏敬の念に近い心情さえ正直に吐露されている。単行本の最終章では「東京都練馬区大泉のあの"サロン"を共有していた萩尾さん、増山さんに『ありがとう』を捧げたい」とも書いている。ただ、これを人間がどこまで冷たくなれるかの標本とみるか。それとも竹宮の人柄の良さとみるか。
ということで、この拙文をここまで読んで、少しでもこの二人、この二冊に関心をもったら、今すぐ本学図書館の書架に走り、実物を手に取ってもらいたい。それも前提に、以下、つづく。