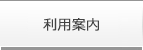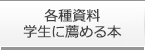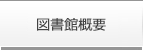図書館HOME>各種資料・学生に薦める本>学生に薦める本
学生に薦める本 2017年版
越智 敏夫
苦行としての読書、5点。読書とは面白い体験のはずだし、面白く読めるものほどそれが結果的に役に立つから読め、みたいなものばかり推薦してきたこれまでの自らを恥じる次第です。今年は読むこと自体、もう何を意味しているのかわからんほどつらくてきついものを推薦。でもやっぱりなんらかの「意味」はあるように思いたい……けど。
『土』
- 長塚節 新潮文庫 1912年(単行本)、1950年(文庫化)
北関東、茨城県南西部、鬼怒川のほとり近く、百姓の勘次、娘おつぎ、がき与吉、亡妻お品の父卯平の4人家族。近隣住人も含めて登場人物全員が貧窮のどん底。明治時代の日本人のほとんどが、江戸時代とほぼ同様、実質的には農業奴隷状態だったことがよくわかる書。とにかく貧乏な、というより、餓死しない程度のぎりぎりの生活が分厚い文庫本一冊つづく。読み終わると「ああ、現代のわれわれは救われているなあ」と妙に自信のつく一冊でもあります。でも本当に現代社会は当時から進歩したか、と社畜が問うことも可。
『白き瓶:小説長塚節』
- 藤沢周平 文春文庫 1985年(単行本)、2010年(文庫化)
その長塚節の人生を藤沢周平が描く伝記的小説。藤沢が書いているのだから読みやすいだろうと思うと、これが地獄の一丁目。なにせ長塚ですからね。『土』があまりに陰惨な小説なので、鬼怒川沿いの人たちは長塚をなるべく歌人として紹介したがっている、ということを何かで読んだことがあるが、歌人としてもそのキャラは鬼怒川のイメージを明るくするものでは決してないですよ。その暗い長塚が「短歌とは何か」と延々悩みつづけるわけだし。そういうスコラティックなところに関心がないと、何を読んでいるのかわからんようになる奇書。どんどん紹介される短歌を読んでいくだけで脳が沸く。あ、それから「瓶」は「びん」ではなくて「かめ」なので。一応。
『黒死館殺人事件』
- 小栗虫太郎 河出文庫 1935年(単行本)、2008年(文庫化)
MS-IMEは「国士館殺人事件」と一発変換するけれど、そんなことはどうでもよろしい。S・S・ヴァン・ダインの『グリーン家殺人事件』のパクリとも言われるけど、あっちの探偵、ファイロ・ヴァンスに比べると、こっちの法水麟太郎のほうがふつうの探偵に見えてくるから不思議である。でも、そんなこともどうでもよろしい。ほぼ同時期に発表された夢野久作の『ドグラ・マグラ』(1935年)、また中井英夫が本作へのオマージュとして書いた(と言っていいのか?)『虚無への供物』(1964年)とあわせて、日本探偵小説の三大奇書などと言われているそうですが、そんなこともどうでもよろしい。とにかく読みにくい本だけれど、それが何、と思ってなんとか読み進めるうち、「衒学趣味:ペダントリー」と言う単語を爆殺したくなってきます。え、殺人事件の謎解きですか、そんなものもどうでもよろしくなる好書(大嘘)。
『浮標』
- 三好十郎 ハヤカワ演劇文庫 1940年(戯曲初演)、2012年(文庫化)
これもきついですよ。短い戯曲なので、あっという間に終わってくれそうに思えますが、もう最初の数ページを読むだけで、比喩ではなく本当に息が詰まりそうになります。なんというか、登場人物がありとあらゆるところで不幸の鍵を探してます。著者本人の弁によるとこの戯曲で描かれているのは、満州事変の少しあと「重病の先妻『みさを』をかかえて千葉市の郊外の海岸に住んでいたころの身辺のことで、ほとんど当時のありのまま」だそうです。で、それを書いたのは「『みさを』が死に、数年を経て、支那事変が拡大してしまつて、不安は既に不安という程度に」とどまらなくなったころで、「つまり私は私個人にとつても客観的にも、ドス黒い時代のことをドス黒い時代の中で」書いたそうです。もうこれだけで窒息状態ですが、本作の初演は1940年3月、築地小劇場で八田元夫(ちなみに旧制新潟高校初代校長八田三喜の長男)による演出であったこと、また主人公「五郎」を演じた丸山定夫(ちなみに松山市北京町生まれ)は三好の長年にわたる親友であり、のちに丸山は移動演劇「桜隊」隊長として広島の原爆によって、阪妻版『無法松の一生』の吉岡夫人役、園井恵子らとともに死をとげることなども知ってしまうと、もう彼岸は近いのでありました。
『失われた時を求めて<1>第一篇「スワン家のほうへ1」』
- プルースト 光文社古典新訳文庫 1913年(原著)、2010年(文庫化)
このところ、ついつい早い時間にベッドに入ってしまい、夜中に「寝れんぞ」とか思いながらも、でも起きる気にもなれなくて、うだうだしている本人のうだうだした意識と記憶の描写が100ページ続くことにあなたは耐えられるか。ところが焼菓子のプチ・マドレーヌが紅茶に落ちてふにゃふにゃになったのを食べた瞬間、その味と匂い、おいしさから、自分の過去がすべてよみがえる。そのあとは、まあこれもなんと言いましょうか意識のジェットコースターのような小説に変貌するんですね。みなさんも小さい頃に使ったバナナ味の歯磨き粉の味とか覚えているでしょう。あれですよ、あれ。「主人公が何をしたか」をほぼすべて省略、「主人公が何を思いだしたか」だけで勝負する大長編。僕は井上究一郎の訳を読んだ世代だけれど、鈴木道彦訳のほか、おそらくはそれぞれの訳者による違いが果てしなく大きいのではないかと思われる作品。そりゃあ人間の頭の中を訳すわけだから。仏語原文を初めて見たときの驚きも忘れがたい。そもそも文章が切れてないのですよ。英語で言えばカンマばかりでピリオドがない。そんなもん、どうやって日本語にするんや。ということで訳者の方々が神に見えてくるころ、この読書体験に没頭したことで失われた時について、粛然とせざるをえなくなるという書。この光文社版も刊行中です。2017年4月現在、5巻まで出てます。計画では全14巻だそうです。どうだ、まいったか。